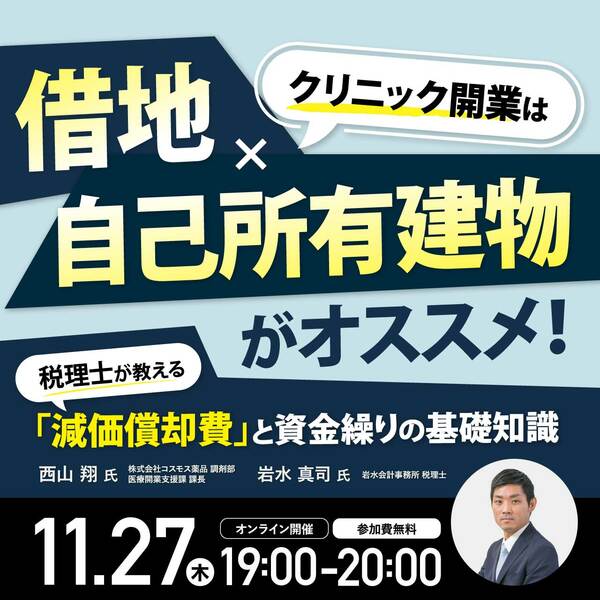「開業医」と「勤務医」の決定的な違いとは?
「開業医」と「勤務医」の決定的な違いとして挙げられるのが、収入の原資です。開業医の場合、収益は自分のクリニックに来院した患者様からの「医業収益」が原資となります。
厳しい話をすると、「診療人数×単価」という数字で自分の報酬・待遇が決定するため、運営が軌道に乗り一定数の患者来院があれば利益も大きくなる反面、赤字経営となればスタッフの給与と家賃を支払うために自分の生活を切り詰め、果ては空き時間を利用して他医療機関で「勤務医」として報酬を得るという残酷な現実もありえます。
開業医に必要なスキルとしては、専門外の患者様も来院することから、自分の専門以外にも浅く広い医療知識が必要です。他診療科の基本は理解しておくとよいでしょう。
これ以外にも、スタッフの採用・勤怠管理から有給休暇や退職金・採用という人事労務、キャッシュフロー管理や融資、給与・賞与などの財務、診療報酬請求や医療に関する法律・行政責任などの医事、最終的には患者様・スタッフを魅了するためのコミュニケーション力や人柄の醸成など、勤務医とは異なるスキルが必要となります。
ここからは、それぞれの項目についてみていきます。
スタッフの採用・勤怠管理など
まず大前提として、自分自身の心身の健康が必須です。これがなければ事業は始まりません。疾病がある場合は、その状態を安定させることが先決です。
同時に、スタッフを雇用・採用して組織運営をするには、スタッフのこれまでのキャリアや人柄はもちろん、家族背景などをしっかりと理解する必要があります。勤務医時代なら同じ「労働者」という区分ですが、クリニック開業となると労使関係になりますので、スタッフは有給休暇(最低でも5日取得)の取得が可能となり、経営側は、スタッフや家族の体調不良などによる突発的な欠員に備えた人員配置の管理、夏季休暇・年末年始の休暇、出産・育児・介護休暇の規定などの知識を実態として学ぶ必要があります。
医師という立場ではなかなか実感できませんが、看護師・医療事務などのコメディカルは近年ではこうした待遇、時間外労働などには敏感ですので、勤務医時代より勤怠管理や労働基準法などの学習が必要です。
キャッシュフロー管理や融資、給与・賞与などの財務関連
勤務医時代にも確定申告する方は多いですが、ほとんどは給与所得で、難易度はさほどでもありません。しかし開業後は、法人化するまでは個人事業主としての事業所得になりますので、税金関連(住民税・所得税など)について実践レベルの知識が求められます。
勤務医時代は、常勤先からは「固定給+時間外労働+インセンティブ」と「賞与」が支給され、同時に所得税・住民税・社会保険・年金などが自動的に控除されて給与が支給されていましたが、開業医の場合はこうした報酬を支給する側になるため、金銭の流れや税金・社会保障に関しての知識の習得が必須です。
たとえば、看護師常勤1名を月給26万円で雇用する場合の負担額は、月給26万円に加え、社会保険料・年金保険料の折半分を含め約32万円となりますが、勤務医の方はそのような知識を持たないほうが大半でしょう。
同時に、自分を含めた報酬の原資となる診療報酬ですが、受診時には3割以下が手元に残り、残りの7割以上は診療報酬請求をしてから2ヵ月後の下旬に入金されるため、月ごとの収支・キャッシュフローを掌握する必要があります。クリニックにおける金銭は、人体でいう「血液」となるため、枯渇すれば臓器機能不全となり、クリニックは黒字倒産しかねません。
診療報酬請求や医療に関する法律・行政責任などの医事
勤務医時代は、多くの医療機関においては入院患者のDPC入力程度で診療報酬請求を行っていますが、その裏では毎月10日まで、医事課職員が血眼となり診療報酬請求業務に追われている現実があり、お膳立てされています。
反面、開業した場合には、医療事務職員も連日の診療終了後や毎月10日前にはレセプトチェック時に病名チェックを行っていますが、本来であれば医師自らが自分の診療行為やオーダーした検査・処置に対して責任をもって病名を付けることが原則です。
同時に、自分の診療内容が患者様にどれだけの金銭的な負担となるか、検査料金や管理料、各種加算の算定等によるクリニックの利益等を掌握する必要があります。
お金のトラブルも、患者クレームの要因として少なくありません。そのため勤務医時代から、自分の診療においてどの加算が算定となるのか、レセプト点数の概要を掌握する努力も必要です。とくに2年に1回の診療報酬改定においては、診療報酬に関する知識がクリニックの経営を左右します。
心療内科的な経験とコミュニケーション能力
スタッフが退職しないための組織風土作り、クリニックへ来院した患者様に定期通院してもらえるようになるには、地域との連携を図り「かかりつけ医」といった地位を確立する必要があります。
そのうえで「コミュニケーション力」のウエイトが、勤務医時代よりもさらに高くなります。コミュニケーションが苦手だと感じても、患者様・ご家族を心療内科的な知識・配慮をもって診療に当たるだけで経営が好転することは多いのです。
クリニックを受診する患者様の多くは、なにかしらの悩み・不安を抱えてクリニックの扉を開いています。そのため、医師の言動は、不安を抱える患者様・ご家族の心理・満足度に大きく影響します。
患者様の状態や疾病に関係なく、患者様との関わりに喜びを感じられるなら、自然と患者様・ご家族の求めや訴えを把握・解決しようとする意欲や能力が向上するでしょう。その結果、関係性も良好となり、それがよい循環を生んで、医師自身も温かい人間性が醸成されていくのです。
目の前の患者様の安心感・喜びという変化こそが、本来あるべき医師としての報酬であり、それが診療報酬という経済的なインセンティブにつながるといえます。こうしたコミュニケーションを、勤務医のうちから心がけておくだけで、結果は大きく違ってくるでしょう。
開業前のキャリアや勤務先でのモードチェンジ
いざクリニックの経営がスタートすると、医学的知識・技術の習得や新規検査や治験などのアップデートが、他業務と比較しておろそかになる傾向があります。
可能であれば、開業前からクリニックで経験を積み、自身が開業するクリニックのイメージ作りや、模擬練習をしておくことを推奨します。また、基幹病院に勤務している場合は、検査を実際に担当する看護師や臨床検査技師などの声掛けの見学、医事課(できれば事務長・医事課長など)の診療報酬における増収対策などについても、取り組んでおくとよいでしょう。
武井 智昭
株式会社TTコンサルティング 医師