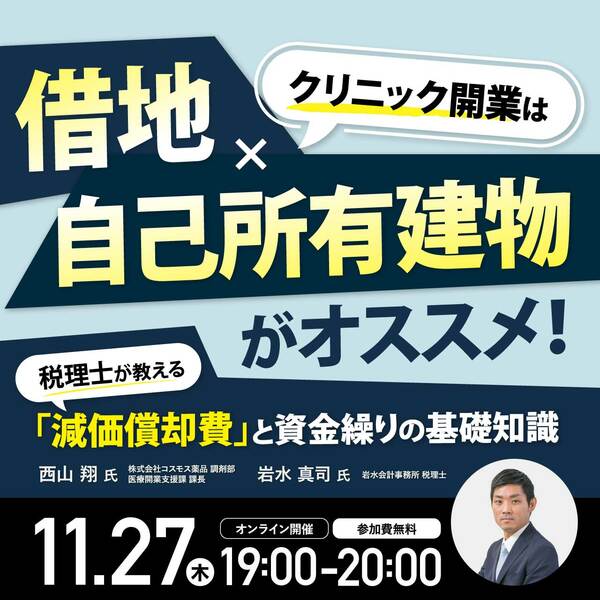医療広告ガイドライン違反の発見ルート
医療広告ガイドラインへの違反は、自治体の調査のみならず、一般ユーザーによる通報、厚生労働省による「医業等に係るウェブサイト調査・監視強化事業」(2017年から)によって発見されます。このなかで、通報件数が増加しているものが、一般ユーザーからの不適切なwebサイトを通報する「医療機関ネットパトロール」です。
医療機関のHP内容に、医療広告ガイドライン違反があると判断された場合、行政による審議を経て、医療機関が所在する地域の保健所、あるいは厚生労働省からパトロールを委託された「デロイトトーマツコンサルティング合同会社」から改善を促されます。
改善点は文書などで明確に指摘されますので、この指示に早急に従えば大きな問題にはなりません。しかし、虚偽広告や違反を一定期間改善しない場合は、前述の刑罰に加え、管理者の変更命令、クリニックの開設許可の取り消しなど厳しい行政処分が課されることになっています。
医療広告の対象範囲外であるもの
医療広告の対象範囲外になるものとしては、下記のものがあげられます。
●新聞等の記事
●患者自らのSNSなどへの投稿・発信
●院内の掲示物、クリニック紹介のパンフレット
●医療機関による採用広告
そのため、SNSでの患者様からの投稿やクチコミに関しては、真偽性は問われるものの、規制対象外であるために、悪いクチコミが発生したとしても取り消すことは困難となります。
広告が可能とされていない事項の広告の事例
以下は、広告が可能とされていない事項の広告の事例です。細かい規定があるため、十分な注意が求められます。
◆医療従事者の専門性資格について
厚生労働大臣が届出を受理した専門医資格については、広告が可能とされています。しかし、「日本小児科学会認定 小児科専門医」という正式名称はOKですが、「日本小児科学会認定 専門医」はNGとなるため、注意が必要です。
◆専門外来について
クリニック名の上部に「〇〇専門外来」「〇〇外来」と表記することはNGとされています。一方で、クリニックの診療内容に「新型コロナウイルス感染症 後遺症外来」などといった記載をすることは規制の対象とはなりません。
◆メディアの掲載情報
「当院医師が○○(メディア)に出演!」といった、メディアの掲載情報に関しては原則NGです。
◆提供する医療と直接関係ない誘引事項
「当院で自費のメニューをおこなった方には、次回の割引券を贈呈します」「お子さんが予防接種をしたら、院内のガチャガチャ用のコインをプレゼント!」などは、提供する医療の内容の誘引と考えられます。このような医療行為と直接関係のない事項の記載は禁止されています。
◆内容が虚偽にわたる広告
医療は不確実なうえで実施されるため、「すべての治療手術を1日で終わらせます」「当院の治療は絶対に安全です」といった確定的な表現はすべてNGとなります。
同時に、「94.7%の患者様に満足していただいております」というような表現には、調査方法を明記する必要があります。
◆他の医療機関と比較して優良であることを示す広告
「他院Aでは〇〇%、Bでは〇〇%など」や、「都内有数の実績数を誇ります」「最高・最良の医療提供です」などの他院との比較は、いかなる部分・内容でも禁止されています。
◆著名人などの診療、受診の強調
「〇〇大学主任教授の特別外来」「モデルの〇〇さんが定期受診」といった、治療とは関連がない宣伝広告は禁止されています。
◆医療広告ガイドラインを守っている事の強調
医療広告ガイドラインに違反への通報を避けるために、フォントの拡大や、マーカーによる強調で「医療広告ガイドラインを遵守しています」と掲載することも誇大広告に該当するため、禁止事項となっています。
2024年3月に追加された広告制限
2024年3月に追加された広告が禁止される内容(誇大広告)として、「提供される医療に関しての内容を誤認させるような内容」「処方箋医薬品を必ず受け取れる期待をさせる広告」が追加となりました。また、オンライン診療に関しての現況の説明追記も要します。
その背景として、本来は糖尿病治療薬であるGLP-1製剤(自己注射や内服)が、最近では自費診療としてダイエット・痩身目的での過剰な処方・受注回数増加目的での過当競争が問題視され、トラブル相談件数も増加しています。
このような背景があり、「減量が可能なホルモン」「痩身の新規医薬品」といった誇大表現の使用禁止となり、保険適用されていた製品が自由診療でも手軽に使用されるようになるという、誤解を招く表現が禁止されました。
処方箋医薬品等を必ず受け取れると期待させる表現を避けるため、保険診療・自費診療ともにオンライン診療における処方箋受取に関しても追記が必要となりました。
具体的には、処方箋医薬品の受け取りには、医師の診察が必要である旨と、薬の受け取りの説明の付近に「医師の判断によりお薬を処方できない場合があります」などの文言を最低限記載することが必要となりました。
また、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」により、初診での処方が禁止されている医薬品や、「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」を処方する場合は、オンライン診療において初診では処方できない旨、または、オンライン診療において処方できない場合がある旨を明記することが望ましいとされています。
参考文献
厚生労働省『医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)』
(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001235202.pdf#page=17)
武井 智昭
株式会社TTコンサルティング 医師