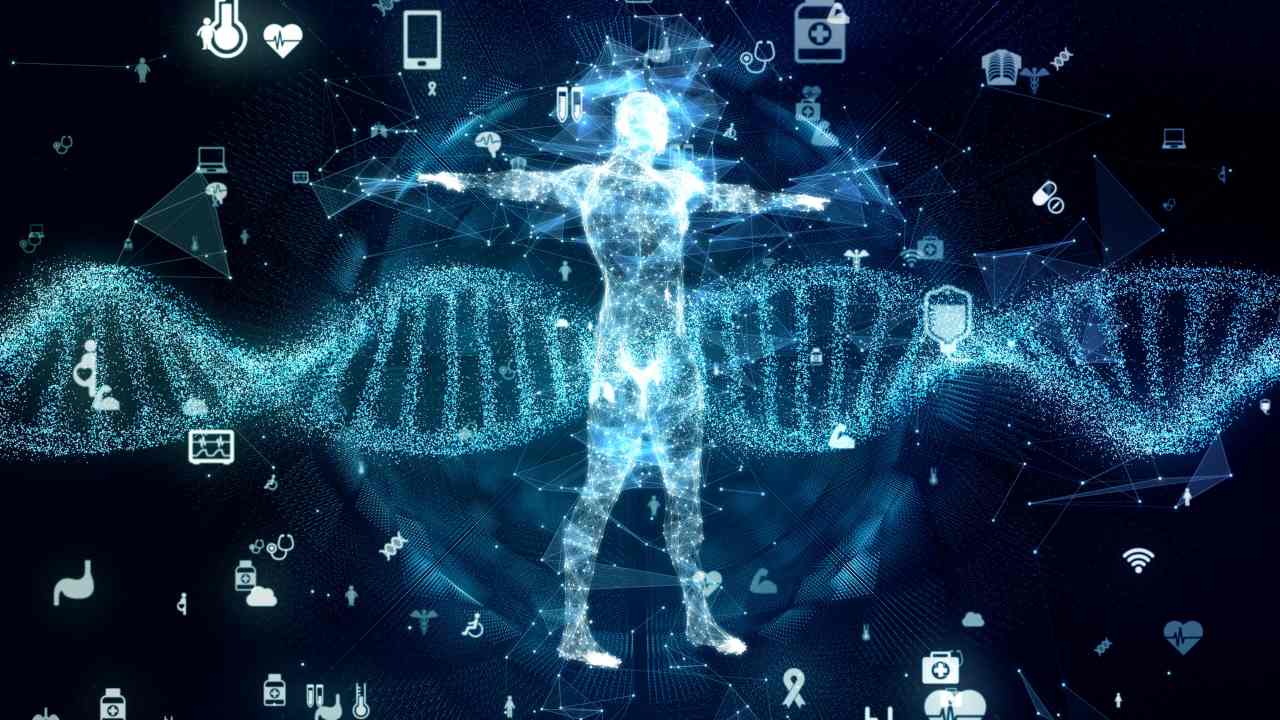学校教育はいまやその内容が複雑化して、生徒にとっては「学ぶこと」よりも「いい成績をとること」がその目的となってしまうきらいがあります。本記事では、日本における双生児法による研究の第一人者である安藤寿康氏の著書『教育は遺伝に勝てるか?』(朝日新聞出版)より一部抜粋し、そもそもなぜ「学校」という場所が必要になったのか、その経緯を通して学校教育の本質に迫ります。
進化的に見た教育
現代社会では、狩猟採集社会の子どもでもない限り、必ず国の定めた学校で、子ども時代のかなり長い時間を過ごさねばなりません。それは親が果たすべき国民の義務となっているからです。ここで学校とは何かという問題について、歴史的、理論的に、やや小難しく考えてみたいと思います。
そもそも学校らしきもの、つまり多くの子どもを一つの場所に集めて、家で親がしつけや子育てをするのとは異なる特別なことをまとまって教えようとし始めたのは、産業革命を迎えた18世紀のヨーロッパにおいてと考えられています。いわゆる「近代」になってからですね。
それまでのほとんどの子どもは、親の身分や仕事を継ぐまでは、「子どもらしく」遊んだり、ときどきは親のそばで仕事のまねごとをしながら手伝いをして、少しずつ社会のことや人間関係のルールなどを学んでいました。
ところが近代になると、西洋でも日本でも大都市に人が集中するようになり、仕事も分化し専門化して、多くの子どもがある程度、組織的に知識を身につけねばならなくなりました。読み書きそろばんのような基礎知識や、階層ごとの文化的教養です。
子どもの数も増え、親は仕事で忙しくなり、子育てを外注しなければならなくなりました。そうしてできたのが、幼児教育の祖と言われるフレーベルやペスタロッチの学校、あるいは日本では寺子屋のようなところだったわけです。
学校はただ親の子育ての肩代わりをしてくれるだけのところではありませんでした。そこでは親が教えてあげられないようなことを教え身につけさせてくれたり、家庭だけでは経験させてもらえないようなことをさせてもらえたりしました。知恵と知識がつまった童話や絵本、昔の人のことばを集めたもの、この世界にあるすばらしいものに触れる機会が、組織的に与えられるようになったのです。
「学ぶ」対象の変化
狩猟採集社会でも、学ばなければならない生きるために必要な知識はたくさんあります。それは主として自分を取り巻く自然環境についての知識でした。それは、自然を相手に自らの経験で学んだり、年上の子どもや大人の仕事ぶりを見て学ぶ形で獲得されていました。
しかしそれが近代になってからは、学ぶべき対象が人間自身が生み出した文化的知識にとって代わられるようになったのです。それにともなって学校という特別な場をつくるようになりました。
それは生きるための知識が、生活の活動の中に埋め込まれたものというよりも、言葉やマニュアルで表現されるものになり、体系化されたものとして表現できるからです。逆に言えば、日常生活とはいったん切り離された、見様見真似では学びにくく、誰かから説明や指導をしてもらわないと習得の困難な知識によって、社会が出来上がってきてしまいました。
使いこなせれば便利だがどう使ったらいいかわかりにくい複雑な機械の仕組み、その機械を使いこなすための作業手順、それが生み出す生産物をお金に換える仕組み、それらが社会の中で動き回るときのさまざまなお作法……どれも狩猟採集社会や、地域に根差した農業牧畜の社会にはなかったものでした。
だから学校が必要になったのです。これは歴史的必然です。かくしていまの私たちも、子どものときから家を離れ、学校で過ごすことが求められるようになったというわけです。