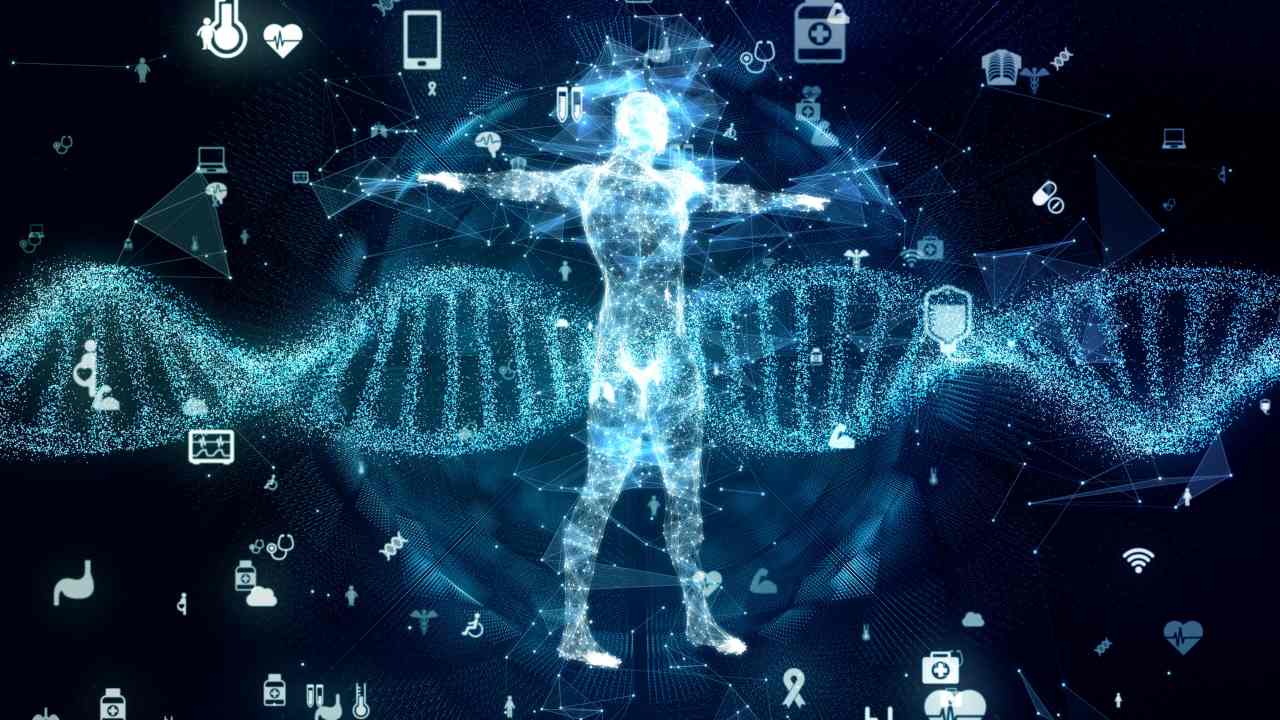知能に関して、「遺伝」の影響が強まっていくという事実は「結局はなるようにしかならないのだ」と悲観的に受け止めたくなることかもしれません。実際それは、本当に悲嘆すべき事実なのでしょうか? 本記事では、日本における双生児法による研究の第一人者である安藤寿康氏の著書『教育は遺伝に勝てるか?』(朝日新聞出版)から一部抜粋し、遺伝と経験が人生に及ぼす影響について解説します。

いわゆる「天才児」でなくても…20歳までに「遺伝的才能」は姿をあらわしている【慶應義塾大学名誉教授が解説】
歳を重ねると強くなる遺伝の影響
子どもが育つ環境は家庭だけではありません。特に子どもが大きくなるにつれて、活動の場は家庭を離れて、学校や学校外へと広がってゆきます。
このことは行動遺伝学でも、知能の個人差に及ぼす共有環境の影響が児童期から青年期、そして成人期に向かって徐々に減少してゆくことから見て取ることができます。その代わりに大きくなるのが遺伝の影響です。
なんだ、やっぱり遺伝によって決まっているのか、親の役割は小さくなっていってしまうんだ、と嘆くには及びません。これはとりもなおさず、子どもが徐々に一人前に自立していることを示唆しているのです。
遺伝的素質の発揮
よく誤解されるのですが、知能への遺伝と環境の影響の割合についてのこの結果だけを見て、親がどう育てても、結局は子どもはなるようにしかならないと悲観的に受け止めがちです。しかし、この結果は知能だけでなく、おそらく学習や訓練によって獲得されることすべてについていえると考えてよいと私は考えています。
つまり知能や学業成績以外の、たとえばおけいこごとで習うスイミングや野球やサッカー、ピアノやヴァイオリン、プログラミングやゲームの能力などもそうでしょう。さらには学校やおけいこごとではきちんと教えてもらえない知識、たとえばお金の流れや世の中の仕組み、人間関係の作り方など、その人のパーソナリティによる部分もありますが、経験と知識によって学んでゆく部分も大きいものです。
こういったことについても、はじめは親の姿を見て学んでいたとしても、だんだんと世界が広がるにつれて、自分の心で感じ、自分の頭で考えるようになると、それに従ってその子が両親の遺伝子を新たに組み直して出来上がったその子独自の遺伝的な素質を発揮する形で、能力を獲得しているのだと思われます。
それは感じたり考えたりする仕方に、その子自身の遺伝的素質が反映されているからです。そしてそれは小学校に上がるくらいから、もうすでにあらわれているのです。
天才児やギフティッド児がその才能を発揮するのは、すでにそのころです。世界的なピアノコンクールでの入賞経験をもつある有名なピアニストの方にインタビューしたときに、幼稚園のころから巨匠の弾くベートーヴェンのレコードを聴いて、自分だったらここはこうじゃなくて別の弾き方をする、そのときの指の動かし方はこうするというのが明確に頭に浮かんでいたというお話をうかがいました。
いや、天才児でもギフティッド児でもない凡庸な子どもがそんな立派な遺伝的素質を発揮して、ものごとを学ぶはずがないじゃないかと思うかもしれませんが、それは子どもを見くびっています。