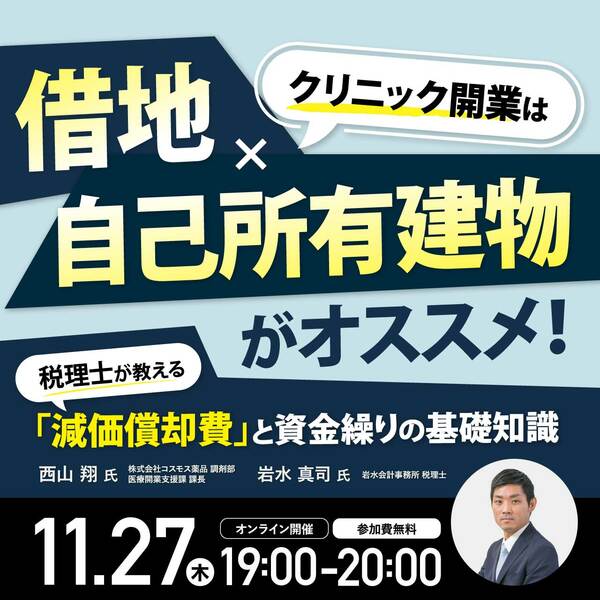「見積りは最低2社(できれば3社)から取り寄せる」ことをルール化
クリニックの開業にあたり、「建築価額の相場」「設計料の相場」「医療機器の相場」「薬品や検査料の相場」等々を事前に把握しているドクターは、まずいらっしゃらないと思います。つまり、業者から提示された見積書の金額が妥当かどうかの判断はできないということです。
相場が分からないのであれば、そもそもの見積金額を妥当な価格にしてもらうため、最低2社(できれば3社)から見積もりを取ることをルール化しましょう。
もし1社のみしか見積もりを取らなかった場合、価格競争の原理が働かず、相手の言いなりになってしまうリスクがあります。
同時に、見積りを依頼するときに「最低2社からは見積もりを取り寄せる」と、事前に業者へ明言しておけば、自然と競争原理が働き、無駄なコストを払わなくてすみます。
<参考1>業者の提案についての考え方・とらえ方
これから出会うすべての業者は、開業されるドクターに自分にできる(品質的にも価格的にも)ベストの提案をしてきます。業者側は自分の仕事分野でベストを尽くしているわけですから、それ自体は決して悪いことではありません。
しかし、その提案を簡単に受け入れてばかりでは、どうしても設備投資額が過大となってしまい、開業後の資金繰りを圧迫していくことになります。そのため、十分な注意が必要です。
<参考2>医療機器の見積もりは保守料まで含めて検討を
たとえば、医療機器の見積もりを数社から取り寄せた場合、一見医療機器の価格が安く表示されていても、月々の保守料まで含めると他社よりも割高になっている、というケースはよく見受けられます。医療機器の価格だけでなく、3年間(または5年間)の保守料も含めた総額で比較するようにしましょう。
<参考3>「いますぐ必要ではない医療機器」は買い控えを
「本当に患者様が来てくれるだろうか?」という不安から、ついつい、すぐには必要でない高額な医療機器まで買ってしまい、設備投資額が過大になってしまった…という失敗もよく聞きます。
まずは「絶対に必要な医療機器」のみを揃えて、その後、患者様の増加具合やニーズを見ながら、余剰資金ができたときに追加の医療機器を購入する、という姿勢も必要だといえます。
設計士の過剰な提案に注意を
設計士との契約が「建物価格の〇%」となっている場合は、建築価額が高額になるほど設計料も上がっていく構図になります。「できるだけ予算をかけ、よい建物を造りたい」という設計士と「できるだけ建築コストを下げたい」というドクターとの間で「利益相反」の関係になってしまうのです。
設計士は「あの建物は私が設計しました」と胸を張れる実績を残したいと思う人が多く、当初の予算をオーバーしても、可能な限り立派な建物を造りたがる傾向にあるように思います。
あくまでも私見ですが、これまでの経験上、設計料は(建築価額がいくらであろうと)〇〇万円という定額制で契約したほうが、建物全体のコストが上振れしにくいように感じています。
医師国保加入の検討
医師会に加入することを決めているドクターは、医師国保(国民健康保険の一種)に加入することが可能です。医師国保は都道府県によって微妙に条件が変わりますが、一般的には前の勤務先の健康保険を任意継続するよりも有利になることが多いです。
また、スタッフの健康保険についても協会けんぽに加入するよりも医師国保の方が有利になるケースが多いのでぜひ検討してみてください。
業者等への支払いを確認する
クリニックの運営においては、さまざまな業者への支払が恒常的に発生します。その場面ひとつひとつを取ってみても「まあいいか」で流してしまうと、チリも積もれば…となり、あとからかなりの出費となっているケースもあるため、要注意です。また、支払い方法に注意するだけでポイントが貯まるなど、お得になることもあります。面倒がらずに損しない方法・お得になる方法を探しましょう。
①クレジットカードの利用
現在は、医療機器や薬品類はクレジットカード決済できるケースが増えています。開業の際、仮に医療機器類を2,000万円クレカ決済した場合、1%の20万ポイントが付与されます。
また新しくクレジットカードを作る場合は、「半年以内に200万円利用したら追加で3万ポイント贈呈」などのボーナスポイントが付くケースも多くお得です。
とくに飛行機に乗ることが多いドクターの場合、ポイントを航空券に替えると通常は2倍以上の価値になりますので、契約の際に「クレカ払いはできますか?」と尋ねてみてください。
②銀行口座自動振替
薬品、医療消耗品、光熱費など、毎月定期的に支払いがある取引先との契約はクレカ決済がベストですが、それが無理な場合は最低でも自動振替にしてもらってください。
自動振替にすると振込料は通常相手持ちになりますので、仮に1回の振込料が500円で10件の取引先があるとすれば、月間5,000円(年間60,000円×開業~閉院までの年数)のコスト削減となります。
ここまでコストの削減方法について述べてきましたが、単純に「コストが下がった!」で終わるのではなく、下がったコストを集患のために使うことも重要だと考えています。
お伝えしたことが、これから開業なさるドクターの参考になれば幸いです。
鶴田 幸之
メディカルサポート税理士法人 代表税理士