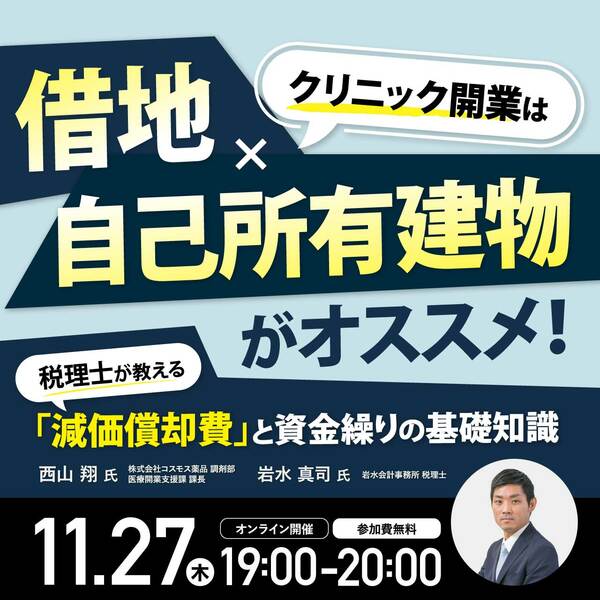スタッフのトラブル、最悪は「大量退職」「収益の問題」等の大問題に
クリニックは患者様を診療するサービス業ですが、一方で、クリニックにおける業務への取り組み方の方針は多種多様です。また、勤務するスタッフ個人の能力や考え方にもそれぞれ違いがあります。つまり、それぞれが持ち合わせている常識や価値観、能力に差異があることから、ときにはぶつかってしまう可能性もあるということです。
冒頭でも述べたように、スタッフ間の深刻な人間関係トラブルは、最悪は大量退職や経営のダメージといった一大事にもなりかねず、そのような事態に陥る前に、院長・事務長を始めとした管理職が早期に対応をするべきなのです。
とはいえ、クリニックでの人間関係には多様な課題があり、個別の課題に応じた柔軟な対応が必要になります。
クリニック内の人間関係が悪化する「根本原因」
そもそもの前提として、人間関係が悪化する主な要因には、
●勤務能力やコミュニケーションが不良であるスタッフへのストレス
●院長などによる贔屓
●職員間のハラスメント
●給与の明らかな差
●スタッフの派閥
といったことが挙げられます。
このなかで最も深刻な人間トラブルに発展しやすく、離職・退職の主な原因ともなるのが、「業務遂行能力」や「コミュニケーション能力」が低いスタッフの存在です。
ほぼ同じ賃金が支給されているにもかかわらず、業務能力が一定のラインを超えず、改善の余地もない、といった場合には、能力が優れている他スタッフの一斉退職といった事態を招く「大きな火種」となり得るのです。
管理者である院長は、自分の診療のほかに、常にスタッフの動向、業務内容を見守る必要があります。
注目すべき点は、医療本体に関わる業務のみならず、受付・会計・電話応対などの接客業務、会計や診療報酬・公費実施請求などの金銭的な業務など、あらゆる業務に及びます。
片づけや日計表の作成なども注目する必要があるため、診療終了後も注意が必要です。
見守りを続けるなかで、
「何度も同じミスを繰り返し、都度指摘されるが改善していない」
「注意されると反抗的な態度を取る」
「患者様やそのご家族に返金などを含めてご足労させる」
といった、クリニック運営に実害があるようなことが起きていないか、きちんと判断する必要があります。
仕事に取り組む姿勢の違いも、スタッフ離職につながる原因の1つとなります。
定められた就業規則を守らない、無断の遅刻早退・欠勤が多い、勤務中にスマートフォンを持って抜け出てしまう、といったスタッフがいれば、他の真面目に勤務しているスタッフに迷惑がかかるほか、勤務意欲に影響がでます。
ほかにも、各部門のマニュアル通りの指示・行動をせず自己流で実施する、他スタッフや院長などの管理者への「ほうれんそう」(報告・連絡・相談)ができない、といったことも、スタッフの能力を見極めるポイントとなります。
院長にとって盲点となりやすいのが、院長・事務長によるものではなく、各部門トップがおこなうハラスメントで、これもスタッフの離職の大きな原因となります。最悪の場合、突然の離職や、内容証明で損害賠償請求が送られてきて、最終的に民事訴訟に発展…ともなれば、100万円を超える和解金の他に、解決までも時間がかかり、管理者は多大なるストレスを抱えることになります。
チームワークを乱す「不良スタッフ」に、どう対応する?
前述のような問題のあるスタッフがいる場合、当然ですが、職場の雰囲気は悪くなります。コミュニケーションが活発で風通しのよい職場であれば、該当スタッフと同じ職種、その次には他職種からのクレームや提言があります。
実はこの早期の段階で、当該スタッフとの「個別面談」や「指導」を行う、というパフォーマンスが重要です。
その理由として、業務遂行能力や態度が不良なスタッフでも、現在の労働基準法の元では簡単に解雇をすることが不可能であるためです。
問題のあるスタッフになにも対応せず、勤務を継続させる管理者や雇用主は、最終的には他のスタッフから不信感を抱かれ、さらなる人間関係の悪化→モチベーションの低下→果てには集団退職へとつながりかねません。
こうした問題あるスタッフを見分ける方策としては、入職時の勤務条件契約書で定める「試用期間」を長く設定しておくことです。そうすれば、解雇へのアクションを行いやすくなります。経験論として試用期間は非常勤では3ヵ月、常勤では6ヵ月ほどがベターかと思います。
問題があるスタッフには、野球と同じで「スリーアウトチェンジ」制をおすすめします。まずは他スタッフからのクレーム・問題点を整理して、当該職員との個人面談で改善点を共有します。
そこから「1ヵ月」などの一定期間を設けて観察し、それでも改善が見られない場合、2回目の個人面談を行います。その際には院長のほか、各部門のリーダー1名を同席させて同様の指導を行い、この時点で3回目の指導になった場合には試用期間後の雇用を継続しないことを明言します。
ここまでの2回の面談で重要となるのが、面談実施の日時・場所・その内容を必ず客観的な記録と残しておくことです。
3回目の面談では、自主退職やこちらからの退職勧奨、それでも納得いかない様子を見せた場合のために解雇予定通告書を用意します。
解雇予定通告書には「〇月〇日、△月△日に指導を実施したが業務遂行能力・態度に改善が認められないこと」と記載し、続けて実際にクリニックが受けた経営的損害(例:レセプト誤請求11件による再審査5800点相当、公費ワクチンの請求漏れ3件3万2,000円相当…など)を明記します。
院長1人で退職勧奨をおこなうと、パワハラなどで逆手を取られる可能性があるので、事務長などを同席させる、内容を録音・録画する、といった最大限の防衛策を講じることが重要です。
業務遂行能力やコミュニケーション能力が欠如したスタッフの場合、経歴詐称や能力詐称が判明することも多く、こちらも退職勧奨理由として明言するとよいでしょう(とくに医療事務でパソコンスキル・レセプト請求などがポイントとなります)。
そのほかの対応
複数人の派閥による、ひとりの新規スタッフなどに対しての執拗ないじめや陰口も、精神的ストレスとなり離職の原因となります。
このような事態を放置した場合は、スタッフの定着率が悪くなるほか、院内全体で良好な人間関係を築くことができず、いつまでも深刻な人間関係の問題や人手不足に悩まされることになります。
また、業務量や給料に明らかな差がある場合も不満を抱きやすく、贔屓されているスタッフへ負の感情が集中してしまうこともあります。
雇用形態や経験年数、当人のスキルなどで、多少の給与や業務量に差が生じることはありますが、不公平さを感じる、やりがいが感じられない、といった職場を作り出さない配慮も、院長には必要です。
チームプレーでこそクリニック運営は成り立ちますので、一定の患者数に達した、1カ月の収益が目標値を超えた、といったことに対してインセンティブを用意することによって、全スタッフへの公平感を演出する、というのも作戦のひとつです。
また、医師・事務長などの管理職スタッフへの対応の違いも、人間関係の悪化につながることがあります。同じミスをしても厳しく叱責される人と、ほとんど注意されない人がいると、不公平感に繋がりやすく、要注意です。
また、院長がほぼワンマン経営で、スタッフの勤務状況などへの配慮がなく、業務を無理強いした場合、院長vs.スタッフ、といった構造ができあがり、院長を敵対視した人間関係となってしまうと、運営の円滑性は著しく低下します。
こうした状況を回避するため、1日1回はスタッフとのコミュニケーションをとる、業務量や能力を平等な視点で、プラスの方向で評価することが重要となります。
ひとりのスタッフに業務が集中していないか、能力に応じた評価や目標設定ができているか、といった振り返りをおこなうことが大切なのです。
これに加えて、ミーティングや個別面談によるスタッフの教育も、深刻な人間関係悪化によるクリニック運営破綻の回避には重要です。
スタッフが自他の業務内容をキチンと把握し、円滑にコミュニケーションをとれることが、クリニック運営の要となります。
人間関係が悪くギスギスした雰囲気は、患者さんにも伝わります。クリニックの評判低下にも繋がりかねず、ひいては経営にも悪影響が生じてきます。
クリニックの人間関係を良好に保つしくみを積極的に取り入れ、管理業務でもスタッフが働きやすい環境づくりを意識することをおすすめします。
武井 智昭
株式会社TTコンサルティング 医師