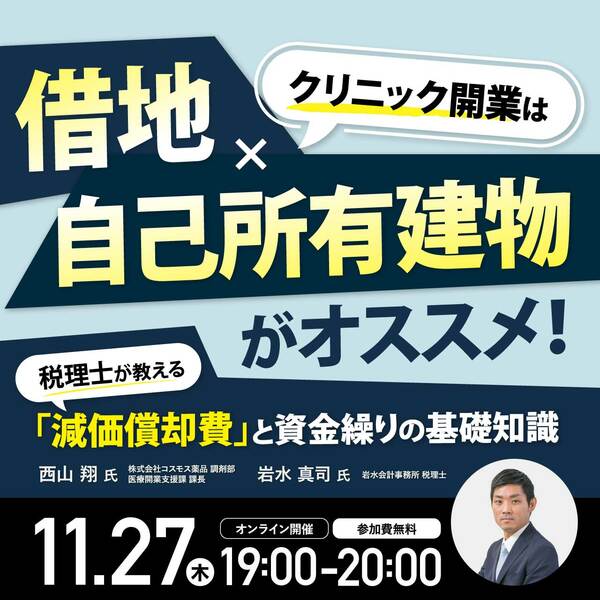現在成功している診療科目だからといって、未来も安泰とは…
クリニックの開業を目指すにあたり、医師はいろいろなことに考えを巡らせます。
これから成功する可能性の高い診療科目、逆に厳しい診療科目はどれか? 将来的なニーズや社会需要はどうなっていくのか? これまでの自分のキャリアとは無縁な科の場合はどうなのか? クリニック経営はどのように軌道に乗せればいいのか?
診療科別の平均収益や年収などは信憑性のあるデータがある一方で、今後の展望についてはハッキリしないことも多く、頭を抱えている医師も多いでしょう。
今後の診療報酬改定や医療政策により、現在は儲かるとされる診療科が、明日には見通しが厳しい診療科になることもありえます。ここでは、今後のニーズが高い診療科と、ニーズが低下し、独自の戦略が必要となってくる診療科について述べていきます。
今後のニーズが高い診療科①…総合診療科
第一に注目すべき診療科目は、小児を含めた全世代を対象とした、よくある疾患を対応する「総合診療科」としての開業です。
昨今の医療政策や患者ニーズとして、気軽に相談を行うことができる「家族の主治医機能」「かかりつけ医としての役割」が地域のクリニックには求められています。
患者としては、医療が細分化・専門化しているからこそ、身体のみならず家庭環境・心理面など全人的な医療を展開し、必要があれば専門の病院へと繋げてくれる医師が身近にいれば安心です。だからこそ、地域住民に支持を得られれば、安定した収益を得られると考えられます。
地域住民への支持を得るべく、総合診療科には訪問診療のスキームを含むこともあります。
厚生労働省が推奨する「国策」でもある「真のプライマリケア医」の存在は今後のニーズも高くなることでしょう。
今後のニーズが高い診療科②…精神神経科
今後の高需要が見込める診療科の2つ目は「精神神経科」です。
過酷なストレス社会を生き延びるにあたり、さまざまな要求・ニーズに応えようと無理を重ねた結果、心理的に追い詰められてうつ病などの「気分障害」に…。近年では、このような状況に置かれる人が増加しています。
また、社会の高齢化に伴って認知症患者が増加することで、精神症状である「周辺症状」の対応が求められますが、同時に、高齢者のケアでストレス負荷が高まっている家族などにも需要があります。
さらに近年では、児童精神科領域や発達障害の診療ニーズも高まり、幅広い年代層から「精神神経科」が必要とされてくることが予測されます。
今後のニーズが高い診療科③…整形外科・リハビリテーション科
ほかにも、人生100年時代をまもなく迎える現代では、サルコペニアやロコモティブシンドロームなどの筋骨格機能維持のためのニーズも高まっています。
外傷の初期対応や脳卒中後などの管理を含めて「整形外科」「リハビリテーション科」の重要性・ニーズは飛躍的に上昇しています。とくにリハビリテーションは、現在では需要に追い付いていない状況です。これらの診療科は継続的・長期的なフォローを必要とするため、今後も注目される診療科であります。
今後は戦略が必要になる診療科①…小児科 今後は需要が減り、独自性の戦略を要するようになる診療科もあります。
少子高齢化の昨今、需要減の筆頭候補が「小児科」です。厚生労働省による統計「医療施設(静態・動態)調査」によると、小児科を標榜する医療施設数は2014年には2,702件、2017年には2,592件ありましたが、10年後となる2022年には2,485件まで減少するなど、厳しい状況に置かれています。
ここまで小児科が減少してしまった原因としては、少子化によって採算がとれない医療機関が増加したこと、長年地域を支えてきた小児科クリニック院長の高齢化など挙げられます。
その一方で、都心部では駅前を中心に小児科が激増しているのも事実です。
これに加えて、この10~15年で疾病構造に劇的な変化がみられたことも、小児科の苦戦の原因に挙げられます。
かつて「ワクチン後進国」と揶揄されていた日本では、子どもは頻繁に発熱をして入院管理を要することも多くありました。しかし2010年に髄膜炎関連ワクチン(ヒブ・肺炎球菌)の定期接種化と接種率が増加したことや、喘息などのアレルギー疾患の予防の啓発と普及により、最近の子どもは重篤な肺炎・脱水・喘息発作による入院を要するケースが圧倒的に減ったのです。
今後の小児科には、3歳未満のワクチン・健診のほか、傷病の頻度が多いボリュームゾーンの効率的な獲得、夜間や休日などの突発的な対応が可能な診療時間の組み方、家族の診療も行うなど、従来の小児科のイメージとは異なる運営が求められることになるでしょう。
この一方で、近年クローズアップされた「発達障害」「不登校」などの疾患に対して時間をかけて懇切丁寧に対応を行う「児童精神科」に関しては相当なニーズがあります。
児童精神科の初診予約は3ヵ月後以降というレベルであり、参入障壁は高く、担い手がかなり少ないジャンルのため、狙い目ではあります。2024年の診療報酬改定で、「小児慢性特定疾患カウンセリング料」の単価増加や算定期間(2年から4年に延長)というエビデンスもあります。
今後は戦略が必要になる診療科②…皮膚科
次に厳しい診療科としては「皮膚科」があげられます。一部のメディアは「皮膚科の開業は、美容を併用すればラクに高収入が得られる」というキラキラしたイメージで報道していますが、現実はこれとは正反対の厳しい状況下に置かれています。
皮膚科医は増加傾向にあり、医師会データによると、この10年で15%増と顕著です。それにともない、開業競争も激化しています。
同じ地域での患者の獲得競争が激しく、目立つために美容機器を導入するとなると、レーザー治療器など1,000万円単位の高額な設備投資が必要です。
運営においては、技量や接遇はもちろんのこと、待ち時間の短縮化・馴染みやすい雰囲気の構築など、求められるサービスのレベルも高くなっています。
また、保険診療のみでは単価が3,000円台と低いため、回転を良くするスキームも求められます。
自費で美容皮膚科を併用する場合、ハイソサエティな顧客獲得のための内装への投資も必須となってきました。
ここまで診療科のニーズや今後の見通しについて解説してきましたが、必要とされる診療科は時の流れによって、また変化していくことが予想されます。
目先の収入よりも、自分自身の「地域社会で貢献したい」という医師としての原点と、やり抜く強い決心が、開業への必要条件になってきます。
武井 智昭
株式会社TTコンサルティング 医師