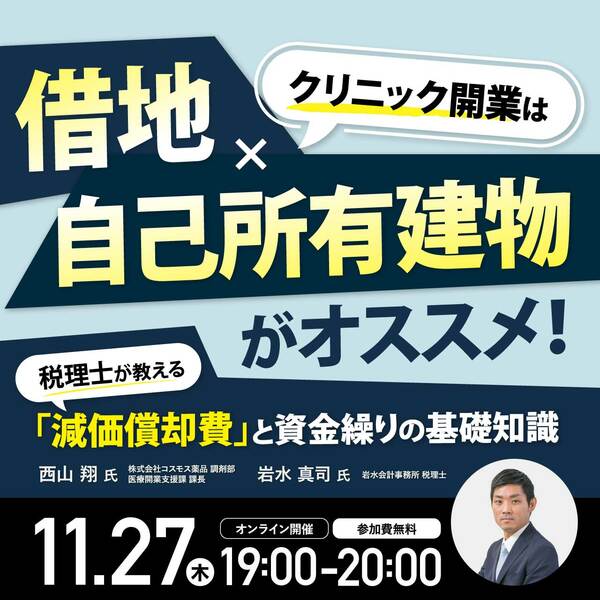配置人数と給与の問題
看護師定着のためにまず把握しておくべきなのは、クリニックにおけるスタッフの適正人件費です。
一般的には、内科等のよくある町のクリニックでは、1日あたりの来院患者の適正人数の目安は「1日最大受診患者数の70~80%」となります。
20~25名について1名のスタッフ配置が適正とされておりますので、1日あたり100名の来院が見込まれるクリニックでは、看護師・医療事務ともに4~5名程度が適正となります。
これ以上であれば、有給休暇は取りやすいものの人件費が増加し、これ以下であれば労働負荷が高くなるほか、有給休暇取得が困難となり、離職につながります。
人件費の算出としては、年間のクリニックの収入額からの逆算する方法もあります。
適正なスタッフの人件費は収入の15~20%(利益率として10~15%を維持)が目安となります。年間の収入が1億円とした場合、スタッフ人件費は2,000万円程度が適正の目安となります。この人件費では正社員の雇用は4~5人、残りをクリニックの繁忙時間にあわせたパート職員を増員する事がポイントとなります。
昨今では、医療業界においても「働き方改革推進」があり、スタッフのほとんどは女性であるため、出産・育児・介護などのさまざまなステージがあり、急な休みなども生じることがあります。
このため、雇い主側には、勤務時間帯や休暇取得に対して柔軟であることが求められ、前述の適性人数に+0.5~1.0名などと余裕を持たせたほうがよいでしょう。「残業続きであるが給与が高水準である」という一昔前の工夫よりも、「人数を多めにして、体調不良や家庭の事情、リフレッシュなど休みやすい体制を整える」という現代にマッチした工夫が優先されます。
人間関係の問題
前述の「残業続きで体力がつらい」「人手不足で有休をとれない」「給与や賞与が周辺相場と比べて低い」という待遇面に続いて、女性で多い退職理由として「人間関係がつらい」というヒューマンリソースならではの理由があります。
人間関係に亀裂が入る背景には、待遇の差・業務量の偏りにより「自分ばかりが負担が強く、働き損」「あの人だけ、院長・事務長などにひいきにされている」が比較的あります。また、著しくコミュニケーションが低い、業務遂行能力が低い人のカバーに疲れたなどという、比較することによる不満が多い傾向にあります。
特定のスタッフによる士気低下がある場合には、この該当スタッフへ何回か指導を行っていき、改善されない場合には解雇を考える必要もあります。この労力は大変ですが、院長は全体を俯瞰する必要があり、他の優秀なスタッフがしっかりと長く働くという方向を持って心機一転、新たな雇用を行うことも必要です。
院内の人間関係が円滑でないと受診する受診する患者様・ご家族への心証への心証も低下して、クリニックの評判にも直結します。このような状況が続き規模拡大による統制がとれない場合、職員間のパワハラによる労務・法的な対処などに発展することがあります。
不平・不満が出た、火事でいえば「ボヤ」の時点で改善をすれば、一斉退職などクリニックの運営すら危うくなる大惨事にはならないでしょう。この時点が、適切な対応を取るタイミングでもあります。
キャリアアップ(内的モチベーションの向上)の問題
クリニックも経営が落ち着くと、病院とは異なり、日常業務は同じルーチンを繰り返す傾向があり、業務がマンネリ化してしまうこともあります。
やる気を持って業務に取り組むには、責任のある仕事を任せる、学会や研究会の参加や発表の支援(費用はクリニック負担)等を行うなどして、「ここで働けば〇〇について学べる」「成長できる」と思える職場の雰囲気作りが重要です。
そのようなモチベーション維持のためには、トップである院長が現状に甘んじることなく、向上心を持ってさまざまなことにチャレンジする、もしくは職員の意見を聞いて業者を呼び、勉強会を開催するなど、行動を見せることが重要です。
厳しい医療現場、スタッフに寄り添った対応・待遇が不可欠に
医療の現場は、体調不良等の疾病を取り扱うところであり、スタッフは気が抜けません。そのような厳しい現場では、スタッフ自身が幸せであり、満足していなければ、他人の健康を支えることは困難です。そのためにも、スタッフのプライベートと仕事の両立が大切なのです。
それぞれのスタッフが、クリニック内での自身の役割を認識するとともに、スタッフ同士で成功体験を分かちあい「私はこのクリニックに欠かせない存在である」「クリニックのために、自分ができることをやっていこう」といったポジティブな気持ちを持つことが重要です。この内的なモチベーション向上の連鎖により、スタッフの定着率は上がっていきます。
同時に、スタッフの休憩のアメニティの充実化(お菓子・お茶、広いスペースなどの環境)、リフレッシュ休暇や福利厚生、スタッフのライフステージに合わせた勤務環境の調整や家庭への配慮、インセンティブ支給などの外的な要因も大きな要素となります。
まずはクリニックのトップとなる院長や事務長が率先してこれらの行動規範を示し、そして職員の手柄をしっかりとたたえましょう。そして、無駄働きにならない、労働に見合った対価(給与、人事、福利厚生の見直し)を充実させましょう。このような意識こそが、スタッフの「このクリニックで長く頑張っていこう」といった前向きな意識を醸成し、離職率の低下へとつながっていくのです。
武井 智昭
株式会社TTコンサルティング 医師