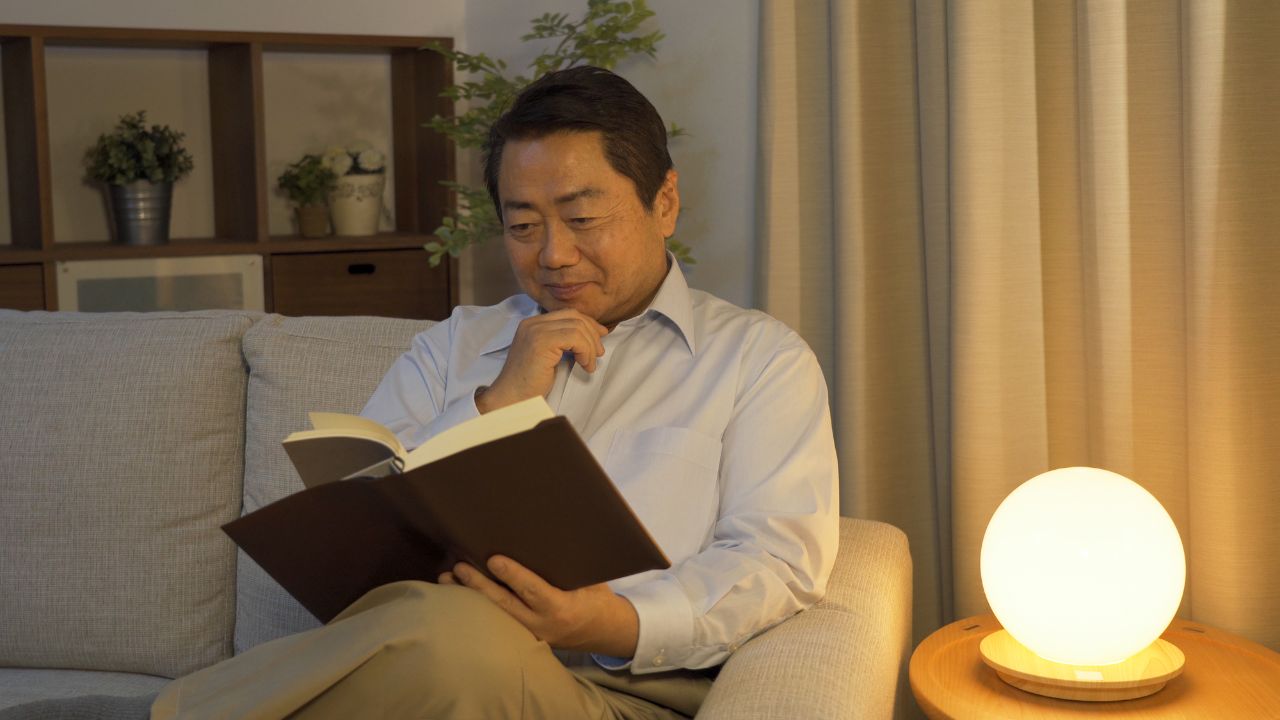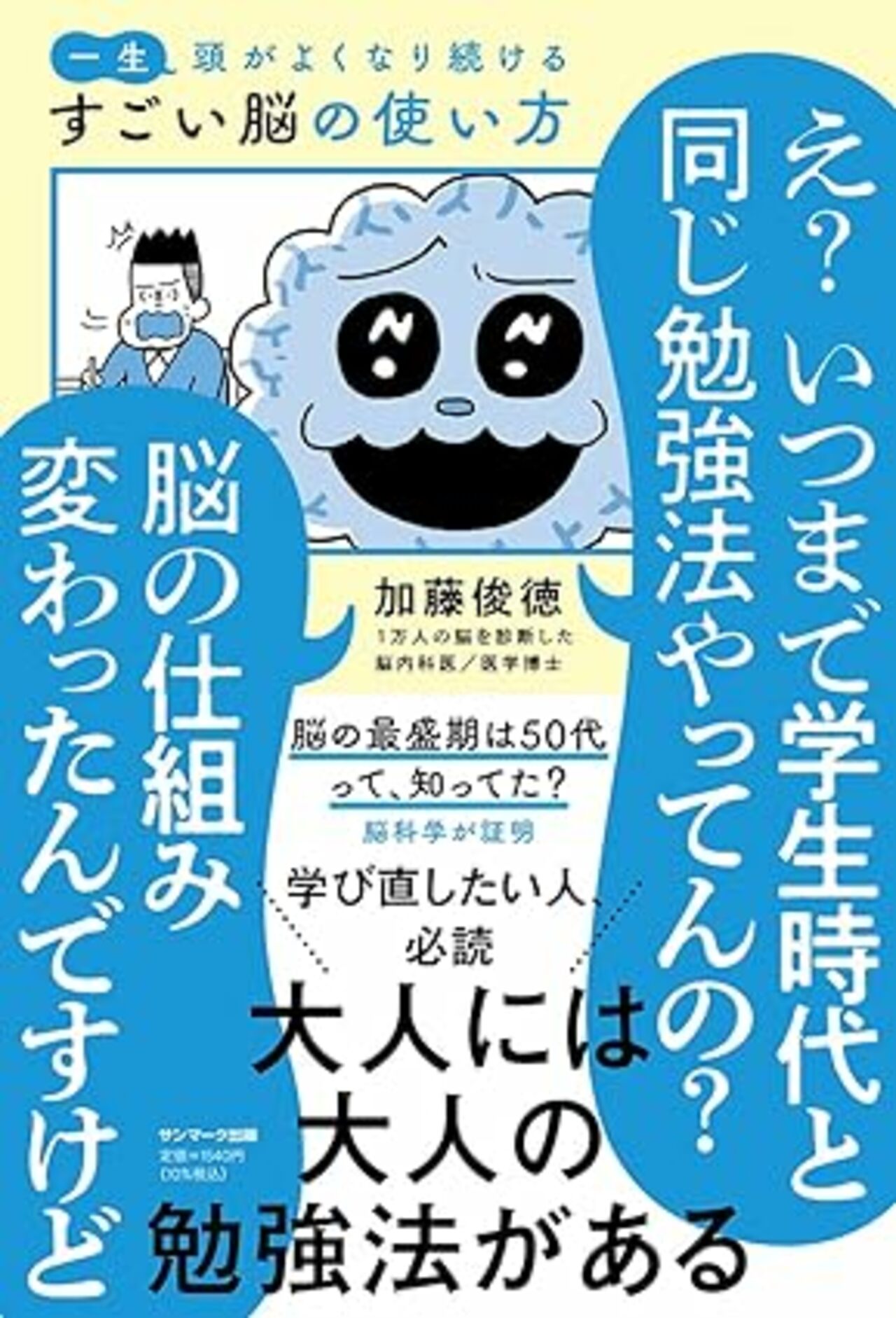「勉強したはずなのに、思い出せない」試験本番で誰もが一度はそんな思いをしたことがあるのではないでしょうか。脳内科医の加藤俊徳氏によると、記憶力で覚える力以上に大事なのは「使いたいときにいつでも覚えたことを引き出せる能力」とのこと。著書『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』(サンマーク出版)より、 加藤氏が解説します。

覚えたはずなのに思い出せない…!「記憶力を高めるため」に大事なこと【脳内科医が解説】
「誰かに伝える」を意識すると脳がよく働く理由
ワシントン大学のジョン・ネストイコ博士らによるこんな実験結果があります。
56人の大学生を「後で別の人に教える」「後でテストをする」「特に何も指示しない」という3つのグループに分け、戦争映画に関する文章を読んでもらいます。その後、少し時間を置いてから、学んだ内容の自由記述および短答式のテストを実施したとろ、「後で別の人に教える」ことを前提としたグループの成績がもっともよいという結果が出ました。
この実験結果からも、アウトプットをするという前提があるだけで、脳の働きがよくなることがわかります。
「これから習うものを、明日発表しなければならない」と最初から自分に意識付けすることで、とたんに脳番地たちに緊張感が生まれ、動いて情報を集め(運動系)、見聞きしたこと(視覚系と聴覚系)を理解し(理解系)、考え(思考系)、記憶して(記憶系)誰かに伝える(伝達系)、というように脳番地は一気に働き出すというわけです。
そもそも脳は情報をインプットするときだけでなく、アウトプットのために取り込んだ情報を思い起こそうとしたときのほうがより強く記憶される「出力強化性」が備わっているため、記憶力の向上にもアウトプットは欠かせません。
脳全体の機能を維持・向上し、生涯働いてくれる元気な脳を育てていくには、年齢とともにアウトプットの比率を高めていく必要があります。
SNSで発信したり、ノートにまとめて音読したり、インプットをアウトプットにつなげるチャンスは、日常の中にゴロゴロ転がっています。「自分ならどう考えるか」という視点で自分に問いかけることを癖にするとアウトプットの能力が磨かれます。
勉強するときも同様です。
テキストを読みながら、これを全く知識のない第三者に伝えるとしたら、どんな言葉でどう伝えるのがベストか。要点を3つにまとめて書き出すとしたらどう分類するのがいいか。そんなふうに、アウトプットを意識して文字を追うようにするだけで、さまざまな脳番地の連携がよくなり、脳が活性化していきます。
脳科学的にいちばんおすすめするのは、アウトプットを意識しながらインプットをし、そこで考えたことをノートなどに書き出して、誰かに説明するように話すというアウトプットのミルフィーユ状態を作り出すことです。
アウトプットを繰り返すほど、脳はよく働いて記憶力も高まるので、意識的にやってみてください。
加藤 俊徳
加藤プラチナクリニック院長/株式会社脳の学校代表
脳内科医/医学博士