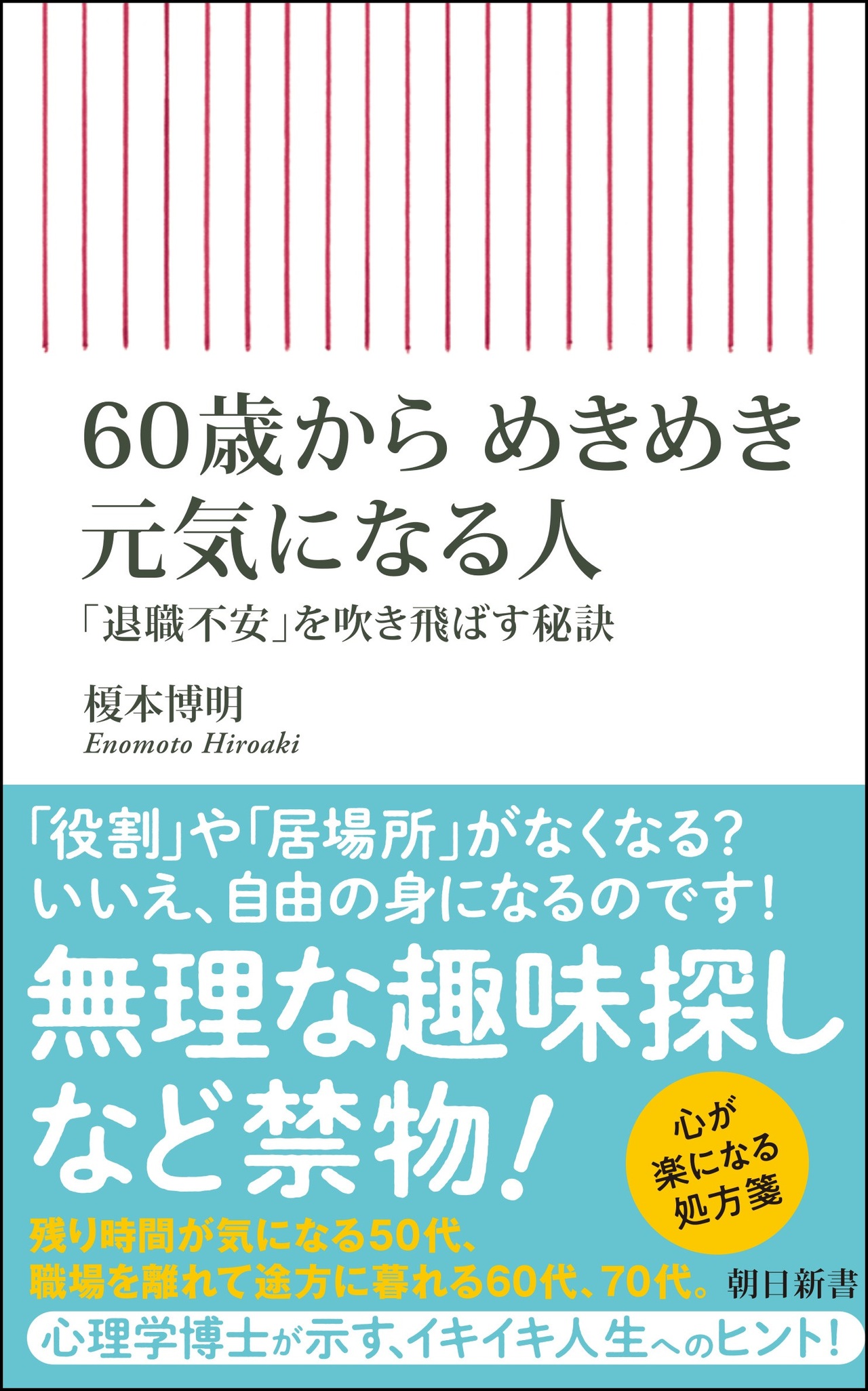定年退職後の孤立が社会問題としてたびたび取りざたされますが、人と関わっていればOKというわけではありません。そこで本稿では、MP人間科学研究所で代表を務める心理学博士の榎本博明氏による著書『60歳からめきめき元気になる人「退職不安」を吹き飛ばす秘訣』(朝日新聞出版)から一部抜粋して、「自己開示性の大切さ」について解説します。

定年退職後の〈孤立〉だけが問題ではない…人と会話しても「なぜか虚しい」と感じるあなたに知ってほしいこと【心理学博士の助言】
自己開示できる相手をもつことの大切さ
定年退職後の社会的孤立ばかりが問題にされ、社会活動への参加がしきりに奨励されるが、人とかかわれば、それでいいというわけでもない。
どうでもいいような社交話によって気が紛れることはあっても、ほんとうに気になっていることを話せる相手、ときに深い話もできる相手がいないとストレスは溜まるばかりである。
心理学者のジュラードは、「自己開示」は心の健康にとって非常に重要であり、自己開示できる相手が少なくともひとりいることが精神的健康に至るための条件であるという。
自己開示というのは、自分自身の経験や自分が思っていることを率直に伝えることを指す。心を閉ざしている人は、人に対して自己開示などしないだろうから、自己開示は心の開放性の指標とも言えるわけだが、自分は社交的だし、開放的な人間だと思っている人が、必ずしも自己開示をしているわけではない。
心理学の世界では、人に対する開放性をあらわす指標として、従来は社交性(社会的外向性)が用いられていたが、私はそれに自己開示性も加え、2つの次元で対人的開放性をとらえることを提唱してきた。
社交性というのは、人と接するのが好きな心理傾向のことである。心理学者のチークとバスは、社交性を他者と一緒にいることを好む性質としたうえで、社交性を測定する心理尺度を作成しているが、日本語に訳すとつぎのようになる。これらの項目が当てはまるほど社交性が高いことになる。
①人と一緒にいるのが好きだ
②人づきあいの場には喜んで出かけていきたい
③一人で仕事するよりも、人と一緒に仕事する方が好きだ
④人とつきあうのは何にも増して刺激的なことだ
⑤いろいろな人づきあいの場をもつことができないとしたら、それは不幸なことだ
社交性の高い人は、だれとでも適当に楽しく雑談することができ、初対面の相手やよく知らない相手を前にしても緊張せず、慣れ親しんだ相手を前にしたときと同じようにごく自然に振る舞うことができる。
社交性の低い人は、人と話す際に何を話したらよいかの判断が即座にできないため、初対面の相手やよく知らない相手を前にすると緊張し、慣れ親しんだ相手を前にしているときとはまるで別人のようにぎこちなくなる。
チークとバスの尺度項目にはないが、初対面の相手やよく知らない相手にも気後れせずにすぐに馴染めるかどうかも、社交性の指標と言ってよいだろう。