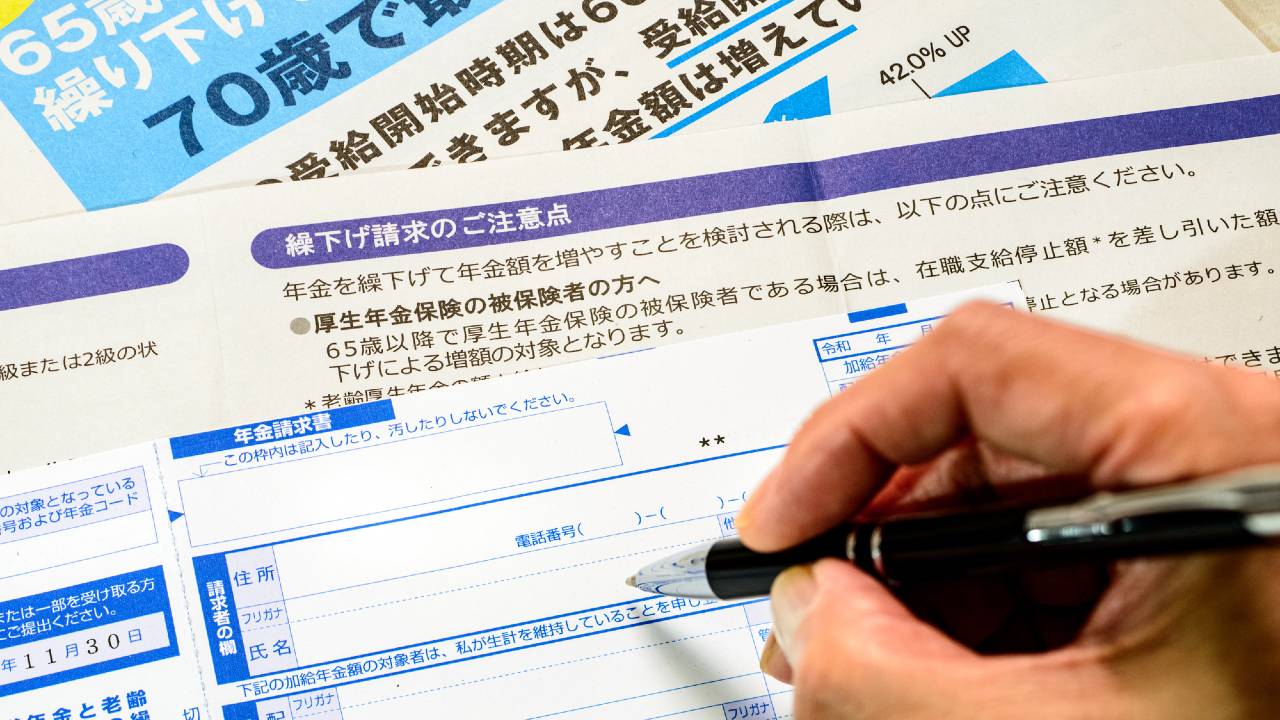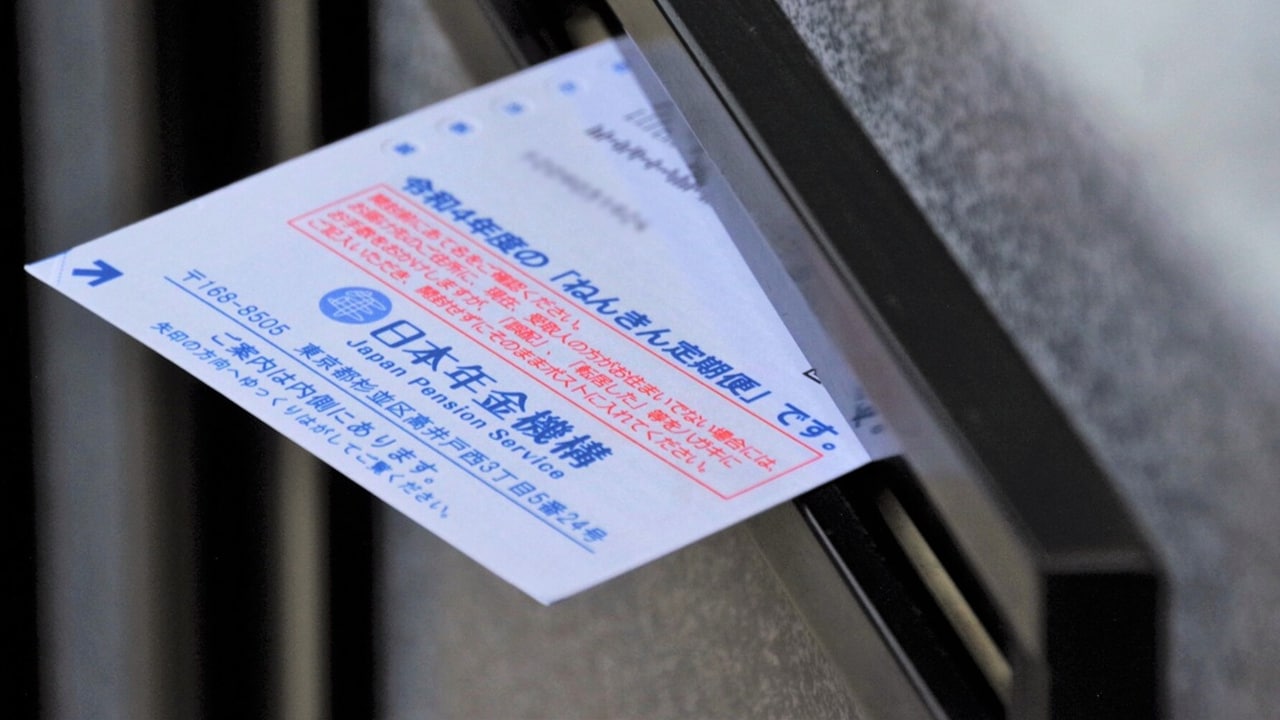公的年金には、原則65歳以降に支給される「老齢年金」のほか、配偶者が亡くなった場合に遺族が受け取ることのできる「遺族年金」があります。しかし、この遺族年金について、致命的な“勘違い”をしている人が少なくないようです。夫を亡くした68歳女性の事例をもとに、遺族年金の仕組みと注意点についてみていきましょう。FP Office株式会社の岩倉由記子氏が解説します。

あれ、記帳ミスかしら…年金月7万円の68歳女性、愛する夫からの“最後のプレゼント”に困惑。通帳を思わず二度見したワケ【FPの助言】
遺族年金の仕組みと支給額の“現実”
遺族年金は先に旅立った配偶者からの“最後のプレゼント”です。しかし、そのプレゼントに満足している人はあまり多くないでしょう。
2024年の厚生労働省「年金制度基礎統計」によると、遺族厚生年金の平均支給額は月約8万円~10万円。この金額で悠々自適な暮らしを送ることは、決して簡単ではありません。
「遺族年金」とは、老後の生活を支える「老齢年金」とは異なり、被保険者が亡くなった際に遺族が受け取る年金のことをいいます。
具体的には、以下の2種類があります。
・遺族基礎年金:主に18歳未満の子どもを養育している遺族に支給。高齢の配偶者は対象外。
・遺族厚生年金:厚生年金の加入者が亡くなった場合、一定の条件を満たす配偶者に支給。
たとえば夫が亡くなった場合、残された妻に支給される遺族年金額は、原則として夫の老齢厚生年金の3/4相当額となり、全額ではない点に注意が必要です。なお、このとき基礎年金部分や加給年金は引き継がれません。
また、夫婦ともに高齢であった場合、加給年金がそもそも終了していたり、被保険者期間が短かったりしたために金額が伸びないケースもあります。
さらには、年の差婚夫婦や妻の年齢が65歳以上の場合、自身の老齢年金との調整も発生します。このため、「思ったより少ない……」と感じる人が多いのが実情です。
あれ、記帳ミスかしら…通帳を見て絶望したA子さん
専業主婦のA子さん(仮名・68歳)は、同い年で会社員の夫を持ち、長年家庭を切り盛りしてきました。やがて定年を迎え、夫婦は月25万円の年金を2人でやりくりしていました。たまの旅行も楽しみながら穏やかな老後を満喫していたそうです。
しかしある日、突然の悲劇が訪れます。
長年連れ添った夫が病に伏し、急逝してしまったのです。残されたA子さんは、今後の生活について頭を抱えてしまいました。
A子さんは夫の預貯金1,500万円を相続したほか、月約8万円の遺族厚生年金とA子さん自身の老齢基礎年金(月約6.5万円)をあわせて月15万円前後の年金収入があります。
A子さんははじめて遺族年金が振り込まれたその日、自身の通帳を思わず二度見してしまいました。
「あれ? 記帳ミスかしら……」