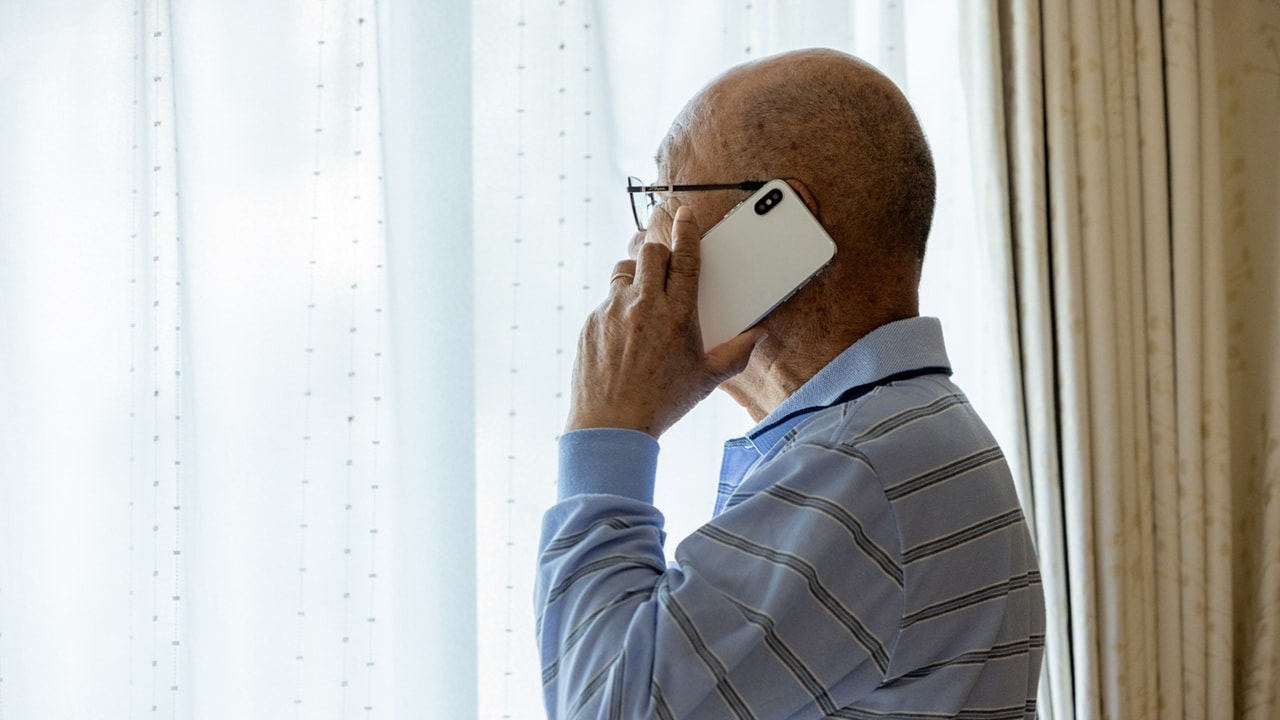103万円、130万円、96万円……日本にはさまざまな「年収の壁」があることをご存じでしょうか。これらの壁を超えると税負担が増えると理解はしていたものの、あまり深刻に考えていなかった孝太郎さん(仮名・55歳)。しかし、その“油断”が「思わぬ事態」を引き起こしたのでした……。神戸・辻本FP合同会社代表の辻本剛士氏が、事例をもとに「扶養控除」の仕組みとその影響を解説します。

ねえ、言ったよね?…年収750万円の55歳サラリーマン、大学生息子からの“助言”を無視して〈まさかの税負担〉→息子からの“激詰め”にしょんぼり「本当に情けない」【CFPが解説】
正しく理解しておきたい「103万円の壁」の落とし穴
「扶養控除」とは所得控除のひとつで、納税者の税負担を軽減する仕組みです。所得税や住民税を計算する際に、各納税者の状況を考慮して一定額を所得から差し引くことで税額を抑えられます。
扶養控除が適用されると税負担が抑えられる一方、扶養控除がなくなると税負担が増額する可能性があるのです。
年収が高いほど税率が上がるため、扶養控除がなくなった際の影響も大きくなります。年収によっては年間で20万円以上の税負担増となるケースも少なくありません。
扶養控除の金額は扶養親族の年齢によって以下のように異なります。
19歳以上23歳未満が該当する「特定扶養親族」の控除額が最も大きく、63万円となっています。このため、大学生の子どもがいる家庭では、扶養控除の喪失による影響が特に大きくなりやすいといえます。
税負担を抑えるためには、特別な事情がない限り、学生の年収を103万円以内(2025年度以降は123万円)に抑えるのが得策です。これを超えると、親の所得税・住民税が増加するだけでなく、学生本人にも住民税や所得税の負担が発生する可能性があります。
孝太郎さん夫婦の家計を改善させる「2つ」の対策
扶養控除が外れたことで税負担が増えた幸太郎さん。現時点で可能な対策は下記の2つでしょう。
1.息子のアルバイト収入を調整
税負担を抑えるには、先述のとおり颯太さんの収入を103万円(または123万円)以下に抑え、扶養内にとどめることが必要です。
しかし、これだけでは颯太さんの収入が減ってしまうため、仕送りを1万円ほど増やすことで世帯全体の手取りを最適化することができます。
2. 「iDeCo」や「ふるさと納税」などの節税制度を活用
また、「iDeCo」や「ふるさと納税」で税負担を抑えるのもひとつの手です。
iDeCoは正式名称を「個人型確定拠出年金」といい、自身で掛金を拠出・運用する「私的年金制度」です。「年金」とあるように、60歳まで引き出せないデメリットはあるものの、拠出した毎月の掛金は、全額所得控除の対象となります。
また、「ふるさと納税」は、故郷や応援したい自治体に寄付をすることによって、住民税の控除や所得税の払い戻し(還付)を受けることができます。
孝太郎さんはFPのアドバイスをもとに、節税対策に取り組むことを決めました。
「いやあ、息子には申し訳ないことをした。この歳まで節税対策を知らなかったことも、本当に情けない……。老後に向けて襟を正さなくちゃな」
これまでの自分を恥じるとともに、改めて税金対策の重要性を実感し、資産形成方法を見直す契機となったのでした。
辻本 剛士
神戸・辻本FP合同会社
代表