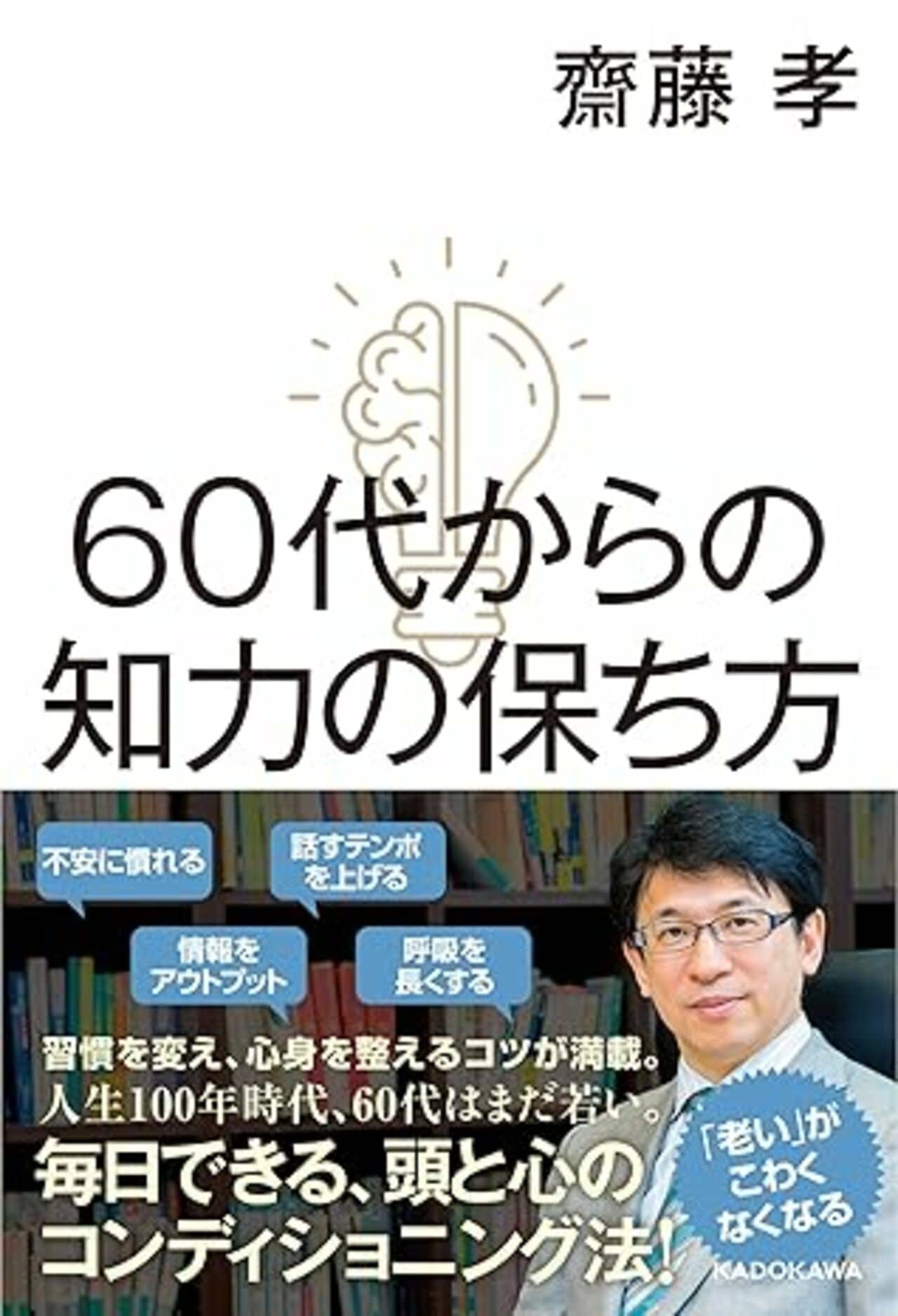誰にでも訪れる「老い」ですが、見た目だけでなく話し方にも老いはあらわれるといいます。本来、頭で考えるスピードのほうが話すスピードよりずっと速いはずですが、年をとると言葉が口から出てこないことが増えてくるのです。内容に意味をできるだけ含みながらテキパキと話す大切さについて、明治大学教授の齋藤孝氏による著書『60代からの知力の保ち方』(KADOKAWA)より一部抜粋・編集してご紹介いたします。

(※写真はイメージです/PIXTA)
この人、ちょっと老いたな…周囲にそう思われてしまう「見た目以外」の要注意ポイントとは【明治大学教授・齋藤孝氏が解説】
この人、ちょっと老いたな…と周囲が感じる瞬間とは
加齢による身体の変化にはあらがえません。白髪が増え、頭髪が抜けることもあるでしょう。シワやたるみ、シミが目立つようになり、猫背気味になるといった外見の変化に、私たちは敏感です。『人は見た目が9割』(竹内一郎著 新潮新書)というタイトルの本がありましたが、老いという点では、私は声や話し方の方が大事だと思います。
初対面の方は声の調子、話し方によって、印象が変わってきます。年齢は話し方に出るのです。「話すスピードが遅い」「言葉が出にくい」「終わりがはっきりしない」。これが老いの3点セットです。話の趣旨がぼやける、聞いたことに答えていないなど、総合的な判断で「この人、ちょっと老いたな」と、周囲は感じるのです。
私はテレビ出演が多いので、そこで特殊な訓練をしていると言っていいでしょう。例えば番組では、CMに切り替わる直前に5秒ほどのコメントを求められることがあります。緊張感漂う中で、言い間違いせず、言葉のセレクトも誤らずに、即座にバチッと決める。意識的な対応が要求されます。
大学の授業で人前に立ちますし、80、90分といった講演も、年間何本かこなします。滑らかに話している途中、あれなんだったっけと2秒止まるだけでも、聴いている側は何かおかしいと感じます。
若い頃から、私は澱みなく話すことを自分の特徴にしていこうと意識してきました。しゃべる速度は思考よりもずっと遅いからです。頭の回転に言葉がついていかないという感触は、文字にして文章を書く時にはっきりわかります。考えることが多すぎて、キーボードを打つ手が遅いと感じることがあります。つまり、話していて言葉が出てこないのは、頭の回転が遅いということなのです。