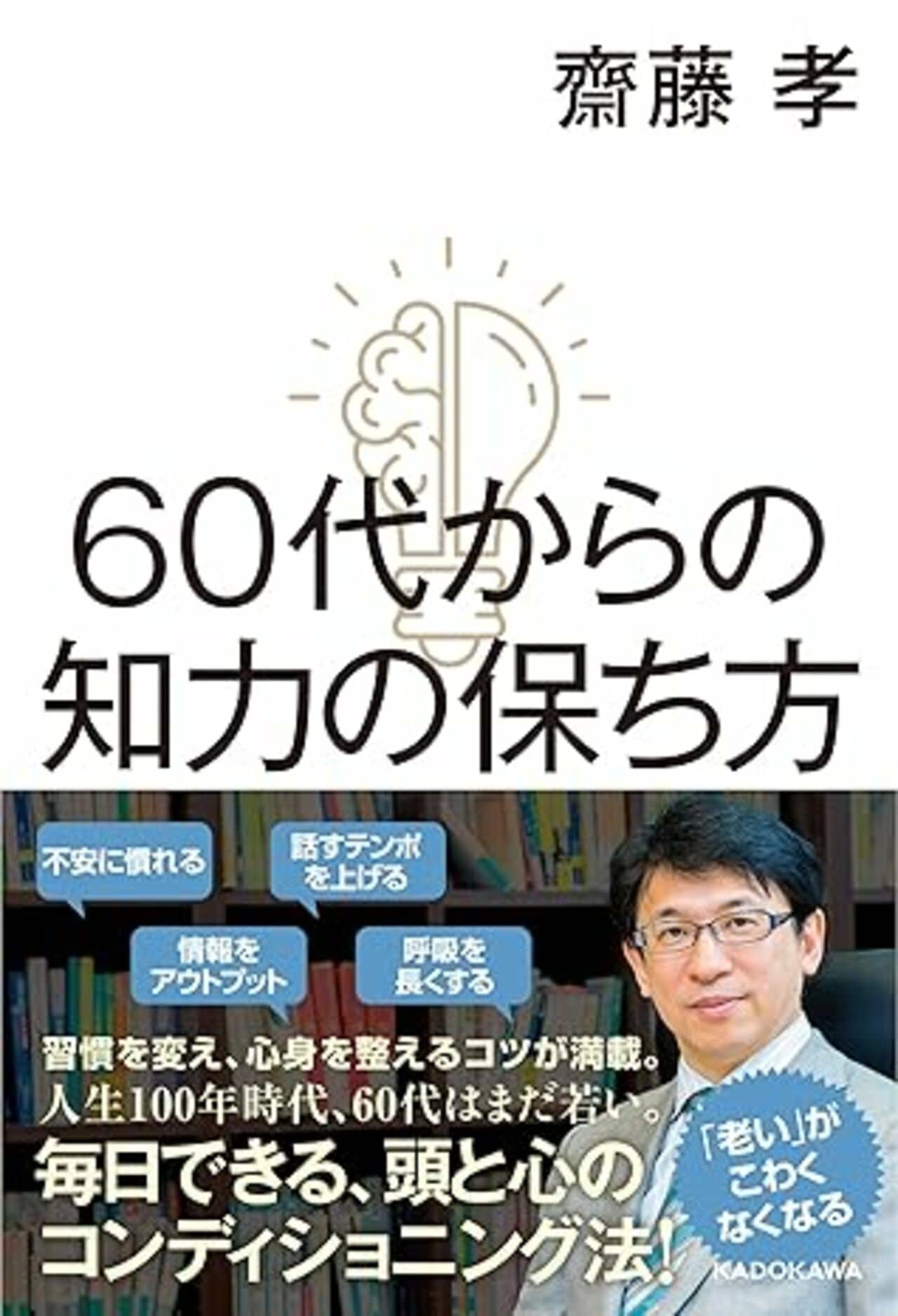誰にでも訪れる「老い」ですが、見た目だけでなく話し方にも老いはあらわれるといいます。本来、頭で考えるスピードのほうが話すスピードよりずっと速いはずですが、年をとると言葉が口から出てこないことが増えてくるのです。内容に意味をできるだけ含みながらテキパキと話す大切さについて、明治大学教授の齋藤孝氏による著書『60代からの知力の保ち方』(KADOKAWA)より一部抜粋・編集してご紹介いたします。

この人、ちょっと老いたな…周囲にそう思われてしまう「見た目以外」の要注意ポイントとは【明治大学教授・齋藤孝氏が解説】
頭の回転数を上げれば話す速度もスピーディーに
頭の回転数を上げると、話も必然的にスピーディーになります。私は学生に、「今から1分で話してください」とテーマを指定し発表させることがあります。学生たちは話の前や間に「えーと」とか、「あー」という、無意味な言葉や口癖を挟みがちです。
次に「では、15秒で話してください」とリクエストしてみます。内容に比べ、圧倒的に時間がないわけですから、速く話すしかない。テキパキ話す練習を続けると、15秒という時間を長く感じられるようになります。5秒で要旨を言うという指導も挟みます。「えーと」「あー」なんて言っている暇はありません。結論だけ言うことになります。
そこから逆に、15秒、1分と時間を延ばしていく。そういう訓練を経ると、どれだけ無駄な言葉が多くて話し方が遅かったのか、いかに言葉のセレクトのスピードが遅いのか、わかるようになります。
テキパキ話すことがうまかったのは、私が教えた学生の中では、アナウンサーになった安住紳一郎さんです。学生の頃から、単位時間当たりの意味の含有率が高かった。30分話しても内容のある話を続けられた。特別な能力だと思います。
話すスピードを横軸に、意味の含有率を縦軸にして考えてみますと、スラスラ話すけれど、意味の含有率が低い方もいます。もたもたしていて意味がないのが最悪です。
意味があって、ゆっくり話すのは、声の低い方に許された話し方です。味わいがあって、じっくり話すことによっていい話をしている印象を高める、という技術はありますが、私は、ゆっくり話すことが宿命的に許されない体質です。声質が高いからです。味わいとは無縁な声の質なので、ゆっくり話すとおかしく聞こえます。スピードがある方が似合っているのです。
高めの声で速めに話す訓練をすると、口の回転も、頭と口の連動もよくなります。単語は店頭に並んでいる商品のように、取り出しなれているとすぐに出てくるようになります。
齋藤 孝
明治大学文学部教授