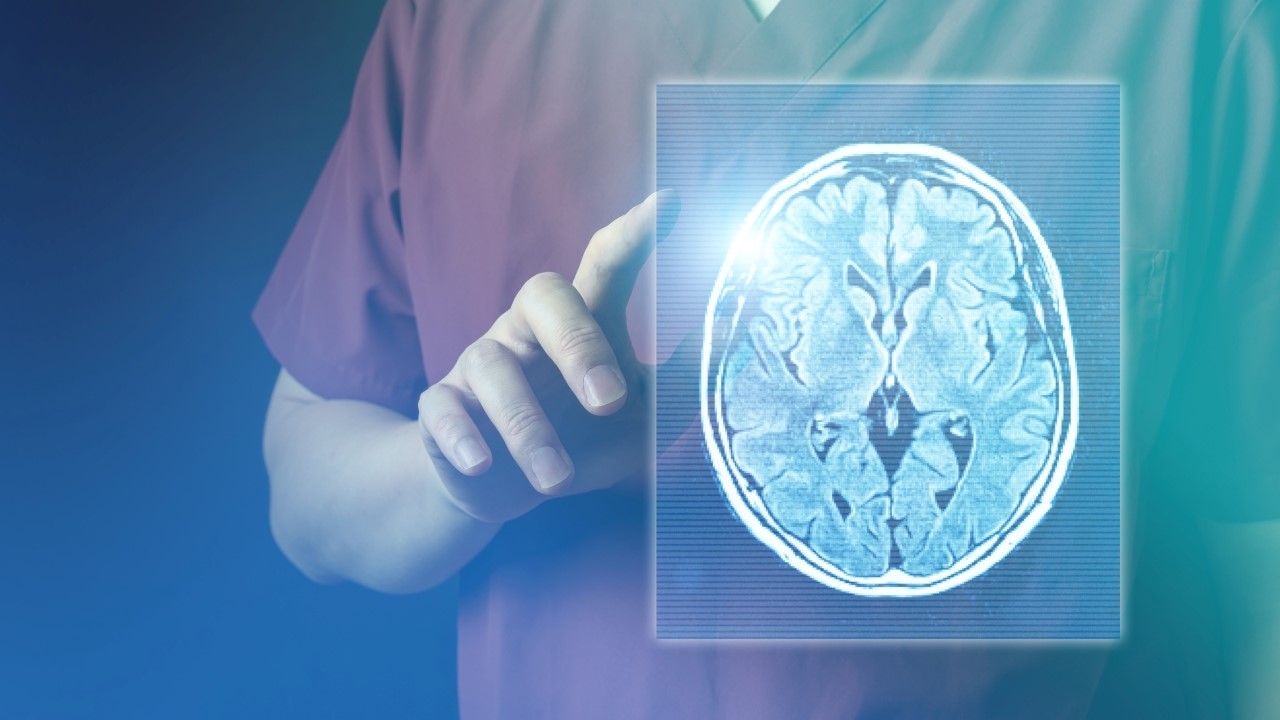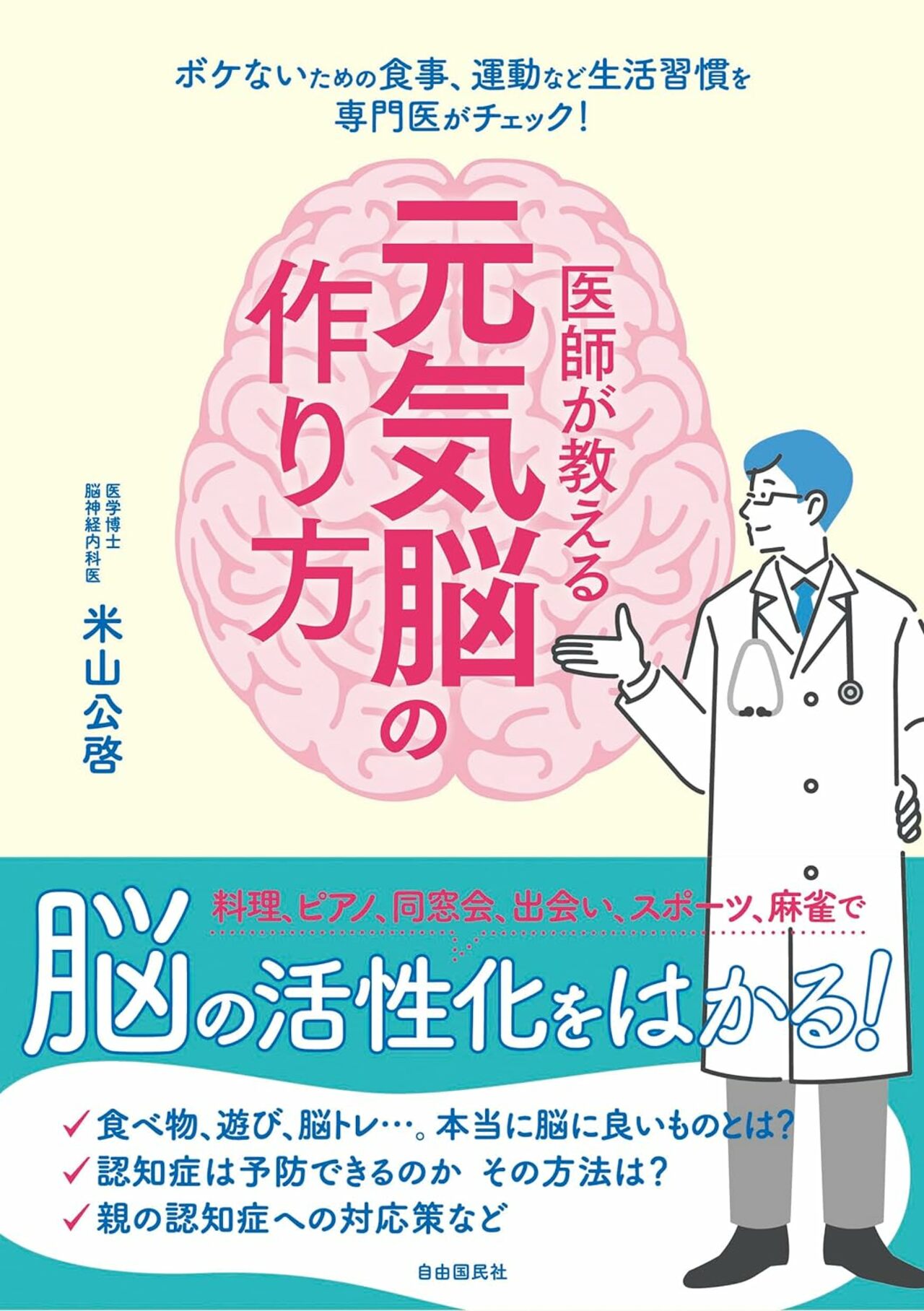いつまでも健康な脳でいたいですよね。それなら、ストレスのない生活をしましょう。脳神経内科医の米山公啓氏の著書『医師が教える元気脳の作り方』によると、脳の健康とストレスは大いに関係しているそうです。本書からその理由を紹介します。
ストレスに脳は非常に弱い
コロナ禍で、私もさすがに極度のストレスにさらされました。開業医というものが、リスクの高い仕事とはあまり思っていませんでしたが、コロナ禍でまだ治療法もわからない時期、それに向かっていかなければならないのは、かなりのストレスでした。
むろん病院に勤務する医者はもっと極限状態にいたと思いますが、感染のリスクという意味では、開業医もあったのです。そもそも、感染症に対する対策など、ほとんど知らないのが現状でしたし、そんな訓練も受けていなかったのです。
感染症という病気は、現代医学では、王道ではなく、むしろ隅に追いやられていた病気とも言えます。とくに先進国の医者はすっかり感染症のリスクからは遠ざかっていたのが現実でした。そこに突然新型コロナウイルスが出現したのです。日本の防疫システムも弱いですし、それ以上に感染症の専門家はごくわずかしかいませんでした。
開業医にしてみれば、まったく未知の話であり、どう対処していっていいのかわかりませんし、十分に情報も入ってきません。だから患者さんにどう接していけばいいのかもわからないまま、診療を続けたわけです。無論医師会などからサポートやアドバイスが十分にあったわけではなく、試行錯誤状態でした。
そのときのストレスは、想像以上のもので、コロナワクチンを接種するだけで、打っている医者のほうも実は非常に緊張して、疲れ果てていました。なので、コロナ禍の2年目には私自身かなりまいっていました。こんなストレスの中でどう仕事をしていけばいいのかよくわかりませんでした。医者の仕事がこれほどストレスの多いものとは思ってもいなかったのです。
そういったストレスに脳は非常に弱いのです。その象徴的な例が心的外傷後ストレス障害(PTSD)です。PTSDはベトナム戦争後の退役軍人の研究によってよく知られるようになりました。極限状態のストレスによって、不眠や小さな物音にもビクッとするような過覚醒状態、茫然自失、再体験、回避などの症状が出てきます。
そのPTSDの人の海馬に萎縮が見られたという報告が複数あります。海馬というのは、脳の中で記憶の保持、強化を司る場所です。海馬が萎縮するということは、記憶に関する機能不全が起こる可能性があることを意味します。つまりストレスによって脳の一部が壊れてしまうということです、海馬は記憶に関係するところですから、常にストレスがかかるような状況では、強いストレスでなくとも脳にいい影響が出ないことになります。
心配事や不安を抱えた人にMCI(軽度認知障害)が多いという研究もあります。MCIは認知症の一歩手前ですから、ストレス回避によって脳を守ることが、認知症の発症を抑えることになります。ストレスを受けると、体内ではそれに対抗するために、副腎からコルチゾールというホルモンが分泌されます。コルチゾールはからだに必要なものですが、慢性的なストレスによってコルチゾールが過剰に分泌されると、海馬の神経細胞が破壊され、萎縮してしまうのです。
さらにストレスは脳の大脳皮質前頭前野というもっとも人間にとって高度な機能を持つ場所に影響を与え、精神機能を奪う可能性があることもわかっています。前頭前野の感情を抑制する機能が作用しなくなり、強いストレスを感じると抑制できていた感情や衝動が爆発して、急な不安に襲われたりするようになります。
海馬同様に、前頭前野にある神経回路は日常のストレスや不安で刺激を受けやすく、前頭前野でストレスホルモンなどの神経伝達物質の濃度が上がると、神経細胞間の活動が低下して機能不全に陥るのです。原因であるストレス自体が減れば神経伝達物質の分解酵素が働くので、前頭前野の神経回路は元に戻ります。ただ、慢性的に長期間ストレスを受けていると、前頭前野の神経細胞は壊れてしまうので、元にはもどらなくなります。いかにストレスから解放されるかが重要な意味を持ってくるわけです。
私の場合、コロナ禍のストレスの多い時期、偶然時代小説の依頼が来たのです。今まで医学ミステリーは10冊以上、本を出していますが、時代小説はまったく書いたこともないものでした。有能で大ベテランの編集者のYさんのおかげで、1年掛かってようやく『看取り医 独庵』が完成しました。1750年前後を想定した江戸の医者が活躍する時代小説です。
昼間はコロナのワクチンをたくさん打って、疲労困憊でしたが、それでも深夜まで小説を書くことで、精神的なバランスを保っていたのです。ストレスを発散する方法は人それぞれです。自分なりのストレス発散法を持っていることが結局は自分の脳を守っていくことになります。