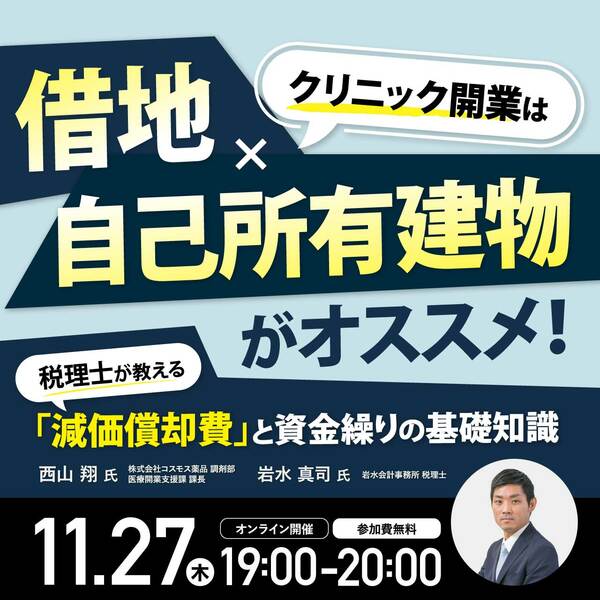医薬品卸会社、開業時には頼りになっても…
大手の医薬品卸会社には、医師の開業支援部門を置く会社も多く、利用しているドクターは珍しくありません。開業支援と同時に、医薬品・医療機器の販売や斡旋も実施しているため、同じ診療科のつながりはもちろん、開業予定地での競合となる医療機関の情報や、近年の医療情勢の動向などのノウハウ、情報を多数持っていることもあり、それをメリットと考えるドクターもいます。
そんな卸会社を利用して開業する場合、開業コンサルタント費用こそ無料または格安になりますが、医薬品購入等において、その会社を優先して取引するといったビジネス上の付き合いが必要になります。
ほかの卸会社と契約して薬品・医療機器の仕入れを行うことは、法的な規制こそありませんが、心理的に難しくなり、相見積もりなどによる競争原理が働かない場合もあります。結果、1社メインとなることで、長期的に見るとランニングコストが大きくなることが懸念されます。人情も大事ではありますが、公正かつ透明性の高い取引も確保するよう意識してください。
卸会社の取引は、複数社とやるべき理由
はじめて卸会社と取引をする場合は、数社との取引を行うことをお勧めします。
複数の卸会社と取引を行うことで、医薬品や医療機器の仕入れ値・販売価格の相場(原価など)が理解できるからです。仕入れ値の相場の情報がわかれば、卸会社が相場より高い価格を提示してきたときも、収益構造を見抜いて相見積もりを取るなど、価格交渉を行うことができます。価格競争をすることでクリニックの収支を改善し、よい品質の製品を上手に購入するセンスを磨きましょう。
また、開業時には内装工事のおおむね2~3ヵ月後からクリニックを運用することになります。卸の会社も大手や中小など様々ありますが、大手1~2社、中小1~2社といった具合に、複数社との取引が必要となります。
会社が大きければ人材も多いため、担当者の力量も玉石混交です。迅速かつ網羅的な対応ができる優秀な人材もいれば、そうでない人もいるでしょう。そんな営業担当者のキャラクターをしっかりと把握することが、長期的にクリニックを継続するうえで重要となります。薬品卸の担当者も、同様に販売ノルマがあることから、集患が期待できそうな院長か、患者が通いやすい立地か…など、冷静に見ているものです。
各社同時にカタログの持参を依頼し、医薬品と医療用備品の見積を、複数社に向けてメールやファックスで同時刻に依頼してみてください。この「同時の依頼」により、見積を提出する速さ、内容(価格)、納入方法について、シンプルに比較検討するのです。
今後クリニックを運営するにあたり、迅速な対応ができるかどうか、営業担当者の力量を推し量ることが重要だということはご理解いただけるでしょう。まずは、価格よりもレスポンスの速さが重要なのです。価格に関しては、数社揃ってから再度の交渉が可能であるため、この段階の優先度としては、最重要項目ではありません。
薬品卸会社の企業としてのカラーも重要である反面、営業担当者との相性もありますので、1番目、2番目に見積りを出したところを中心に、複数社とのお付き合いをはじめてみましょう。
取引先にさりげなく恩を売り、有利な取引につなげるのもテクニック
開業後、いろいろな医薬品を継続的に購入することになりますが、Aという製剤はX社、Bという薬品はY社…などと業者を使い分けつつ、全体のバランスを考えて取引・購入をするように心がけてください。特にインフルエンザワクチンが開始する10月より前には、卸からの納入回数によっては、自身が考えていたワクチン数を提供してもらえない場合もあります。6月から8月には、少し多めでもよいので医薬品を購入して心象をよくする、高額な医療機器を導入しておく…なども有効なテクニックとなります。
タイミングを合わせて先方の売上向上に協力するなど、モチベーションを高めるような取り組みも必要なのです。
可能であれば、自分の同級生や友人など、開業予定の方を紹介するという方法もひとつであります。高い医療機器の購入はせずに、紹介先で取引が成立することで、ギブアンドテイクではありませんが、便宜を図ってもらう、有益な情報提供をしてもらうといった、販売促進のルートの開発につなげることもできます。
担当者変更時の「リスクヘッジ」をどうするか?
担当者は早ければ数ヵ月、長ければ10年程度で変更になります。担当者が代わって対応が悪くなる場合もありますので、そのタイミングで取引の頻度・割合を変えてみることも重要です。トラブル回避のため、契約時にはそれぞれの企業と「取引契約」を実施しておくこともリスクヘッジとなります。
なにより、担当者と定期的に顔が見える関係構築を継続することで、自分のやりたい医療を展開していくことも可能となります。担当者がクリニックを訪問した際には、自分が日々思っていることやスタッフの意向・意見を踏まえ、数分でもよいのでコミュニケーションを図る営業努力も、開業医には必須な業務のひとつだといえます。
武井 智昭
株式会社TTコンサルティング 医師