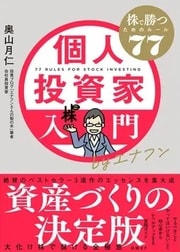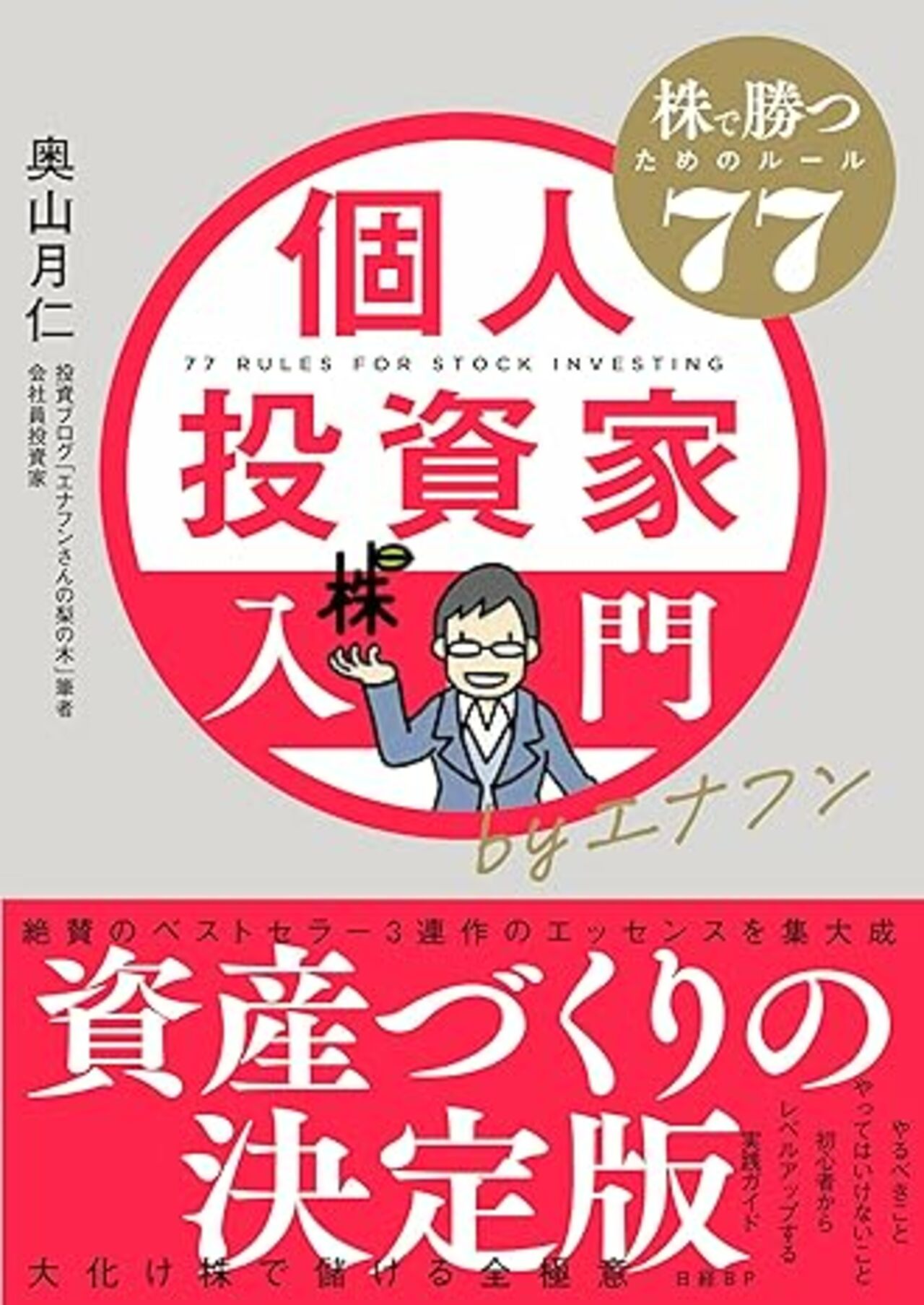成長株を見つけ出すのに重要なのが『会社四季報』の通読です。初心者でも始めやすい四季報の読み方について、人気投資ブログ「エナフンさんの梨の木」の筆者であり、会社員投資家である奥山月仁氏が解説します。奥山氏の著書『個人投資家入門byエナフン 株で勝つためのルール77』(日経BP)より、詳しく見ていきましょう。

“割安”な〈成長株〉で勝ちを狙いたいなら…『会社四季報』の読破こそ「手間はかかるが割に合う」手法と言える“納得のワケ”【人気投資ブロガーが読み方のコツを伝授】
「継続は力なり」が実を結ぶ
割安な成長株を探索する方法として、私が実践しているのは、東洋経済新報社が発行している季刊の株式投資情報誌『会社四季報』(以下、四季報)の通読である。
「えぇ~。あんな分厚い本を3ヵ月に1回読破するなんてあり得ない!」。この話をすると、多くの人は驚きと拒絶の反応を示す。
しかし、考えてみてほしい。毎日つらい思いをして会社で働いても、1年間に貯められる金額は本当にわずかだろう。仮に100万円貯められたとして、その努力を10年間継続してようやく1,000万円だ。
一方で真剣に成長株を探して10倍株を見つけて100万円分買えば、あとは何もしなくても100万円を1,000万円に増やせる。10倍株は無理にしても、買値から2~3倍に値上がりする株でも、金銭的な余裕は一変するはずだ。そのための努力として四季報を読む程度の手間は十分に割の合うものだと思うが、いかがだろうか?
四季報通読のメリットの1つ目は、上場企業を網羅的に知ることができる点である。四季報に掲載されている3919社(2023年4集秋号)という企業数は確かにとても多いが、手に負えないほど膨大な数でもない。大学受験に必要な英単語数(センター試験に必要な単語数は5000語と言われている)よりも少ない数字だ。
単語力がないと英語の試験で高得点が狙えないのと同じく、企業についての知識がないと大化け株を見いだす力も不足する。四季報が発行されるたびに読み込めば、次第に企業名やその会社の概要が頭に入ってくる。
しばらくは結果が伴わないかもしれない。しかし英単語学習と同様に、この取り組みはいつしか結果を出し始め、それに合わせて実力も着実に付いてくるはずだ。
2つ目のメリットは、読み続けることで相場観が身に付くことだ。すべての企業のPER、PBR、ROE、時価総額といった主要な株価指標の数値をざっと流し読むことで、市場は大体どのくらいの水準を妥当と判断しているのか、おおよその数字を感覚的につかめるようになる。
自分の保有銘柄だけを見ていると、まだまだ値上がりする気もするし、逆に値下がりしてしまうのではないかと不安にもなる。多くの企業の現実の数字を知ることで、自分の保有株が割安なのか割高なのか判断軸を持つことができるのだ。
相場は生き物である。ネットか何かで、「PER10倍以下、PBR1倍以下は割安と判断できる」などといった知識を得たとしても、それだけでは使えない。割安には割安である理由が存在するからだ。
その理由を1つひとつ理解しながらPERやPBRを確認することで、初めて割安か割高かという真の判断ができるようになる。その力を付けるために四季報を読むのである。
3つ目のメリットとしては、四季報を通読することで、成長株を見つけるチャンスが広がることだ。普段、いくらアンテナを高く張っていても、心理的な盲点にはまって、それが投資のネタだと気付かないことがある。ところが、四季報で具体的な企業情報を知ることによって、急にパズルのピースが埋まるように、有望株を発掘できることがある。
最後の4番目のメリットとして、値上がりする株の傾向がつかめる点を挙げたい。通常は四季報に掲載されている企業の中から有望と思われる企業をいくつかチェックしておき、その後、そこからさらに有望な選りすぐりの企業のみを購入する。このような手順で丹念に企業情報を調べ続けていくことになる。
その中で、チェックはしたものの、「買わない」と判断した銘柄のほうが大きく上昇するケースが結構出てくる。「しまった。この株がこんなに上がっていたとは……」。恐らくあなたはこんな悔しい思いを何度も味わうことになるだろう。
ここで「悔しいからこの会社のことはもう二度と調べない」と思わずに、「なぜ、こっちの株のほうが値上がりしたのか」と原因を丹念に調べる。そうすることで、株価が上昇する理由を極めて実践的に理解することができる。