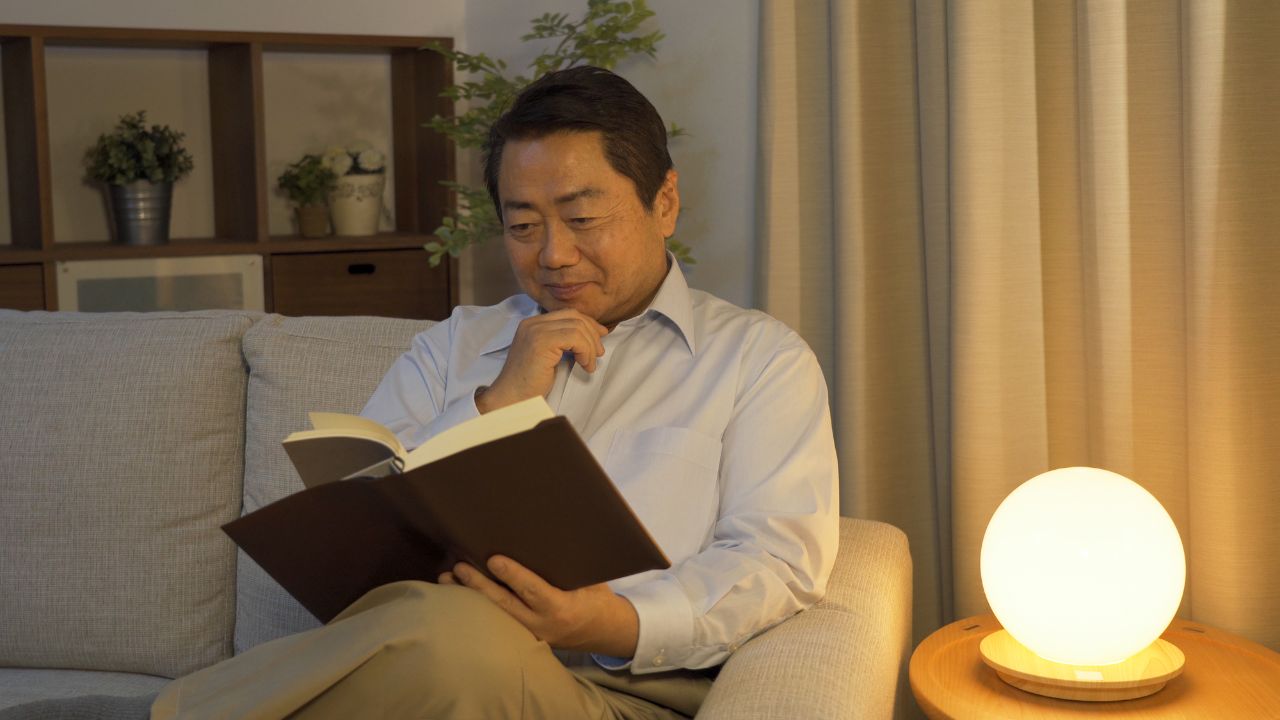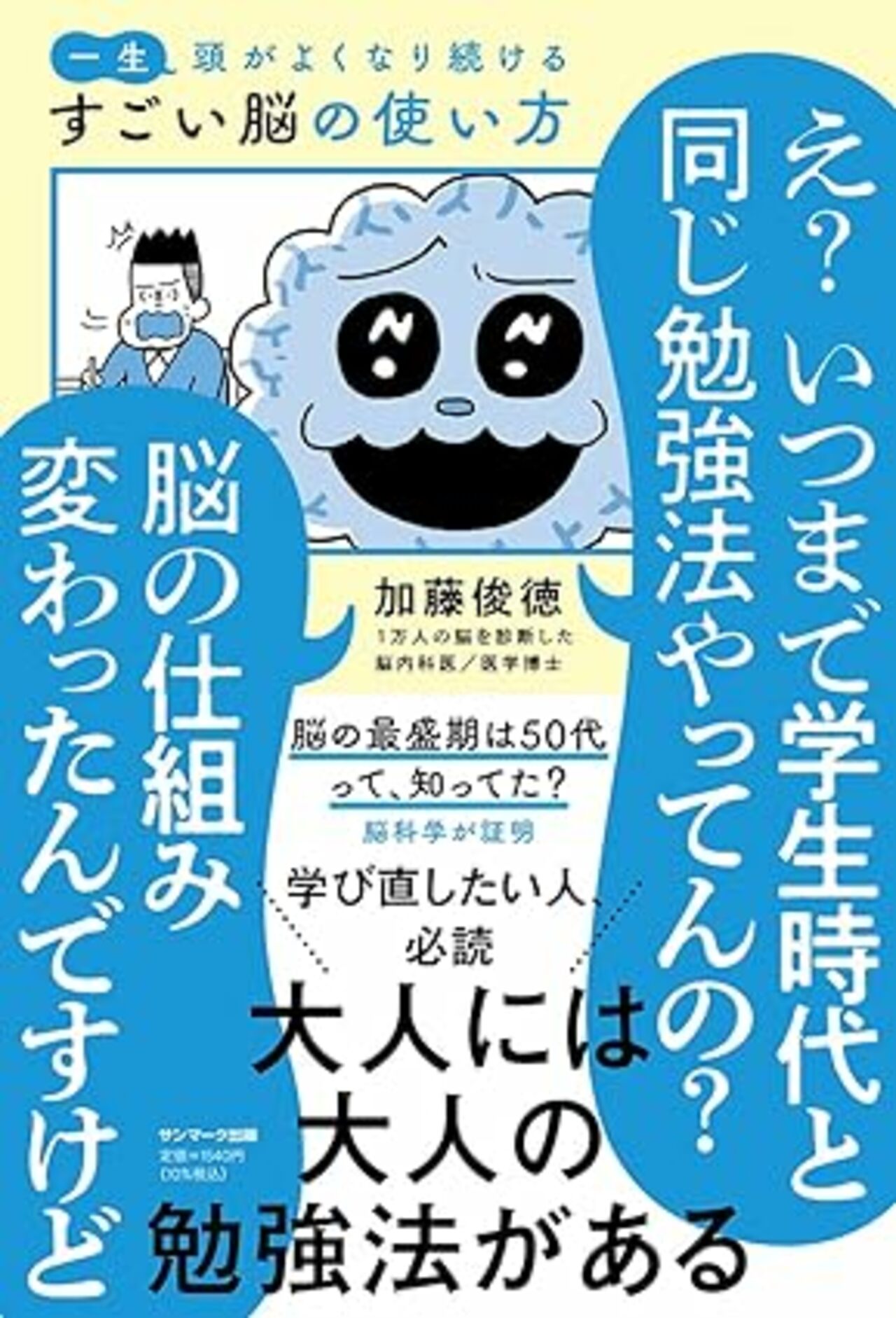新しいことや、とっつきにくい分野を勉強する際、いきなり難解な専門書に取り組むのはご法度! 今回は好きを引き寄せながら学んでいくコツについて、著書『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』(サンマーク出版)より、 加藤俊徳氏が解説します。

「あ、これ知っている」と思うページからでOK!…新しい分野に触れるときに使いたい“脳の特徴”【脳内科医が解説】
参考書をパラパラめくって「これ知ってる」のページから始める
私が新しいテーマに取り組む際も、小さな接点を見つける作業から始めています。
たとえば、難しい本が目の前にあったら、まずはパラパラパラッとページをめくり、単語なのか写真なのかはわかりませんが、自分の目が「これは知ってるぞ!」という反応を示したページを開き、その前後に書かれていることをまずは読んでみます。
そこで、「へぇ、この本で言いたいのはそういうことかぁ」と少しでも思えた瞬間、ついさっきまでは自分のテリトリーの外側にあった本がテリトリーの内側に入ってきて、本への親密度が高まっていることが実感できます。
1ページ目から読み始めて「退屈だなぁ」と思いながら苦労して読み進めても、苦労の割に、脳にはその情報が届いていません。これではコスパが悪いですよね。
サッカーが好きで海外のサッカー選手の名前なら苦労せずにどんどん覚えられるのに、世界史に出てくるカタカナの名前の偉人は全然頭に入ってこない、これに似たような経験を持っている人も多いのではないでしょうか。
このように脳は好きなものと好きでないものを明確に差別します。
脳は、好きなことには研究熱心で、さらにもっと知りたいという探究心を発揮します。
この特性を活かすためにも、退屈なものを退屈なところから読み始めてはいけないのです。
学生時代の勉強法が階段状に理解を積み重ねていく方法だとすれば、大人の勉強法は白地図の好きな場所から色を塗っていくようなイメージです。
最終的に白地図のすべてに色が塗れればいいわけで、どこから塗り始めたって何も問題はありません。
まずは小さな接点を見つけ、1つでも色を塗ることができれば、次は隣をちょっとのぞいてみようかなど、親密度を加速度的に高めていくことができます。
もし、分厚い本をパラパラとして自分の目が反応したページを読んでみてもいまひとつ理解が及ばないときは、別のアプローチを考えます。
たとえば、ある分野について理解を深めたいときは、その分野のスペシャリストである人物の自伝を読んでみるのもおすすめです。
「そっか、哲学書では難しいことばっかり言ってるけど、釣りが好きだったなんて知らなかったな」とか、「今は華やかに見えるけど、案外、苦労人なんだな」など、その人の人間らしさに触れることで親密度が増し、そのジャンルに対する抵抗感が薄まるという経験を私自身が何度もしています。
勉強したい内容とは関係のない自伝を読むのは遠回りのようにも感じますが、これから学ぶことへの親密度が高まれば、好意的に勉強に取り組めます。
脳が好意的になれば、その後の理解系脳番地、視覚系脳番地、聴覚系脳番地、記憶系脳番地の働き具合も大きく上がります。
大人になったら、「覚えなければならないもの」と「自分」の間にある溝をあの手この手で埋め、好きになれる接点をどうにかこうにか見つけましょう。あとは脳番地が自家発電しながらぐんぐん知識を吸収してくれます。
加藤 俊徳
加藤プラチナクリニック院長/株式会社脳の学校代表
脳内科医/医学博士