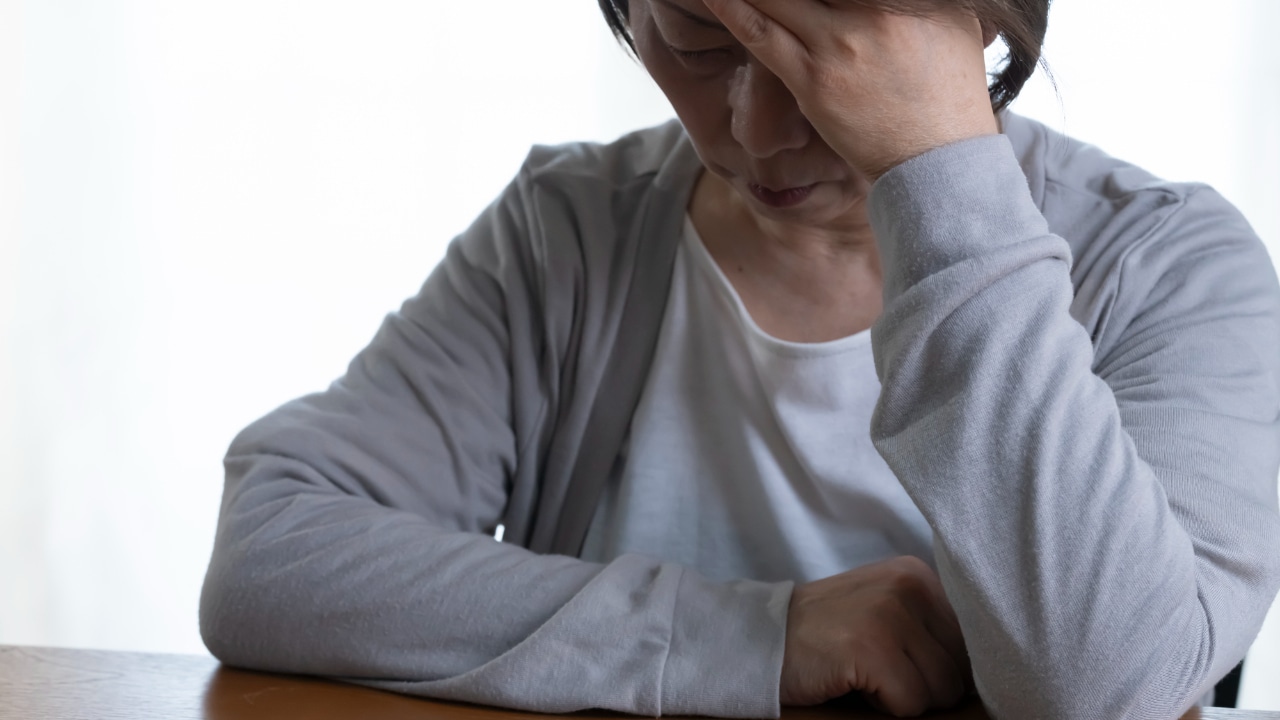公務員と聞くと「安定している」「年金・退職金が充実していて老後も安泰」などのイメージを抱いている人も多いのではないでしょうか。しかし、実のところ公務員であっても「老後破綻危機」に陥るケースは少なくありません。具体的な事例をもとに、株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の五十嵐義典CFPが解説します。

(※写真はイメージです/PIXTA)
悔しい…「年金月22万円」「貯金5,000万円」の65歳“勝ち組”元国家公務員、最愛の妻と満喫していた〈理想の老後〉が“たった1日”で崩壊したワケ【CFPの助言】
かつては“特別”だった公務員の年金制度だが…
国家公務員の退職共済年金(国家公務員共済組合連合会が支給する老齢厚生年金を含む)の平均年金額は189万1,000円で、そのうち男性は210万円、女性は163万6,000円とされています※。
※ 出典:財務省「国家公務員共済組合年金受給者実態調査(2020年)」
日本の公的年金制度は「2階建て」といわれ、1階部分の「国民年金」と2階部分の「厚生年金」に分かれます。公務員はこの2階部分が「共済年金」というものでした。
また国家公務員は、国家公務員共済組合連合会から退職共済年金を受給できます。さらに、“3階部分”として「職域加算」が設けられていました。この職域部分は保険料負担なしで受け取ることができたことから「公務員は年金制度が手厚い」といわれていたのです。
しかし、2015(平成27)年10月の「被用者年金一元化」により、公務員も「共済年金」ではなく「厚生年金」に加入することになりました。一元化以降に65歳になる人は、2階部分の年金が退職共済年金ではなく、老齢厚生年金となります。
ただし、経過措置により、2015年9月までの共済加入期間に対する職域部分は、退職共済年金(経過的職域加算)として受け取ることができます。
こうしたこともあり、依然として公務員の公的年金は民間企業よりも多くなりやすいといえるのです。
とはいえ、公務員で年金が多いからといって安心できるものではありません。老後の生活に大きな影響を与える突発的な出来事は、その職業に関係なく、ある日突然やってくるからです。そしてそれは、公務員であっても例外ではありません。