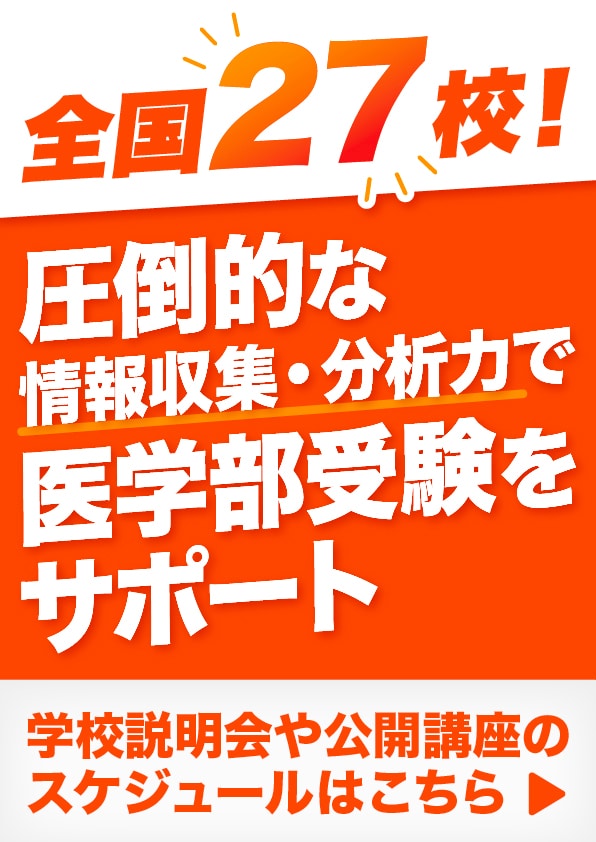化学
入試直前期の学習ポイント
まずは弱点を見つけて、その弱点を克服してください。不得意な単元はどうしても手が進まず、得意な問題ばかりを勉強し、嫌な単元は嫌なままで放置してしまいがちです。しかし、苦手な単元であればあるほど、実はそこに大きな伸びしろが隠れています。わかりにくい単元は高校の先生や塾・予備校の先生に質問し、弱点をどんどん克服して自分の強みに変えていってください。
弱点以外の単元については、現在使っている問題集を見直してみてください。そのなかで、間違える問題があれば何度も繰り返し解いて、「こういう論点が問題になっている。では、その答えを出すためにはどういう原理や原則に基づいて考えればよいのか。計算式や公式はどれを使うのか」という解法パターンをマスターしてください。
私立医学部〔1次〕・国公立医学部〔2次〕対策
医学部入試は試験時間が圧倒的に足りません。すべての問題を完答することは至難の業といえます。医学部入試で目指さなければならないのは、満点を取ることではなく合格することです。他の受験生より1点でも多く取り、合格ラインを超えなければなりません。そのためにするべきことは、「解ける問題から確実に正答し、点数を積み上げ、捨て問には絶対に手を出さないこと」です。
過去問演習の際にも、本番同様に「どの問題から手をつけるのか、その問題にどれだけの時間をかけるのか、捨て問はどれなのか」と作戦を立てて臨んでください。
その他注意点
各大学は多種多様な問題を出してくるので、理論、無機、有機の各分野をバランスよく演習してください。特に「気体」「平衡」「有機化合物の構造決定」は頻出ですので、これらの単元の問題演習はしっかりと取り組んでおきましょう。
また、見慣れないテーマとして「分子量測定法と質量分析計」〔’24日本医科大で出題〕、「ルミノール反応」〔’24日本医科大、’24帝京大で出題〕、「Van der Waalsの状態方程式」〔’24北海道大、’24東京医科歯科大(現・東京科学大)で出題〕、「人工甘味料」〔’23埼玉医科大、’23防衛医科大学校で出題〕などに注意しましょう。
さらに、出題単元とは別の切り口の話ですが、共通テストでよく見られる「会話文形式」にも要注意です。冗長な問題文に惑わされることなく、問われている内容の本質を掴む練習が欠かせません。
生物
入試直前期の学習ポイント
過去問演習は志望校の傾向を掴むのに有効です。試験本番のように時間制限を設けて演習を行えば、より効果が高まります。
一方、基礎・標準レベルの問題を解くことも忘れてはいけません。この時期は用語などの基本知識を失念するパターンが増えてくるからです。発展問題の演習量が増えたことで、問題を解くスピードは上がり、考え方の視野も広がっているでしょう。結果として解ける問題は増えていますが、発展問題に注力するあまり基礎知識が抜けていく状態になってしまっては、結局意味がありません。正答率が伸び悩んでいる人のなかには、この問題を抱えている人も少なくないと思います。
重要なのは学習のバランスです。入試本番まで毎日少しずつ、基本的な用語の意味をコツコツ確認していきましょう。用語などの知識を直接問う設問の配点は決して高くはありませんが、他の受験生が正答する部分で失点してしまうと、足もとを掬われかねません。
これまで得た知識を入試本番まで維持することは不可欠です。過去問の演習時間を調整しつつ、問題集の基礎・標準レベルの問題を解いて、本番直前まで「今までの学習を入試に生かす演習」に取り組んでいきましょう。
私立医学部〔1次〕対策
私立医学部の入試は、個々の大学の特徴が強く表れる傾向があります。そのため、事前に個々の大学の過去問の演習を通して特徴を掴んでおくことが必要です。各大学の傾向は年度を経るごとに少しずつ変わっていきますから、最低でも直近3年以上の過去問を演習しなければ、その大学の特徴を掴んだとはいえないでしょう。
大学によっては、過去に出題した内容を一部改題して出題する場合もあります。そのような大学は特に過去問演習が有効です。気になる受験生は、塾や予備校の先生に聞いて確認してみてください。
時間が許すのであれば、この過去問の演習、そして志望大学の特徴に対応した対策を立てましょう。小問集合で総合的な知識を問われるならば「抜けている知識の補完」を、特定の分野についての出題が多く見られるならば過去問の演習だけでなく、「教科書や資料集に記載されている内容を細かいところまで学習する」といったひと手間をプラスすることが、得点率をぐっと上げることに繋がります。
また、これは決して高い確率ではありませんが、他大学が過去に出題した内容と似た内容が出題されることがあります。私立医学部の場合、国公立と比較するとやや高めです。そのため個人的には、過去問をひととおり終えたあとに、同じ分野を出題したことのある大学の過去問演習に取り組むことをおすすめします。うまくいけば似た問題が本番に出題されるかもしれません。生物は初見の知識を問題から読み解いていくことが多いので、似た問題を一度解いた経験があると、かなりのアドバンテージとなるでしょう。
国公立医学部〔2次〕対策
国公立医学部は、私立医学部の対策と大きくは変わりません。ただし、単科医科大学は実験・考察系が多く出題され、総合大学は、生態系などの私立医学部では出題頻度の低い単元からも割と出題されます。
単科医科大学は過去問演習が有効であり、演習する問題がなくなったときは、近い内容の出題可能性も考え、他の単科医科大学の過去問の演習がおすすめです。総合大学は総合的な知識が要求されるので、過去問演習と並行して苦手な単元の学習を進めましょう。
また、国公立医学部は私立医学部と比べて記述量が多い傾向にあるので、本番までに記述・論述問題の添削指導を定期的に受けるようにしましょう。
物理
入試直前期の学習ポイント
この時期に分野ごとの典型問題が解けていないようならば、それは苦手分野です。まずはその典型問題を解けるようにするために、使用する公式や解法などを参考書や問題集で確認してください。それでもわからない場合は、高校の先生や塾・予備校の先生、チューターにどんどん質問して克服してください。
ある程度苦手分野は克服できているけれど伸び悩んでいるという人は、「公式の適用条件」や「なぜこの問題でこの公式を使うのか」を意識しながら学習を進めてください。
また、物理はケアレスミスが大きな失点に繋がってしまう教科でもあります。日々の演習でも、計算は慎重かつ正確に取り組み、解答の単位等を確認する習慣をつけ、ケアレスミスを少しでも減らせるよう工夫をしましょう。
私立医学部〔1次〕・国公立医学部〔2次〕対策
私立医学部の1次試験では、大学によって出題される内容や傾向が大きく異なります。標準的な問題を出題する大学もあれば、あまり見慣れない目新しい設定の問題や、医学に関連した内容の問題を出題する大学も見られます。
例えば、2024年の昭和大学では「水飲み鳥のしくみ」【熱】、2023年の慶應義塾大学では「眼球のモデル」【波】、順天堂大学では「腕でボールを持つときの骨と筋肉のようす」【力学】、2022年の東京慈恵会医科大学では「生体分子モーター」【電磁気】を扱った問題がそれぞれ出題されており、日常生活における科学的視点や実際の医学を意識した内容となっています。
また、問題量や記述量が多く試験時間が足りない大学もあります。受験する大学がどういう傾向の出題をしてくるのかを、過去問演習を通して把握しておくことが大切です。
同じ国公立医学部の2次試験でも、総合大学と単科医科大学では対策が異なります。総合大学は、標準的な問題を確実に得点できるように、弱点や穴のない勉強が大切になってきます。単科医科大学は、難度の高いいわゆる「捨て問」には手を出さずに、解ける問題を確実に取りに行くことが大切です。
その他注意点
「力学」や「電磁気」の分野は、どこの大学でも必ず出題される単元なので、弱点を残さないように勉強しておくことはいうまでもありません。「熱」や「波」、「原子」の各分野も後回しにせず、バランスよく勉強するようにしてください。「原子」分野の知識問題(放射線の単位や素粒子)も近年頻出です。定義などを必ず確認しておきましょう。
自分一人で全科目の弱点を見つけ出し、志望校の出題傾向を加味した対策を行うのは、今からではどうしても時間が足りません。
メディカルラボなら、国公立私立医学部82大学別にプロ講師が1対1で対策。短時間で効率よく対策が可能です。志望校対策が心配な方は一度、ご相談ください。