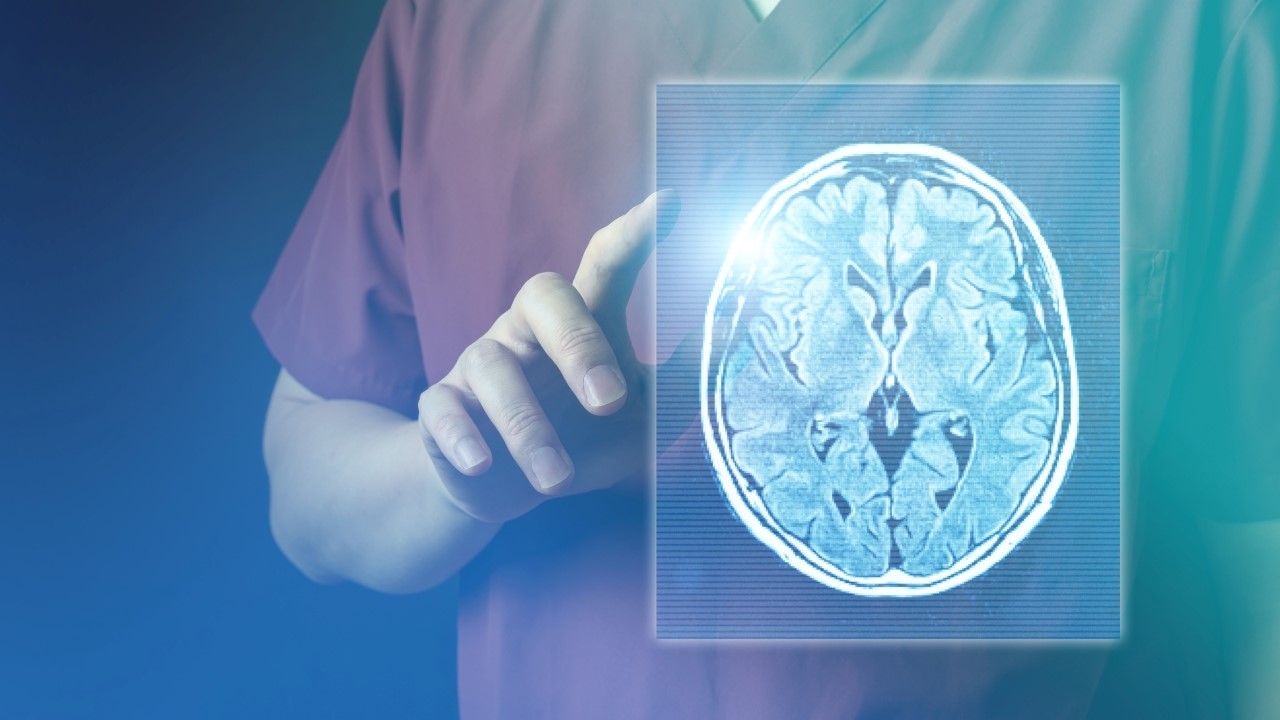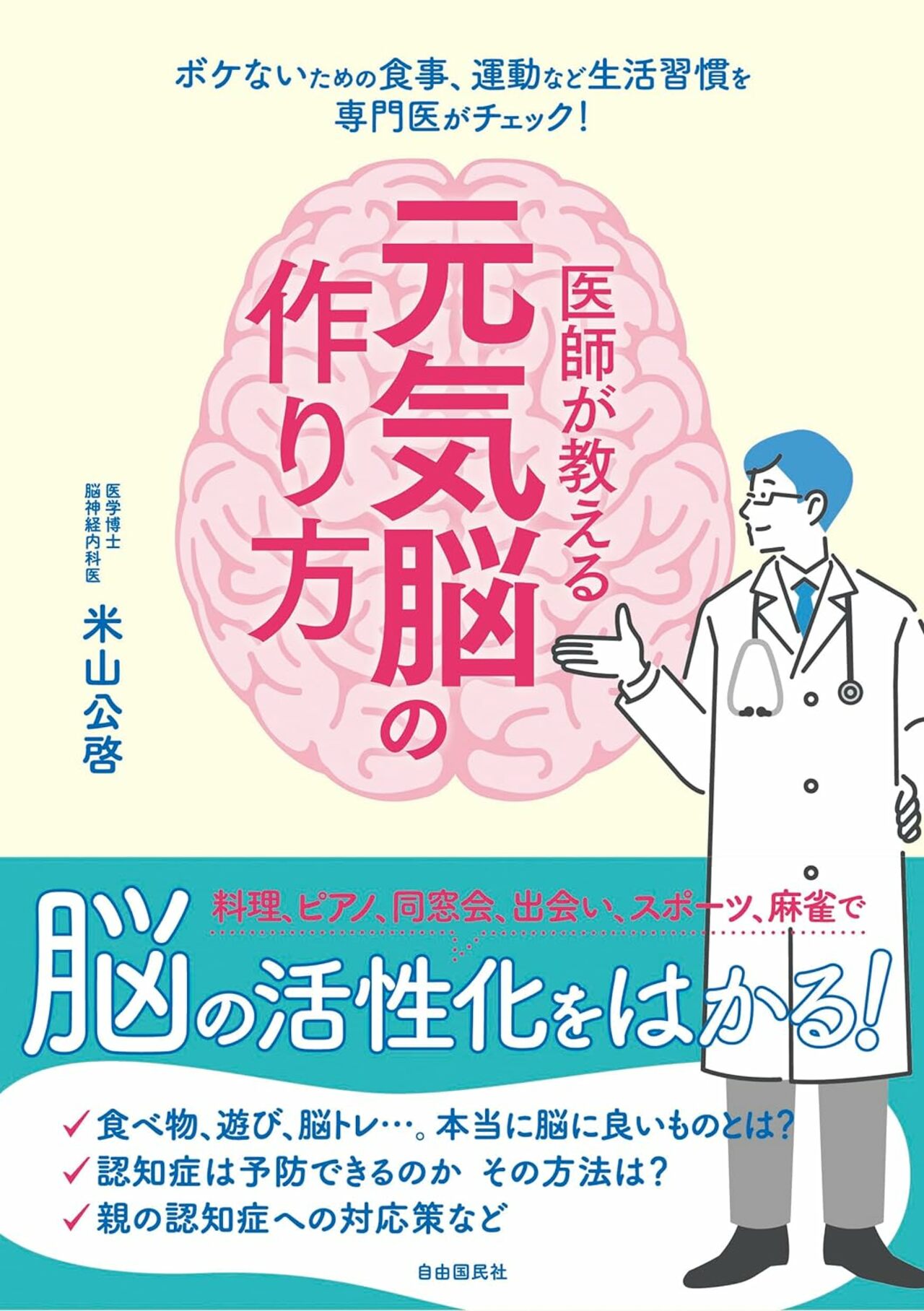いつまでも健康な脳でいたいですよね。そのためには、食べ物も関係があるのではないかと思いますよね。脳神経内科医の米山公啓氏の著書『医師が教える元気脳の作り方』によると、脳の健康と食べ物はあまり関係がないそうです。本書からその理由を紹介します。

食べ物で認知症を防げるのか?脳神経内科医が教える脳の健康と食べ物に関する研究結果
食べ物で認知症を防げるわけではない
どんな病気も食べ物で防げるのであれば、医者もいらなくなります。食べ物で防げる病気としては、ビタミンB1不足の脚気、ビタミンC欠乏の壊血病などが有名です。これはまだビタミンという概念がないときに、経験的に見つけだした病気とも言えます。
足りないものを補えば病気は防げるという考え方が浸透していますし、わかりやすいので、テレビのサプリメントでも○○が欠乏するから○○という病気になりやすくなるので、○○をたくさん摂りましょうということで宣伝をします。しかし、それは現代のようにまずビタミン不足などが起こりにくい状況にも関わらず、やたらに○○不足を煽って、サプリメントを売る手法とも言えます。
認知症も何かの不足によって起こる病気であれば、話は簡単ですが、残念ながら認知症は何かの欠乏で起こる病気ではありません。確かにビタミンB1などは脳の神経細胞の活動に必要な物質ですから、ビタミンB1が多く含まれる豚肉が脳にいいという言い方がされます。しかし、現代の食事環境では、ビタミンB1不足が起こる可能性は低く、豚肉を多く食べたところで、大きな影響はありません。
認知症と食事の関係は、様々な疫学調査がされて、それなりのデータはありますが、食べ物の疫学調査は、調査の限られた時期の食事を見ているだけです。10年間調査をしたといっても毎日何を食べたかを調べることは不可能でしょう。なので、新薬の効果を見るような調査とは違い、信頼度は低くなってしまうのです。
果物には抗酸化作用成分がたくさん含まれているので、認知症予防に有効とされています。果物に含まれる抗酸化物質は、ポリフェノール、アントシアニン、ビタミンなどです。脳にいいという視点で見ると、ブルーベリーやストロベリーのベリー類はいいとされます。血中の抗酸化物質のレベルが高い人は、認知症を発症する可能性が低いという研究報告があります。これによって、認知症の発症が数十年遅くなると報告しています。
抗酸化物質は、細胞損傷を引き起こすおそれのある酸化ストレスから、脳を保護するのに役立ちます。ビタミンA、C、Eとカルテノイド類の血中濃度を調べ、認知機能の低下や認知症との関連を調べた研究があります。その結果、抗酸化物質が多いほど、認知症の発症リスクが低いことと関連していました。
2015年、米シカゴのラッシュ大学医療センターで考案された“アルツハイマー病を予防する”食事法「MIND(マインド)食」の効果が発表されました。認知症になっていない高齢者923人を対象に、平均4年半にわたる観察を続けた結果、厳密にMIND食を行ったグループは、アルツハイマー病を発症するリスクが53%も低かったのです。
MIND食は、心臓病の予防効果やダイエット効果が確認されている地中海食、そして高血圧を防ぐために米国で考案されたDASH(ダッシュ)食という、2つの優れた食事法をベースに、認知症の予防を目的に考案された食事法です。MIND食で積極的に食べた方がいい果実は、ブルーベリーなどに代表される「ベリー類」です。ベリー類は優れた抗酸化作用を持つポリフェノール(アントシアニジンなど)を豊富に含みます。
ベリー類の摂取量が多い人は認知機能の低下が最大2.5年遅いという報告もあります。もちろんイチゴ(ストロベリー)でもいいのです。ブルーベリーは日本では普段食べることは少ないのでジャムなどで摂るほうがいいでしょう。日本ではベリー類は季節のものですから、冷凍食品などで常に食べる習慣を持ったほうがいいでしょう。果実といっても、カロリーが多いものもあるので注意が必要です。
ただかなり厳密にやった調査とはいえ、一般の人がそれを守っていけるかということです。脳にいいと言われても、10年もそれを続けることはまず難しいでしょう。そこが現実的ではないということになります。わかっていたとしても、実行できないそれが食事療法なのではないでしょうか。
魚をよく食べる人ほど認知症のリスクが低く、15年後の認知症のリスクが61%低下したという日本の研究があります。魚に含まれる「DHA」(ドコサヘキサエン酸)、「EPA」(エイコサペンタエン酸)、「DPA」(ドコサペンタエン酸)、「α - リノレン酸」は動脈硬化や血栓を防ぎ、血圧を下げます。LDLコレステロールを減らす作用があり、脳の血管にはプラスに作用します、それが認知症のリスクを下げるのでしょう。
また他の日本の研究で5.7年間の追跡研究の結果、魚を多く食べるほど認知症リスクが下がりました。ただこういう研究はアンケート調査です。精度の高い研究は難しく、認知症ですでに魚をあまり食べられないという結果を見ている危険もあります。魚は脳にいい、認知症予防につながると言い切るにはもっと長期の研究データが必要でしょう。
また光る魚がいいと以前から言われていますが、そこまで詳しい調査がされていないので、魚の種類でどの程度影響があるのかはまだはっきりしません。魚は脳にいいとは以前から言われてきていますが、結局、信頼度の高い疫学調査は難しいのです。ベリー類がいいというデータは示しましたが、ビタミンA、C、Eなど多数の抗酸化物質の血中濃度を測定した結果、「ルテイン」「ゼアキサンチン」などの抗酸化物質の血中濃度が高い人は、低い人に比べて認知症リスクが低下することがわかりました。
ルテインやゼアキサンチンは、緑黄色野菜に多く含まれている物質で、ニンジン、ホウレンソウ、カボチャ、ブロッコリー、ケールなどに含まれています。ただこういう研究は、ある時期にどれくらい緑黄色野菜を摂ったかを調べているだけですから、生涯にわたって抗酸化物質をどれくらいとればいいのかはわかりません。食事と病気の関係はなかなか簡単には結論が出せないものです。
またホモシステインという、ほうれん草やブロッコリー、イチゴなどに含まれる物質は、有害なアミノ酸を無害化する働きを持つ葉酸(ビタミンB群の一種)が多く含まれています。血液中のホモシステイン濃度が上がると脳梗塞などの原因となる動脈硬化の抑制に働くので、脳血管性認知症の予防に有効な物質です。
緑黄色野菜、ベリー類、魚類は脳によさそうということは言えそうですが、それだけで認知症を防げるということではありません。コンビニで切った野菜を売り始めています。少なくともそういったものを食べる習慣が、あったほうが10年くらいの期間で見ていけば、有利になるかもしれません。
ただ70歳を過ぎてから、そういう食生活にしてどこまで脳にいいのかはまったくわかりません。40歳代から食生活を改善していかなければ、もの忘れが始まったときにいくら食事療法を開始しても無理というものです。そのあたりの検討はしていないので、なんとも言えないのが現実でしょう。