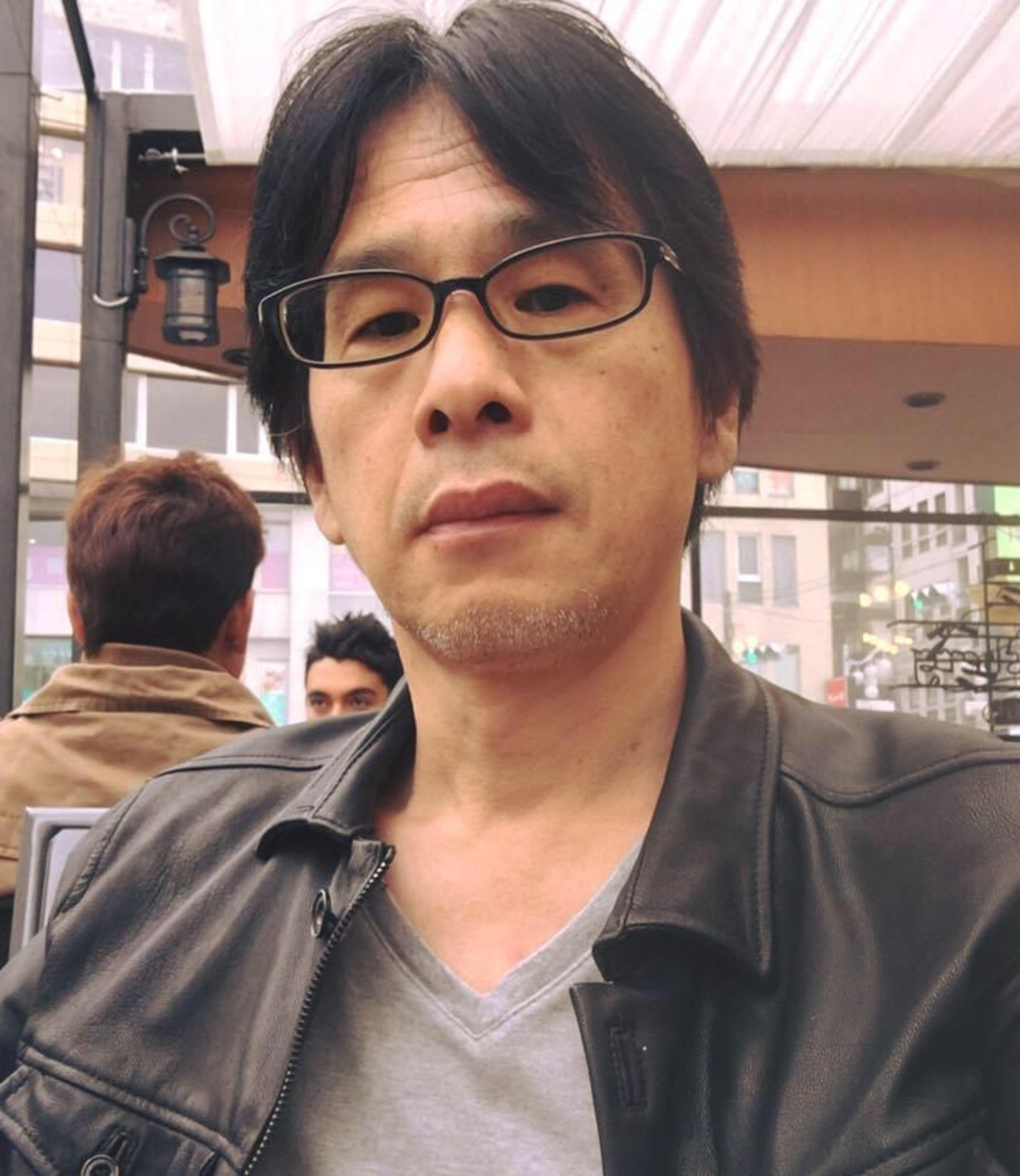4月から放送が開始された連続テレビ小説「虎に翼」。その主人公のモデルとなった「三淵嘉子」は、ついに裁判官の見習いともいえる“判事補”に任官されます。本記事では、青山誠氏による著書『三淵嘉子 日本法曹界に女性活躍の道を拓いた「トラママ」』(KADOKAWA)から一部抜粋し、日本初の「女性裁判官」が誕生した経緯についてご紹介します。

『虎に翼』寅子のモデル・三淵嘉子は〈日本で2番目の女性裁判官〉…嘉子が日本初の女性裁判官「石渡満子」に抱いた感情は?
三淵嘉子が女性の地位向上に「躊躇」を覚えるワケ
権利を有する者には、それに相応した自覚と責任が求められる。突然に大金を得て金持ちになった者は、金の使い方がわからず散財し〝にわか成金〞などと蔑(さげす)まれる。
敗戦のショックで茫然(ぼうぜん)自失となっている間に、日本は民主主義の国になっていた。知らぬ間に、自由が降ってわいた……当時、大多数の女性たちは、そんな感じではなかったか? いきなり与えられたものをどう使ったらいいのか分からない。
「はたして、現実の日本の女性が、それにこたえられるだろうか」
彼女は当時の心境を、このように語っている。
最高裁判所でも発揮された三淵嘉子の才能
民法改正事業がひと段落した昭和23年(1948)1月、嘉子は司法省民事部から最高裁判所事務局に異動している。
前年の5月3日に日本国憲法が施行されると同時に最高裁判所が発足。司法省の隣にあった旧大審院の建物が、そのまま最高裁判所として使われることになった。嘉子は裁判所事務局内に設けられた家庭局に配属され、民事訴訟など家庭裁判所関係の法律問題や司法行政の事務を担当した。あいかわらず男性が圧倒的に多い職場だったが、
「女性であるために不快な思いをしたことは、一度もありませんでした」
と言う。むしろ年配の男性職員や裁判官たちにはかわいがられ、色々と気を遣ってもらえる。高学歴のインテリたちが集まる職場だけに、いち早く新時代にあわせた職場内の意識改革がなされたのだろうか。
あるいは、嘉子のキャラクターがそうさせたのかもしれない。見知らぬ相手でも物怖(ものお)じせず、ぐいぐいと距離を詰めてくる積極性はあいかわらず。女学生のように天真爛漫(らんまん)で憎めない。ふくよかな丸顔には笑顔がよく似合い、誰からも好感を抱かれる。
だから先輩の裁判官たちも親身になって色々と教えようとする。教えられ上手。それも彼女がもつひとつの才能だろう。
最高裁判所で仕事をするうちに、嘉子は裁判官に必要なスキルをどんどんと身につけてゆく。それが認められて、昭和24年(1949)8月には東京地方裁判所民事部の判事補に任官された。