公私を分けて生活している人もいるでしょう。そういった考え方には、大きなトラブルを起こりにくくする一方で、意外なデメリットが潜んでいるかもしれません。本記事では、米ハーバード大学医学大学院・精神医学教授のロバート・ウォールディンガー氏とハーバード成人発達研究の副責任者を務める心理学教授のマーク・シュルツ氏による共著『グッド・ライフ 幸せになるのに、遅すぎることはない』(&books/辰巳出版)から一部抜粋し、公私と職場の「雰囲気」の関係性について解説します。
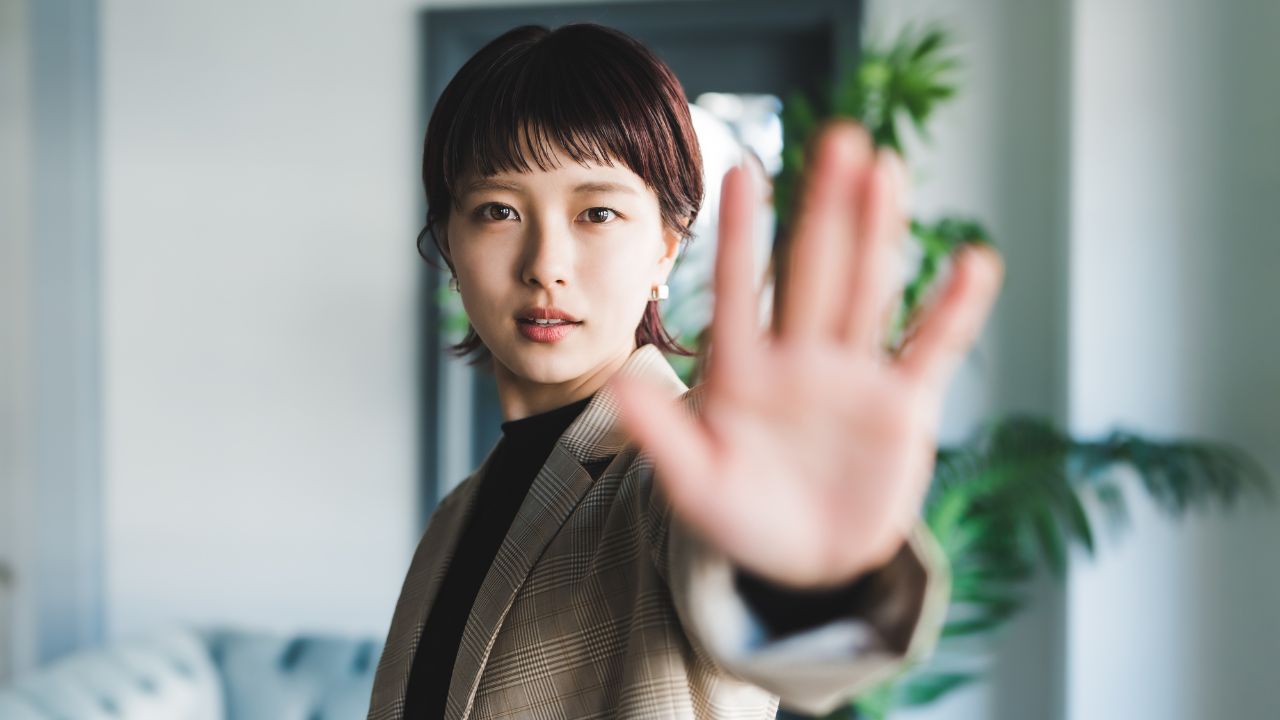
「職場に友達」は不適切? 同僚との付き合いを意識的に避けるようになった女性の後悔【ハーバード大の幸福論】
不平等や権力勾配がもたらす歪み
職場で良好な人間関係を求める際に、気をつけるべきことがある。昔から、社会的弱者は、職場でも他の人より大きな負担や苦労があった。20世紀前半、本研究のボストン都市部の被験者の大半は欧州や中東の貧困地域からの移民であり、社会的弱者だった。
学生自治会研究の被験者だった女性たちも社会的弱者だった。今日でも女性や有色人種は職場でさまざまな壁に直面しており、社会的弱者だ。
そして、職場において不平等や偏見が蔓延している場合、損得抜きのまっとうな人間関係を築くのは難しい。
「今、とても不安なんです」と、1973年、前述の学生自治会研究の被験者レベッカ・テイラーは研究チームに語った。「勤務先の病院が看護師を何人か解雇しようとしていて、私もその一人かもしれないんです。先日、男性医師たちが『看護師を辞めさせたって、大した問題にはならないさ。どうせ共稼ぎで大黒柱の夫がいるんだから』と話しているのが聞こえきたんです。
私はいてもたってもいられなくなり、話に割って入りました。『いいかげんにしてよ! どういうつもり? 女の看護師は背負うものがなくて気楽だ、看護師なんてみんな同じだって言いたいわけ?』と言ってしまいました。本当に頭にきていたんです。職場には男女差別がはびこっています。私の知る限り、病院の経営陣も同じです。私なんていつ仕事を失ってもおかしくない。不安でたまりません」
男性中心の心理学界で女性として活躍したメアリー・エインズワースも職場で性差別を受けた。1960年代初頭のジョンズ・ホプキンズ大学では、職員用のカフェテリアは男性専用だった。報酬も男性より低かった。若い頃には、女性であることを理由に、カナダのクイーンズ大学が研究職採用を見送った。もし彼女が差別を乗り越えて活躍しなかったら、心理学の分野も本書の内容もまったく違っていたはずだ。
職場における女性差別については世界各地で改善が見られるものの、不平等は根強く残っている。米国では1960年以降、職場における女性の役割が大きく変化した。今では女性がかつてないほど多様な職に就き、長時間働いている。だが、家庭内の女性の役割には、それに見合った変化が起こっていない。
社会学者のアーリー・ホックシールドは1989年の著書『セカンド・シフト』の中で、職場で女性が担う役割には革命が起きたが、家庭で女性が担う役割はほとんど変わっていないし、子育て中の夫婦でも事情は同じだ、と述べている。
ホックシールドの指摘から30年以上が経過したが、夫婦間での家事や育児の分担は今も不公平なままだ。
筆者らが実施している夫婦療法でも、頻繁に見られる問題だ。男性は、家事を夫婦で平等に負担していると思っていることが多い。父親の世代より家事を負担しているのはたしかだ。だが、男性の家事時間は本人たちが思うより少ない。例えば、女性は夕食をつくる、男性は食器洗い機に食器を入れるという分担なら、女性の負担は一時間、男性の負担は数分のみだ。
女性が子どもの宿題を手伝い、男性は寝る前に子どもに絵本を読み聞かせている場合も、女性は30分、男性は15分の負担だ。もちろん、夫婦の関係のあり方は千差万別だ。だが、統計的には、今も女性のほうが家事時間の負担が大きい。











