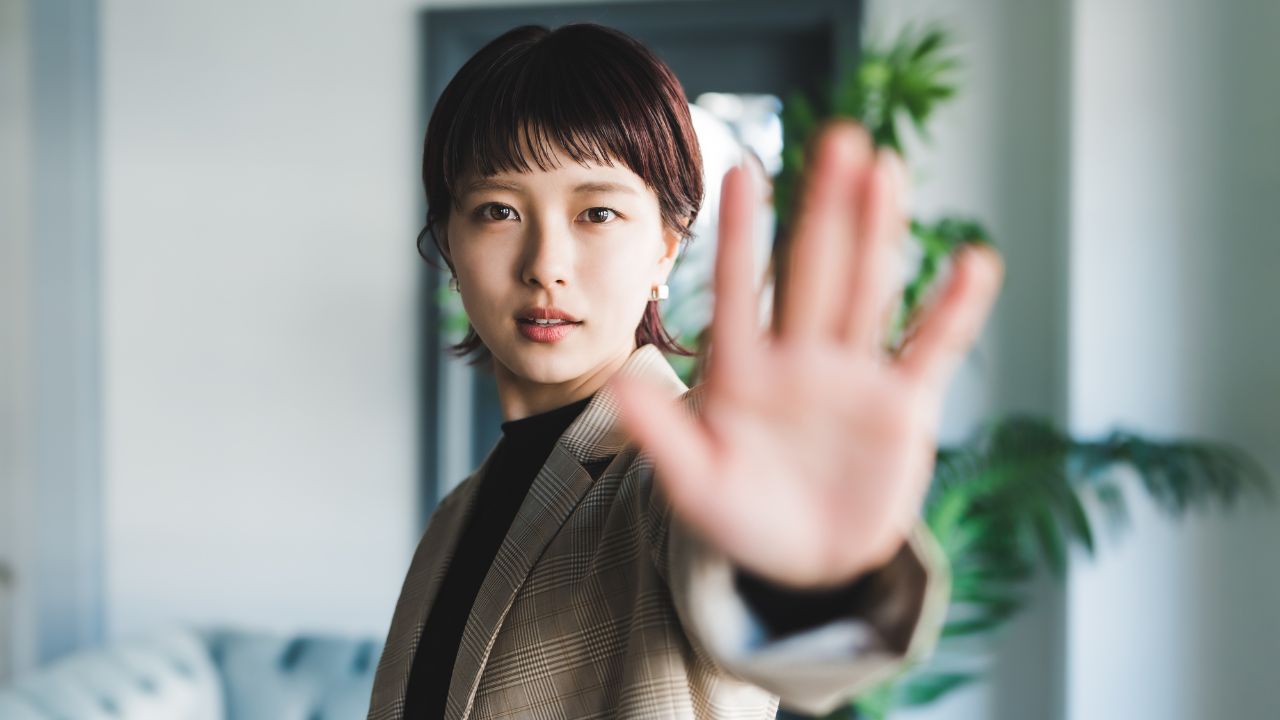就職・転職活動では「給与」や「福利厚生」に目がいくもの。しかしながら、本当に重視すべきは「職場の人間関係」かもしれません。本記事では、2,000人以上の人生を85年かけて調査した「ハーバード成人発達研究」を元にした『グッド・ライフ 幸せになるのに、遅すぎることはない』(&books/辰巳出版)から一部抜粋し、仕事の場で感じる「孤独」を解消するコツについて解説します。

「職場に親友はいますか?」85年にわたるハーバード大の〈幸せ研究〉が導いた、仕事のストレスが和らぐ〈たった1つの要素〉
心通い合う関係は、福利厚生になる
ビクターはボストンのノースエンド地区で、シリア系移民の子として育った。本研究では数少ない、アラビア語を話す家族出身の被験者だ。ノースエンドはイタリア系移民が非常に多い地区だったため、幼いビクターはなじめないと感じることが多かった。
対面調査を行うたびに、研究チームは彼の知性の高さと自意識の強さに驚いていた。ところが本人は、自分は周りの子より頭が悪い、と思い込んでいた。子どもの頃、同級生がずる休みしたり家出したりすると、頭が良すぎて学校が退屈なんだろうとか、自分よりも勇気があるな、などと考えた。
「ビクターは率直で、気さくで、愛すべき少年で、いつも周りに気を配っています。でも神経質な子です」と、中学校の担任教師は研究チームに語った。
20代のときは職を転々としていたが、ニューイングランド地方を営業エリアとする小さなトラック会社を設立したいとこから、働かないかと誘われた。ビクターは一度は断った。だが、その後結婚し、いとこの会社が成功して支社を増やすと、考え直した。
「一人で過ごすのが好きだから、トラックドライバーの仕事は悪くないかも、と思ったんです」
数年後、ビクターは会社の共同経営者になり、ドライバーの仕事を続けながら、会社の利益の一部を受け取る立場になった。
収入は上がり、妻子にいい暮らしをさせているという誇りも生まれた。だが、孤独感は消えなかった。仕事で数日間家を留守にすることもあったし、定期的に交流する友人もいなかった。いとこは職場で唯一、よく知っている人間だったが、短気で、会社の経営方針をめぐって衝突することも多かった。
この会社に勤めて20年が経った頃、ビクターは研究チームに対し、「なまじ給料がよかったせいで他のことに挑戦できなかった。仕事が人生の重荷になっていた」と語った。
「勇気があったら会社を辞めていたと思います。でも、今の収入を手放せないから、辞められない。死ぬまでトレッドミルの上を走っている気分です」
世の中では、ビクターのように仕事を選べない人のほうが普通だ。生まれ育った境遇や経済的理由により選択肢が限られ、心が満たされない仕事を続けるほかない人もたくさんいる。
また、満足度が最も低い職種と最も孤独感の強い職種が一致するのも偶然ではない。一昔前までは、孤独な仕事といえばトラックドライバーや夜間警備員など、夜勤のある仕事だった。
しかし、今どきは、新興産業のIT産業にも孤独な職種がたくさんある。例えば、ネット通販の配送やフードデリバリーといった単発の請負仕事(いわゆるギグワーク)には、同僚がいない。