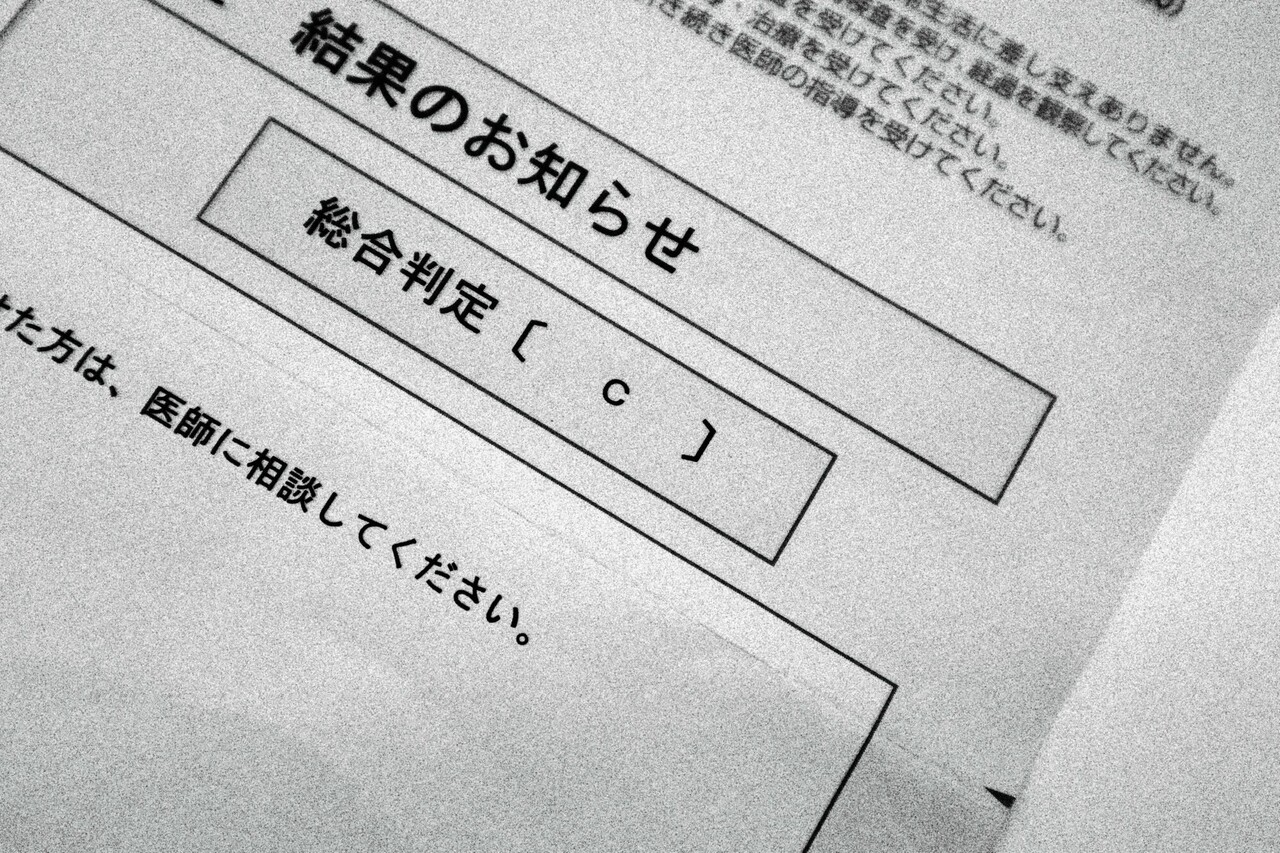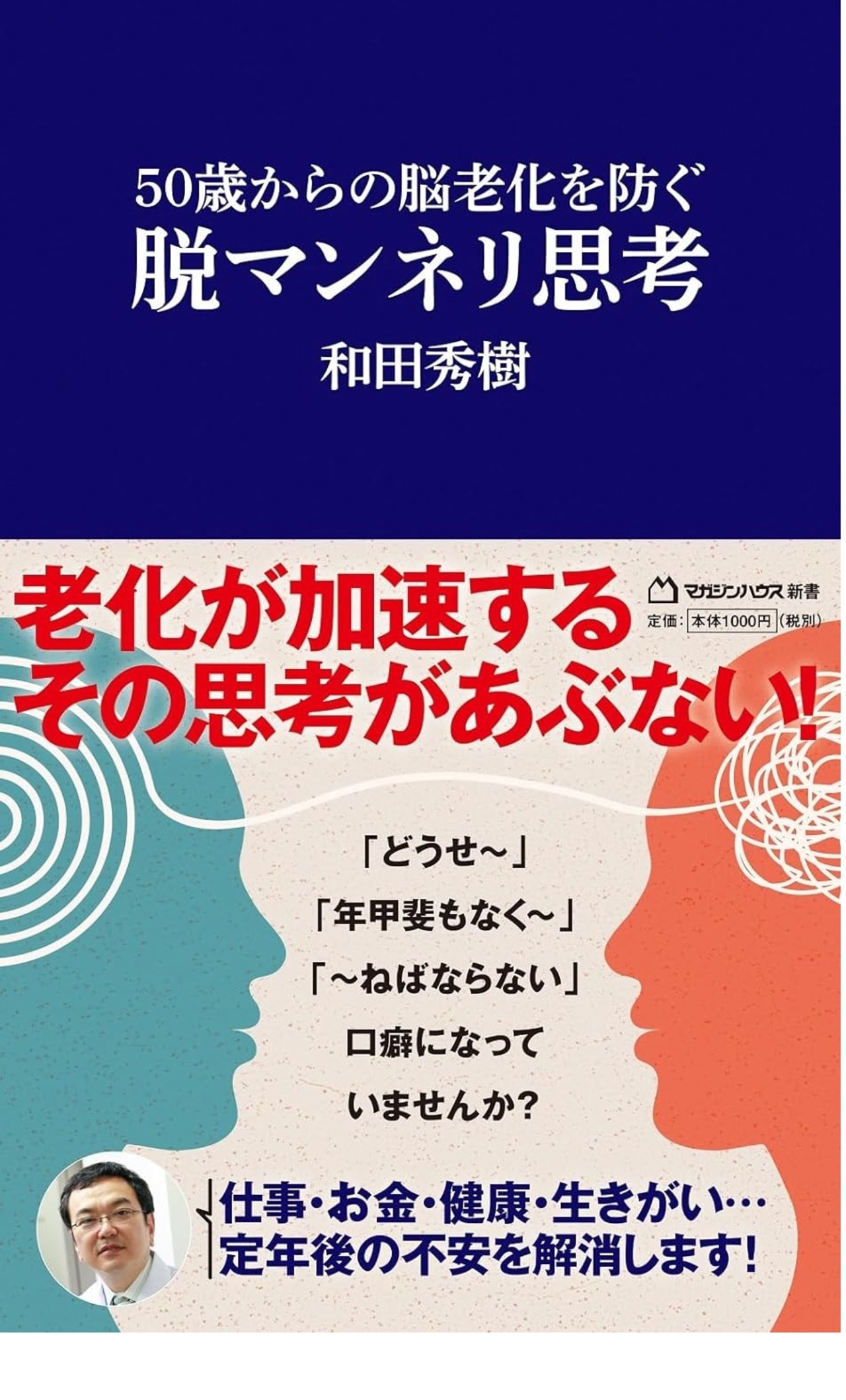自由に生きることができることは、いくつになっても元気を支える大切な環境です。親の介護は子どもがするべきといった世間体に囚われ、子どもが「親を面倒みなければ」と思っても、かえって親に悪影響が出ることがあります。本記事では、『50歳からの脳老化を防ぐ 脱マンネリ思考』(マガジンハウス)の著者で医師の和田秀樹氏が、親と子の関係について解説します。

1人気ままに暮らしていた90歳女性、子どもの世話になった途端に動悸、食欲不振に…「親の介護は子どもがする」は世間体を気にした単なる“エゴ”【有名医師が解説】
「昔は子どもが親の介護をしていた」というのは大きな誤解
結局、子どもが親の介護をするというのは美談でも何でもなく、ただ子どもの「育ててもらったんだから今度は面倒みなくちゃ」という責任感だけが先走った結果という気がします。地方の場合はそれにプラスして世間体もあります。施設に預けられた親は「可哀そうに、子どもにも見放されて」と同情されたり、逆に自宅で子どもの献身的な介護を受けている親は「△△さんは幸せね」と羨ましがられることは珍しくないからです。
「でも昔はみんな自宅で介護していた」という人もいますが、これにも大きな誤解があります。たとえば平均寿命を考えてみましょう。1955年(昭和30年)の平均寿命は男性が63歳、女性が67歳です。つまり、およそ60年前は介護が必要になる前に寿命が尽きていたのです。現代ほど医療の進んでいない時代ですから、寝たきりになってもその期間も短かったはず。
さらにはあまり知られていませんが、70年代から90年代にかけては、高齢者を老人病院に入院させることがごく一般的に行われていました。いわゆる「社会的入院」と呼ばれるもので、病気の治療が目的ではなく長期間介護することが目的でした。
この老人病院にはひどいところが多くて、一部屋に大勢の老人を押し込み一日中点滴を打つだけというところも珍しくありませんでした。かなり劣悪な環境が多くて、わたしから見ればまさに「姥捨山」でした。
ところが不思議なことに、親を老人ホームに入れるのは世間体が悪いと考えても、老人病院に入れることに対しては、子どもは罪悪感を持たなかったのです。病院と名前がついていれば「医者の世話になっているんだから仕方ない」と周囲も子どもも納得しやすかったのでしょう。
現在では医療費削減の観点から社会的入院のための介護療養病床の廃止(2024年3月末)が決定しています。介護施設も増えていますし、超老人大国となった日本の介護職員は技術も知識も含めて世界でも高いレベルにあります。
介護保険が始まって以来それがどんどん向上しています。医療に関しても素早く対応できますから、介護施設のほうがお年寄りの生活の質が上がるという側面もあります。実際に在宅介護の手に負えなくなって施設に預け、それで親が元気に朗らかになったという例は多いのです。
久しぶりに会ったら身体だって動けるようになったとか、自宅ではめったに見せなかった笑顔に出会えて驚いたという話はよく聞きます。いずれにしても「親の介護は子どもがするもの」というのは、現実を無視して世間体だけに囚われた考え方ということができるはずです。
和田 秀樹
精神科医