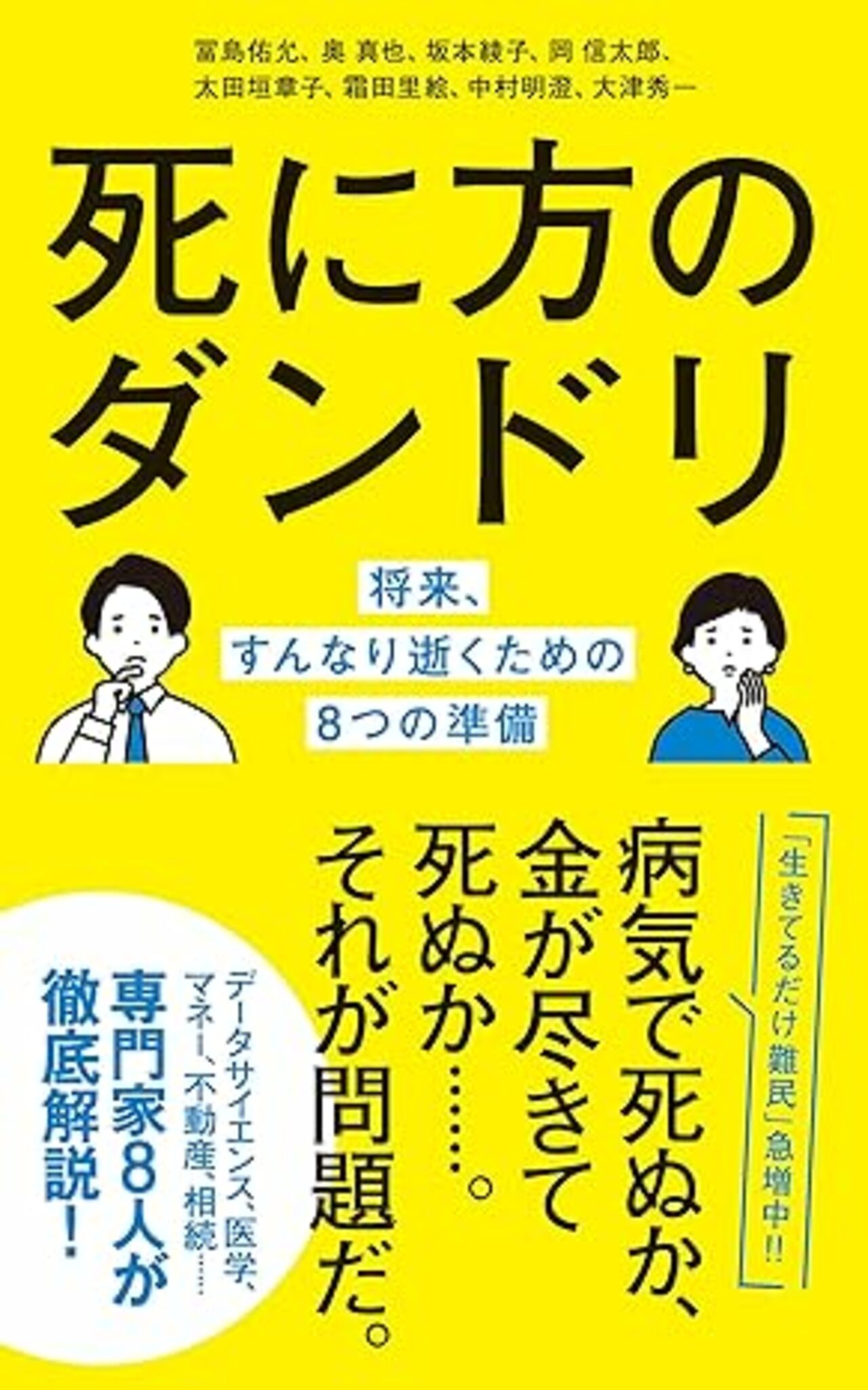当然ですが、生きていくうえで「住まい」は必要不可欠です。しかし70歳以上の高齢者はその「住まい」を確保する難易度が格段にあがると、司法書士の太田垣 章子氏はいいます。いったいなぜなのでしょうか。『死に方のダンドリ』(ポプラ新書)より、詳しくみていきましょう。

(※写真はイメージです/PIXTA)
内覧希望のメールを無視!?…家主や不動産会社のホンネ「できれば高齢者に貸したくない」のワケ【司法書士が解説】
高齢者の賃貸は「家主のリスクが高すぎる」ため敬遠されがちに…
そもそも賃借人が亡くなったことを知らず、家主側から連絡を受けるような場合や、賃借人が亡くなったことを知っても知らぬ顔をしている場合は、賃借人との関係が希薄なのでしょう。そうなると亡くなった賃借人が多額の借金や家賃の滞納をしていても、知らない可能性があります。後から相続人のところに借金取りが来ても困ってしまうため、保身を考えて相続放棄をしたいと考える人が多いのも致し方ありません。
ところが相続人が相続放棄したからと言って、不在者財産管理人のときと同じで、このまま終われるわけではありません。
相続人が相続放棄してしまい、次順位の相続人も相続放棄して、相続人が誰もいなくなった場合には、民法上は相続財産清算人を選任申し立てし、その清算人と手続きを取っていくことになります。すべての手続きが終わるまで、少なくとも1年以上はかかってしまいますが、家主側は当然、その間の賃料報酬を得ることができません。
また相続財産清算人はボランティアではないため、賃借人の資産から報酬が得られないとなると、辞任せざるを得なくなることもあります。そうなれば、家主側は何もできない、ということになってしまいます。結果、家主側にすべての負担がのしかかってしまうというわけです。
部屋の賃借人が孤独死した場合の、具体的なトラブルを挙げてみます。
・相続人である家族が相続放棄してしまったので、荷物の処分をしなければならなくなった
・遺品整理に多額の費用と時間がかかり、その費用が家主負担となった
・死臭や亡くなった痕跡が残り、次の借り手が見つからず、建物が取り壊しとなった
・生活保護受給者だったが、亡くなった日からの家賃補助が打ち切られ、室内の家財道具撤去費用を負担してもらえなかった
・連帯保証人である遺族に無視され、遺品の引き取りにも来ない
・病死であっても近隣の噂で耳に入るので、募集しても入居申し込みがない
・遺品整理に多額の費用と時間がかかり、その費用が家主負担となった
・死臭や亡くなった痕跡が残り、次の借り手が見つからず、建物が取り壊しとなった
・生活保護受給者だったが、亡くなった日からの家賃補助が打ち切られ、室内の家財道具撤去費用を負担してもらえなかった
・連帯保証人である遺族に無視され、遺品の引き取りにも来ない
・病死であっても近隣の噂で耳に入るので、募集しても入居申し込みがない
こうした声を聞くと、家主や不動産会社が「できれば高齢者に貸したくない」と思うのは無理からぬことかもしれません。
太田垣 章子
司法書士