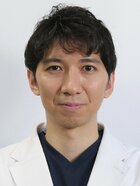(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)
盛り上がりを見せる遠隔手術の現状

現在、世界で最も認知され、日本の医療現場レベルにおいて最も導入が進んでいる手術支援ロボットは、米国インテュイティブ・サージカル社が販売する「Da Vinci(ダビンチ)サージカルシステム」です。2000年に初めて米国FDA(食品医薬品局)で使用が承認され、日本でも2012年、泌尿器科領域の前立腺がんに対して初めて薬事承認されました。現在までに外科領域や婦人科領域までその適応を拡大させたこともあってか、国内では、2022年時点で400台以上が導入されています。
実際、Da Vinciサージカルシステムはすでに、大学病院やがん専門病院といった大病院(400床以上)に限らず、ごく一般的な市中病院でも導入が進んでいます。例えば筆者が所属する病床数240床の常磐病院も、2012年に第一世代のDa Vinci Sを購入し、2020年には当時最新型だったDa Vinci Xiに買い替えを行なっているほどです。ちなみにZeusロボットシステムは2001年にFDAの承認を得ましたが、2003年に米国コンピューターモーション社が米国インテュイティブ社に吸収合併され、同年、Zeusの販売は中止されました。これにより、手術支援ロボットの開発は、Da Vinciに一本化され、現在に至るまで大きく発展してきました。
他方、日本国内では、2020年8月に川崎重工株式会社とシスメックス株式会社の共同出資により設立された株式会社メディカロイドが、手術支援ロボット「hinotoriTM(ヒノトリ)サージカルロボットシステム」について、泌尿器科領域での製造販売承認を取得しました。さらに、2022年10月には、消化器外科・婦人科領域でも承認を取得しました。
このように国産の手術支援ロボットが開発・承認されたことも、遠隔手術が盛り上がりを見せている一つの理由と言えるでしょう。事実、2023年になって報道されている国内の遠隔手術の実証実験は、hinotoriを用いたものです。例えば2023年4月7日には、hinotoriを用いて、東京の外科医が300km離れた愛知県での手術を想定した実験が行われました。この実験では、操作の際に生じるタイムラグはわずか0.032秒だったといいます。
話が逸れましたが、Da Vinci、hinotoriいずれにおいても、術者は、術野に入らずに手術を実施していきます。すなわち、術者は術野の外に用意された飛行機のコックピットのような装置に座り、術野で患者に取り付けられたロボットアームを操作して、手術を実施します。それでもこれまでは、術者が患者と同じ手術室内で操作を行うのが一般的でした。ですが術者が術野に入る必要がない以上、通信手段さえ担保されるのであれば、遠隔で安全に手術を実施することも、原理的に可能になったということです。
実用化は可能か?遠隔手術の今後

ロボット支援手術システムが急速に普及している一方で、医療現場への応用については、多くの課題が蓄積しているのも事実です。最大の課題は、ハードやインフラです。ここまで述べてきたように、遠隔手術の実施には、手術支援ロボットと安定的な通信が欠かせず、加えてこれらの高度な技術が、手術中を通じていずれも問題なく機能しなくてはいけません。すなわち、これらの技術に不具合や故障があると手術の遅延や合併症に直結しかねないことは、肝に銘じられるべきでしょう。特に術者と患者に取り付けられたシステム間のデータ伝送の「遅延」は、術者がリアルタイムで正確な動作を行う能力に影響を及ぼす重大なリスクとなります。これは今後、遠隔手術の応用を広く進めていく際に、最大の障壁となるかもしれません。
また遠隔手術が、都市部と地方あるいは僻地の間での手術を想定していることも、ハードやインフラの課題を困難にする可能性があります。現在日本では5G回線の普及が進んでおり、タイムラグを起こすことなく医師の動きを正確に再現できる通信環境は徐々に整いつつあると言えます。しかし、5G回線の普及は都市部が中心で、遠隔地では後れているのが実情です。そのため、もし地方や僻地などにおいて遠隔手術を実施しようとする場合、特別な回線が必要となる可能性があります。特別な回線の導入・維持には莫大なコストがかかる可能性も考えられ、持続性は乏しくなるでしょう。そもそも、高価な手術支援ロボットの導入は、地方や僻地では十分な症例を確保できず、採算が合わない可能性があります。一方で、ある程度の人口規模の地方都市であれば、ロボット支援手術の体制が一定程度整備されていて遠隔手術を必要としないケースも考えられます。外部からの経済的な支援などに頼らず、自立可能な形で、小規模の地方自治体や僻地で遠隔手術をいかに実施していくかは、今後の大きな課題でしょう。
さらに、遠隔地の外科医が手術を実施することについての説明や同意の取得、何らかの突発的な問題が生じた際の責任の所在などの問題もあります。そのほか、患者データをネットワーク経由で送信する際に、サイバーセキュリティ上のリスクにさらされる可能性もあります。これらの懸念に対処するためには、明確なルール作りや、法的・規制的枠組みが必要です。
とはいえ筆者自身は、遠隔手術に伴う様々な制約は、将来的に克服可能と考えています。ただし、遠隔手術を使用する場面は限定されるかもしれません。少なくとも、私見では、遠隔手術は、手術支援ロボットの導入を加速し、その手術手技の教育スピードを向上させる上で、大いに役立つように思います。すなわち、現在は指導者がわざわざ現地を訪問してロボット支援手術を指導していますが、遠隔手術によって、このような指導がより容易になる可能性があるということです。
ひいては今後、遠隔技術による海外への手術支援なども広がる可能性があります。もちろん、その際には再度、手術支援ロボットがそもそも現地に存在するか、安定的な通信システムが存在するかといった課題に取り組む必要があります。しかし、もし海外の人々が遠隔支援手術を本当に必要とし、そのための技術が求められるのであれば、何らかの形で克服されていくと筆者は考えています。
*
尾崎 章彦
ときわ会常磐病院乳腺甲状腺外科
福島県いわき市在住。いわきと南相馬で地域医療に従事しながら、震災に伴う健康影響の調査のほか、製薬マネーが医療に及ぼす影響などを調査している。