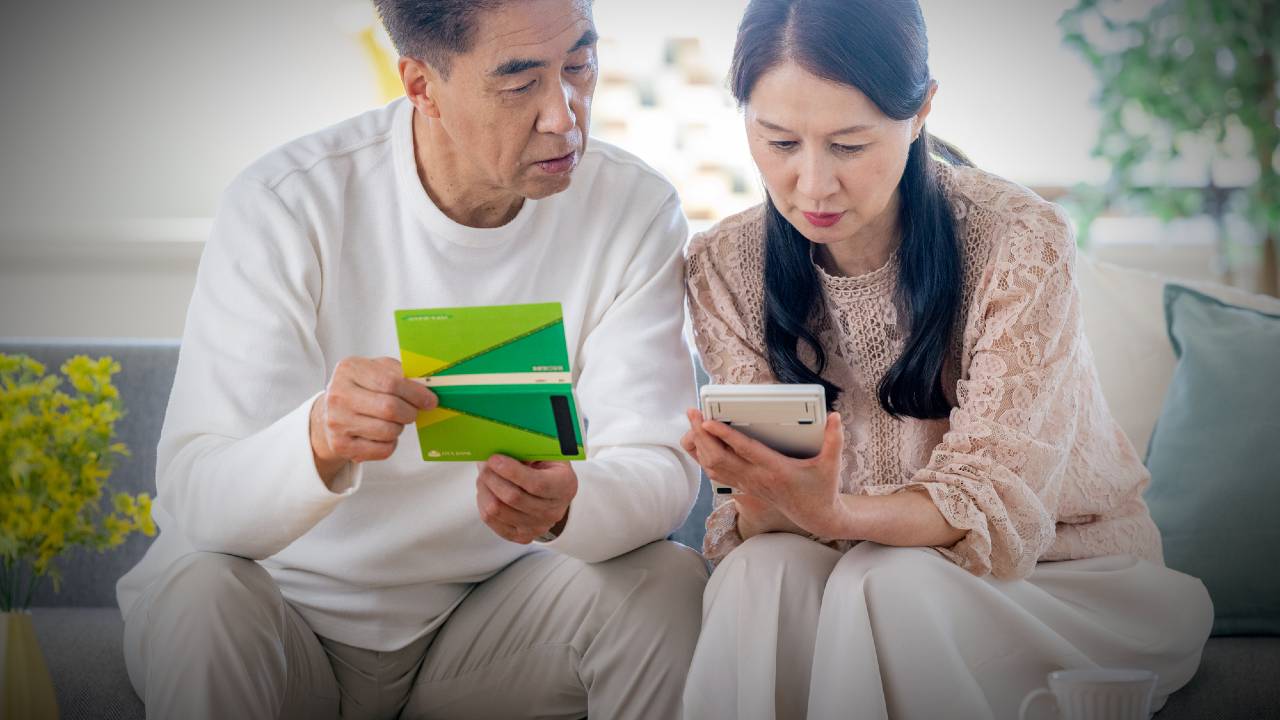ひと昔前は「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という考え方が一般的でした。年金制度もこの考えに沿ったものとなっており、夫に万が一のことがあった場合、遺された家族のために〈遺族年金〉が支給されます。では、実際に遺族年金を受給することとなった場合、具体的にいくらくらいもらえるのでしょうか。夫を亡くした専業主婦Aさんの事例からみていきましょう。石川亜希子氏FPが解説します。

年金月24万円のはずが…60歳専業主婦、サラリーマンの年下夫が急逝→唖然の〈遺族年金額〉に老後不安が止まらない「こんなの、あんまりです」【FPの助言】
“子のいない妻”が受け取れる「中高齢寡婦加算」とは
子どもがいれば受け取れた遺族基礎年金ですが、妻も被保険者に生計を維持されていたにもかかわらず、子のいる、いないによって支給の有無が決まってしまい、不公平感は否めません。
「子」がいなくて遺族基礎年金をもらえない、または、もらえていたが「子」が18歳を超えて遺族基礎年金が打ち切りになってしまった……そのようなとき、妻に支給されるのが「中高齢寡婦加算」です。
「中高齢寡婦加算」は、妻が40歳から65歳で妻自身の老齢基礎年金がもらえるまでの間、受け取ることができます。支給額は一律で61万2,000円(令和6年度)です。
つまり、Aさんが月に支給できる金額は、概算ではありますが、
【Aさんが65歳になるまで】
遺族厚生年金約7万8,000円+中高齢寡婦加算5万1,000円=約12万9,000円
【65歳以降】
遺族厚生年金約7万8,000円+老齢基礎年金6万8,000円=約14万6,000円
ということになります(老齢年金額は令和6年度)。
ただし、さらに「65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受給する権利がある場合、老齢厚生年金は全額支給、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となる」というルールがあることには注意が必要です。
不安を募らせるAさん…FPの助言に「確かにそのとおりだわ」
中高齢寡婦加算を合わせても、夫が急逝してしまったことで、Aさんが受け取れる年金は、当初予定額の5~6割になることがわかりました。Aさんは、夫との悠々自適な老後をイメージしていただけに、ますます暗い気持ちになってしまいました。
総務省の令和5年度家計調査報告書によると、65歳以上の単身高齢者世帯における家計収支の平均は、収入(年金など)12万6,095円に対して支出が15万7,673円と、月に約3万円の赤字となっています。
Aさんの収入は約12万9,000円なので、おおむね平均程度です。
「月3万円の赤字……急な出費もあるだろうし、どうしよう」Aさんがますます不安を募らせていたところ、FPから「Aさんも少し働いてみてはいかがですか?」との提言がありました。
「フルで働かなくても、働いた分金銭的な余裕が生まれます。そしてなにより、社会とつなることは精神的にもプラスに働くのではないでしょうか。Aさんはまだまだ若いです。人とのつながりを大切にして、健康寿命を延ばすことが大切ですよ」
実はAさん、結婚前は幼稚園教諭でした。長いあいだ働いていませんでしたが、現場は人手不足。幼稚園や保育園での保育補助のパートの求人は多いのです。
また、時給はパートより下がってしまいますが、地域のシルバー人材センターやファミリーサポート事業に登録し、育児の見守り(共働き家庭で子どもと留守番、習い事の送迎など)を請け負うこともできます。こういった組織では会員同士の交流もあるため、気の合う友人も見つかるかもしれません。
「実は私もファミサポ(ファミリーサポート事業)を利用していたんですよ」40代の女性FPは笑って言いました。
「そうね、確かにそのとおりだわ。時間もたくさんあるし、家にいても悲しくなるだけだもの。私が元気でいないと、夫も心配してしまうわね」Aさんは将来に対して少しだけ前向きになれたと、笑顔で帰っていきました。
あまり考えたくはないが…“万が一”への備えを
一家の大黒柱に万が一のことがあったとき、残された家族のために支給される遺族年金ですが、さまざまな要件があり、それぞれの事情によって支給される金額も異なります。
万が一のことはあまり考えたくはないものですが、元気なときに自分たちはいくらもらえるのか確認して、足りない分については事前に備えておくことが大切です。
石川 亜希子
AFP