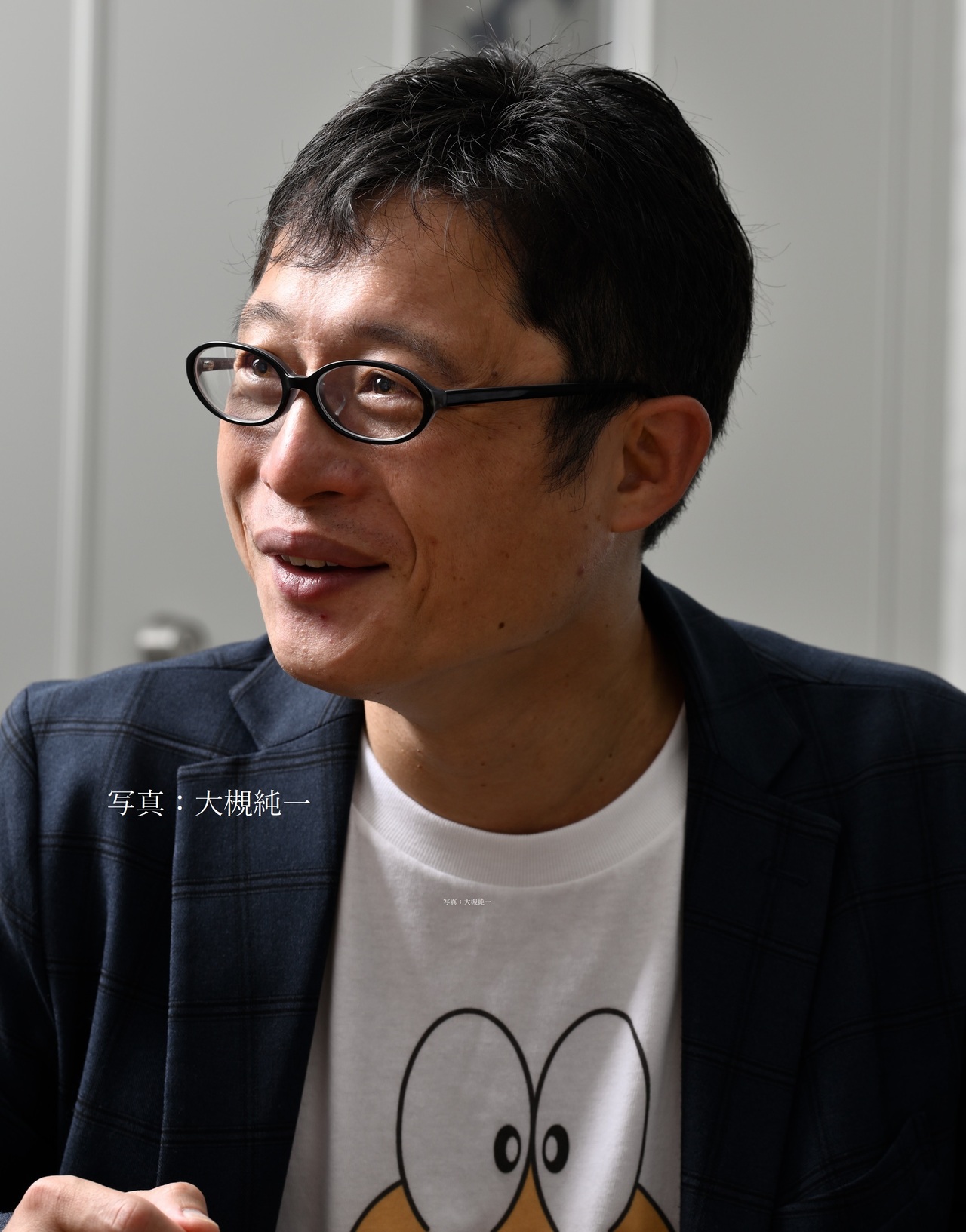代表曲『残酷な天使のテーゼ』で知られる歌手の高橋洋子さん。「『残酷な天使のテーゼ』でヒットを飛ばした後に、芸能界から身を引いて介護の仕事をしていた」時期があったと言います。本稿では、川内 潤氏の著書『わたしたちの親不孝介護 「親孝行の呪い」から自由になろう』(日経BP)より一部を抜粋し、5年間プロとして介護の現場に身を置いた高橋さんと川内さんのインタビューを紹介します。

「芸能人の君に介護の仕事はできないよ」と夫は言ったけれど…『残酷な天使のテーゼ』高橋洋子がそれでも「大変とは思わなかった」と言い切れるワケ
介護は知られていない、だから怖がられている
川内:介護に人材が集まるために、やるべきことは給与水準の向上を筆頭にいろいろありますが、高橋さんのご経験から、「こうすればいい」ということがあったら、ぜひ。
高橋:給与はもちろんですが、同時に、社会の意識を変えるためにやるべきこともあると思っています。一つは、「高校生ぐらいになったら必修科目で介護を学ぶべきだ」と。例えば、車椅子の押し方。知らない人は坂道で下に向けて車椅子を押したりしてしまう。逆に向けて後ろ向きで下りなければならないですよね。
川内:知らないとそういう恐ろしいことをやってしまいますよね。
高橋:そういう学びを学校で積極的に取り入れたらどうかなと。車椅子の押し方を知っていれば、「坂で車椅子を押している人は大変だろうな」と思えるようにもなります。重い人が乗った車椅子をデコボコ道で女性が押すのは、ほぼ無理です。老老介護をしている奥さんがだんなさんを乗せた車椅子を押しているのを街で見たりすると、泣きそうになります。
私がそう思えるのは介護体験があるから。でも、車椅子を押す高齢者を見て「邪魔だな」と思ってしまう介護「未」経験者がいるはずです。
あとは、コミュニティーの場として、幼稚園や保育園、小、中、高校、大学に、それぞれの成熟度のレベルに合わせて、老人ホームや障害者の施設でのケアに参加する仕組みが欲しいですね。そこで学生が高齢者の面倒を見たり、元気な高齢者が子どもの面倒を見たりする。
「知らない」ことが「なんとなく怖い」「自分の手に負えない」「自分とは縁がない」という気持ちにつながっていると思うんですね。それが減らせるんじゃないかと。
川内:確かに、目を背けて知らないままでいるからかえって怖くなっている面はあります。
高橋:例えば、何かのきっかけでキャーキャーと大声で喚いてしまう子も、普段は静かに、普通のトーンで話をするんです。本当に障害の形も十人十色。そういうことを知らないから、恐怖を感じてしまう。
介護にも同じことが言えて、知らないから「嫌なもの」だと思っているフシがあると思います。「自分には関係ないし、できないよ」ではなく、「まずはこのくらいならば自分にもできる」という介護体験をする場が増えてほしい。
川内:それを通して「介護は汚い、キツい」というネガティブな感情から逃れることができると、さらにいいですね。
高橋:介護に対してのそういう先入観は強いですよね。現場でも「何で自分は介護”なんか“やっているのだろう?」と口に出す人がいました。だけど、そういう人でも介護の本質に触れていくと考え方が変わっていきます。ちょっと介護体験をしただけでは絶対に分からない世界だとは思いますが、だからこそ継続して触れる機会が早めに欲しい。
編集Y:その「本質」というのは……。
高橋:誰もが年を取り、衰えていく、という事実に正面から向き合うことで見えてきます。今「高齢者の世話なんて」と言っている人も、いずれ年老いたら、重たい荷物を今のように持てなくなりますし、「障害者のケアなんて」と言っている人だって「あなたはケガを一生しないと言い切れますか?」ということです。特に、介護は絶対に必要です。
川内:高橋さんがおっしゃったように、介護が自分の人生に一切関係ないという人は、基本的にいないわけです。『親不孝介護距離を取るからうまくいく』でも申し上げましたが、できることが限られていく中で、自分の親は、そして自分は、何をしたいだろう、何だけは続けたいと思うだろう、と考える。介護はその機会を与えてくれるんですよね。