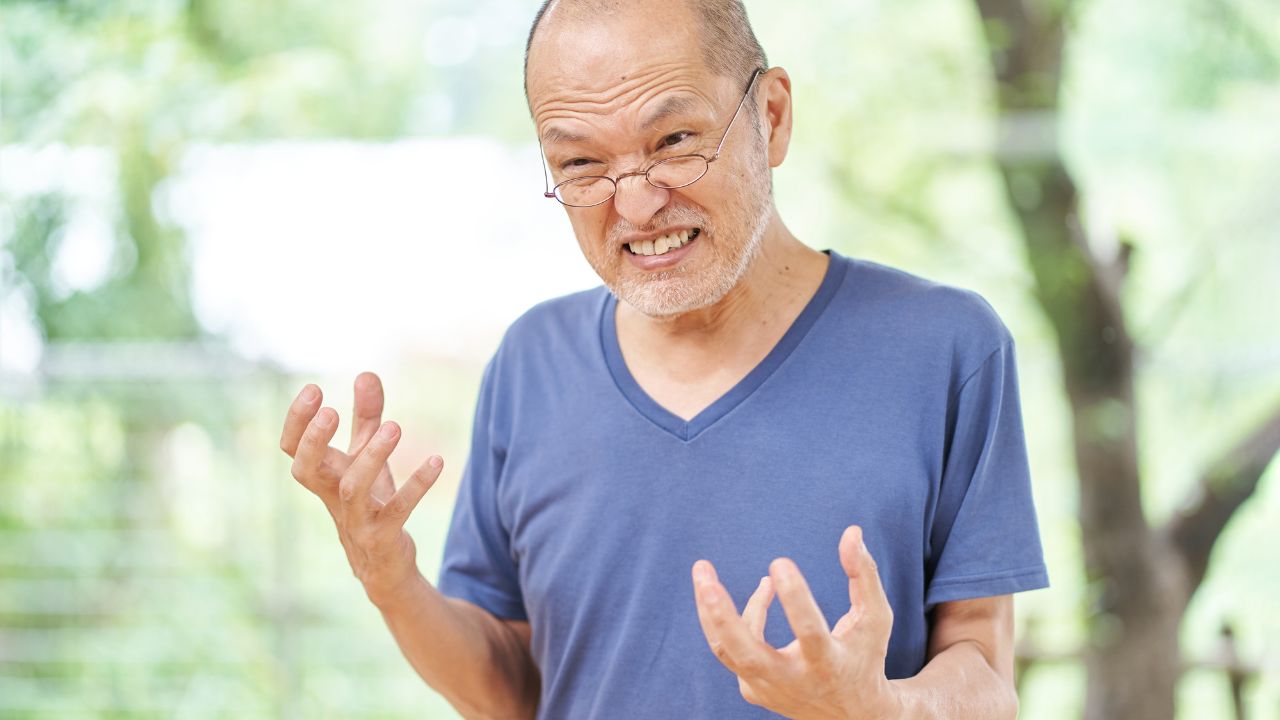人生100年時代。昨今増える「熟年離婚」は、生活や金銭のストレスだけでなく、寿命さえ左右してしまうケースもあるのでしょうか。本記事ではAさんの事例とともに、共働き夫婦の遺族年金について、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。

遺族年金56万円「妻より年金少ない夫」…60代元共働き夫婦が町内会で囁かれた「悲しすぎる悪口」【FPが解説】
離婚に合意できないまま妻が急逝
妻が定年を迎えた60歳時に5歳年上のAさんは65歳。妻は長年外で働いてきたこともあり、家事が苦手。Aさんはデザインの仕事を夜中に集中して行うことが多かったため、昼間はできるだけ静かにしてほしいといいます。
「お互いが一日中同じ家のなかにいるのは疲れるのではないだろうか」
険悪な関係というわけではありませんが、生活リズムの違いから別々に生活したほうがお互いのためと、Aさんは離婚を提案します。しかし妻は、別居には賛成も、離婚はしたくないといって合意がとれません。
そんな話し合いの最中、妻が脳梗塞で急逝します。葬儀が終わると、Aさんは管轄の年金事務所に訪れ、手続きを済ませました。Aさんは妻が亡くなるまで離婚しておらず、生計維持関係にあったため、遺族年金の請求ができたのです。遺族年金の計算は亡くなった人の、厚生年金保険の報酬比例部分の4分の3です。妻の遺族厚生年金は、
です。ただし、Aさんにも厚生年金保険期間があるため、Aさん自身の老齢厚生年金を優先に受け取り、遺族年金としては差額支給となります。そのため実際の支給額は、
です。前段のような昔ながらの家庭では、妻が先に亡くなっても夫の年金のほうが高いため、遺族年金はありません。ですが、働き方によっては男性のAさんのほうが遺族年金を受け取ることができます。
町内会で吹聴されたこと
どこで聞きつけたのか、Aさんの妻は離婚の話し合いの最中に急逝し、Aさんが妻の遺族年金をはじめ、退職金などを手にしたと、町内会で噂になります。噂には尾ひれがつき、Aさんの妻は離婚話にストレスをかかえ急逝したとか、Aさんが妻の退職金や年金を狙っていたなど、根も葉もない悪口が横行。
確かに離婚の話は出ていたものの、ストレスを抱えないための離婚の提案のため、夫婦関係が険悪になっての離婚ではありません。今回のAさんの離婚話しは、お互いが充実したセカンドライフを考えての離婚話だったかもしれませんが、一般的に離婚するには、生活・経済面や精神面でなんらかのストレスを感じることでしょう。さらに周囲があることないことを噂する悪口は悲しすぎます。
人生100年時代、多様な働き方や家庭の在り方があります。そのなかに熟年離婚や卒婚があるのかもしれません。
〈参考〉
※ 令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei23/dl/02_kek.pdf
三藤 桂子
社会保険労務士法人エニシアFP
代表