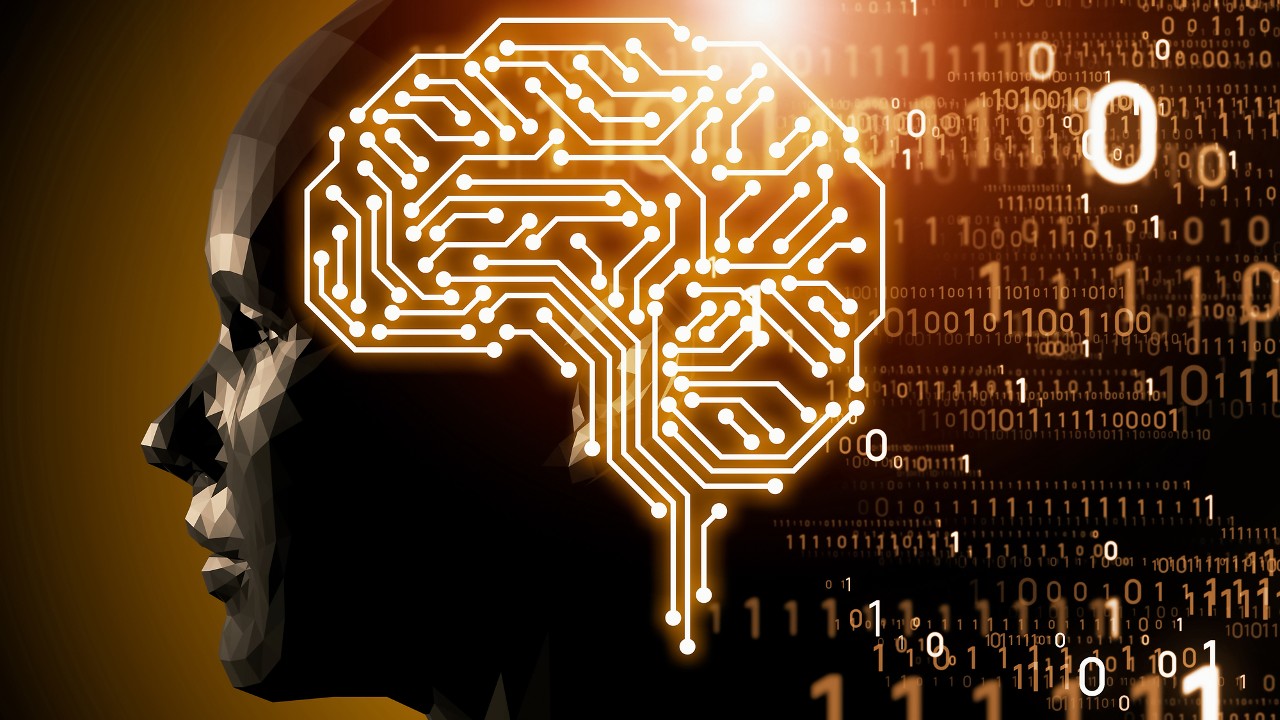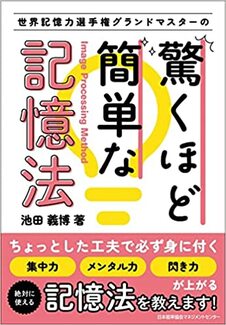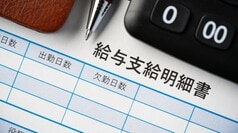記憶術を単体で使うのが難しい理由
もしかすると、本書を手に取られた皆さんの中には、すでに記憶術というものに、いろいろな形で触れてこられた方も多いのかもしれません。その方は、触れてきた記憶術に対してどのような感想をお持ちでしょうか。
正直にいって、なかなかかゆいところに手が届かないといった印象をお持ちの方もいるはずです。つまり、テクニックとしての記憶術のしくみは理解できるのだけれど、実際にそれを自分の勉強や仕事に当てはめるのが難しいというのが、感想としては多いのだと思います。それはある意味当然のことなのです。
いわゆる記憶術とよばれるものは、学問的にはどこに属するかご存知でしょうか。記憶というものを扱う学問は、形としては心理学の範疇です。しかし、心理学で扱う記憶から抽象的なものは排除して、技術としてより具体的な方法論に落とし込んだものが記憶術です。つまり、逆にいうと、具体的すぎるということです。
具体的すぎるというのは、型にはまっていることを意味しています。例えば、数字だけをたくさん覚えるとか、言葉だけをたくさん覚えるには便利なのですが、勉強や仕事で覚えたいものはそのようなものだけではないため、実用的な面に応用するのが難しいのです。したがって、記憶能力を伸ばしたかったら、記憶術だけではなく、記憶という能力を包括的に捉える必要があるということなのです。
包括的に捉えるためには、まず、記憶に関して知識の階層があることを知っておくべきです。先程述べたように、記憶術の上には心理学という階層があります。そして、その上の階層には脳科学があるのです。記憶は脳で行われるため、それも当然のことです。つまり、脳には記憶のメカニズムというものが存在しているのです。
そのメカニズムとは、脳の中で記憶に関わる部位はどこなのか、その部位はどういう働きをしてどういう性質を持つのか、そして、それらがどのように連携してどういう工程で記憶が行われているかということです。もちろん、学者や研究者のような深い知識が必要というわけではありません。簡単な特徴としくみがわかれば十分です。
私も、自分で記憶能力をアップさせるためにいろいろ調べていくうちに、脳の機能に行き着いたのですが、これを知ったことはとても大きな収穫でした。記憶に関する上位概念を知ることで、自分自身で覚える方法をカスタマイズすることもできるようになったからです。
そして、脳科学の次に位置する心理学ですが、簡単にいうと、実験などの検証で、どのような行動がどのような結果に結び付くかということを教えてくれる学問です。よく「○×効果」などの言葉を聞くと思いますが、記憶に関してもこういうものが存在します。そういう意味では、個々のものを覚えるというよりも、戦略的にどのような行動で効率的な学習ができるかといった知識を得ることができます。
【Jグランドの人気WEBセミナー】
税理士登壇!不動産投資による相続税対策のポイントとは?
<フルローン可>「新築マンション」×「相続税圧縮」を徹底解説