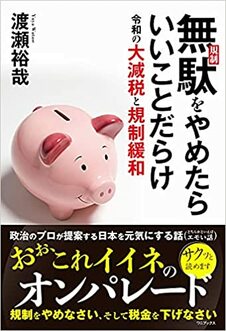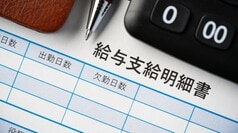米騒動で広がった「コメの代用食」としてのパン
米騒動のときには、もうひとつ非常に面白い市場原理が働いています。パン食の登場です。
白米の値段が上がって買えないけれども、何かしら食べなければ生きていけません。すると、白米以外のものを原料とした食糧を作ろうと考える人が出てきたのです。現在も「超熟」など人気商品を製造・販売する名古屋の製パン大手、敷島製パン(Pasco)の創業者、盛田善平氏です。米騒動の食糧難から、「パンが米の代用食となりうる」として、起業しました。つまり、食べ物のイノベーションを起こしたのです。
市場には、問題を解決する力があります。政府があれこれと頭を悩ませているとき、民間は「白米の値段が上がったのなら、それより安い小麦を使ったパンを作ればいいのでは」といって新しい商売を始めることができます。
小麦は、江戸時代にも水田の裏作や農民の食糧として栽培されていました。明治時代初期に36万ヘクタールの栽培面積だったものが、パン食の普及にともない大正時代には50万ヘクタールに増えます。さらに1920年代半ばからは小麦の輸入も増加していきます。徐々にパンが普及していくと、一般の消費者も手に入れやすくなっていきました。

第二次世界大戦後も、小麦は米の代用食として国民の食糧難を救うことに寄与し、現在では若い人たちがお米よりもパンを食べているとか……。日本の朝食はご飯よりもパン食が多くなるほどパンは日常の食品となっています。
ちなみに、食生活全体に影響を及ぼすようなイノベーションを起こし、新しい食べ物が生まれたのも、別に政府が「パンを作れ」と言ったわけではありません。日露戦争から大正時代当時の二大国民病のひとつ、脚気対策で海軍は洋食を取り入れましたが、せいぜい海軍で麦飯が食べられるようになった程度で、陸海軍ともにパンは普及しなかったぐらいです。
米騒動に見られるような政府の施策や、現在に至る税制といった政府の規制は、簡単に言えば、基本的には「今ある商品だけを対象にした政策」です。新しいものを生み出すのは、民間の力なのです。民間に任せておくと、何かひとつ値段が高騰すれば、それと競争する安価なもの、別の材料を使った新しいものを開発します。これは地球環境の問題とも関係します。
たとえば、エネルギーです。石油の希少価値が上がって、これまで通り使えないときには、代替となる安価な資源を見つけてきたり、もっと少ない石油で同じエネルギーを使えるような技術革新が起こったりするのです。政府の力で無理やり制限しなくても、民間は利益を上げるために必死で努力するからです。
現在、欧米も日本もCO2排出量削減への取り組みが各国政府の課題となっていますが、アメリカでもこれまで、石油・ガス産業界がCO2よりも環境負荷の高いメタン排出量を減らす努力などを続けてきたのです。筆者は、そういった民間の経営努力を評価して伸ばしていく方が、民間企業の経営努力で生み出した富の上前(うわまえ)を政府が撥ねるようなやり方よりも大切であるし、最終的には問題の解決につながっていくと考えています。
食糧の問題も同様です。日本は人口が減少していっていますが、世界の人口は年々増え続けています。食糧問題はこれから、より注目されていくことになります。「人口の伸びに対して、食べ物の供給が追い付かない!」と危機を唱える人もいますが、これまでも色々な危機があるたびに人類はイノベーションを起こして克服してきていることを忘れてはいけません。
現在、食糧の問題は牛や豚など、世界で普段食べられている家畜のように生産コストが高いものではなく、より少ない資源で栄養価の高い食糧を作ろうという方向へ進んでいます。動物性たんぱく質の代替食として脚光を浴びているのが昆虫食です。
古くから、日本にもイナゴや蜂の子のような昆虫食の習慣があります。FAO(国連食糧農業機関)は千九百種を超える昆虫を食用としており、消費人口は二十億人以上いると言われています。筆者の知り合いにも、食用コオロギを日本国内で生産している人がいるのですが、これがまた結構、儲かるのだとか……。
こうしたことも、世界人口の増加に対するイノベーションです。より少ない資源で、より栄養価が高く、ミネラルもたくさん含んでいる食糧の開発と生産・販売は、企業家精神に富んだ人たちに任せておけばよいのです。政府が余計なことをしなければ、昆虫食の需要に応じて民間で勝手に美味しく食べやすく改良もされるでしょう。
日本に限らず、世界中の政府の仕事に意義があるとしたら、統計データなどを揃えて、人口やその動態が正確に分かるようにすることぐらいです。政府が自ら何かしようとするのではなく、民間の力で問題は解決していけるのです。
渡瀬 裕哉
国際政治アナリスト
早稲田大学招聘研究員