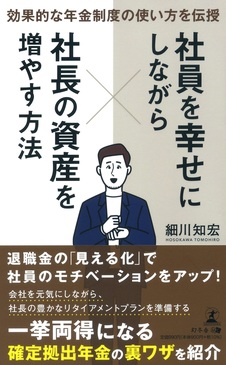本当に「2000万円足りない」?内訳を見ていくと
同報告書では、老後生活に必要となる支出に関しては、総務省「家計調査」2017年版が使われていました。前提として、夫65歳以上、妻60歳以上で夫婦のみの高齢無職世帯とされています。その毎月の支出は26万4000円くらいになると示されています。
一方、老後のメインの収入となるのは年金です。この例では、会社員として20歳から仕事をして定年まで働き、年金が約19万円、そのほかの収入が2万円弱で、約20万9000円が収入となっています。この差額となる5万5000円が毎月足りないことになります。
ただ、この前提に当てはまらない家庭も多いでしょう。
例えば、この例は、妻は一度も働いたことがなく、結婚後はずっと専業主婦だった前提です。今の若い世代で、このような夫婦はレアケースでしょう。
また、夫の65歳での退職後、老後は30年間、つまり95歳まで生きるという前提もあります。現在、実際に95歳まで生きる男性は4人に1人程度です。
さらに、この算出根拠となっている月々の支出を確認すると、酒類と外食が約1万円、教養娯楽費が約2万5000円、交際費が約2万1000円などとなっています。老後といっても60代、あるいは70代の前半で、まだまだ元気な方も多いので、これらは必要になるかもしれません。
しかし80代にもなれば、外食や交際費にそこまでのお金が必要な人のほうが少ないでしょう。一方で、住居費は約1万4000円とされています。これはおそらく持ち家を前提にしているのでしょう。もし、自宅をもたず、賃貸住宅で暮らしている人であれば、住居費がずっと高額になる可能性はあります。
このように、いくつもの仮説を重ねたうえでの金額なので「2000万円」という数字そのものには、さほど意味があるものではありません。
ここでのポイントは、高齢化・長寿化により、だれでも95歳、あるいはそれ以上の年齢まで存命する可能性はあるという点です。それにもかかわらず、年金だけでは生活費をまかなえない可能性があるということなので、年金以外にも備えなければなりません。