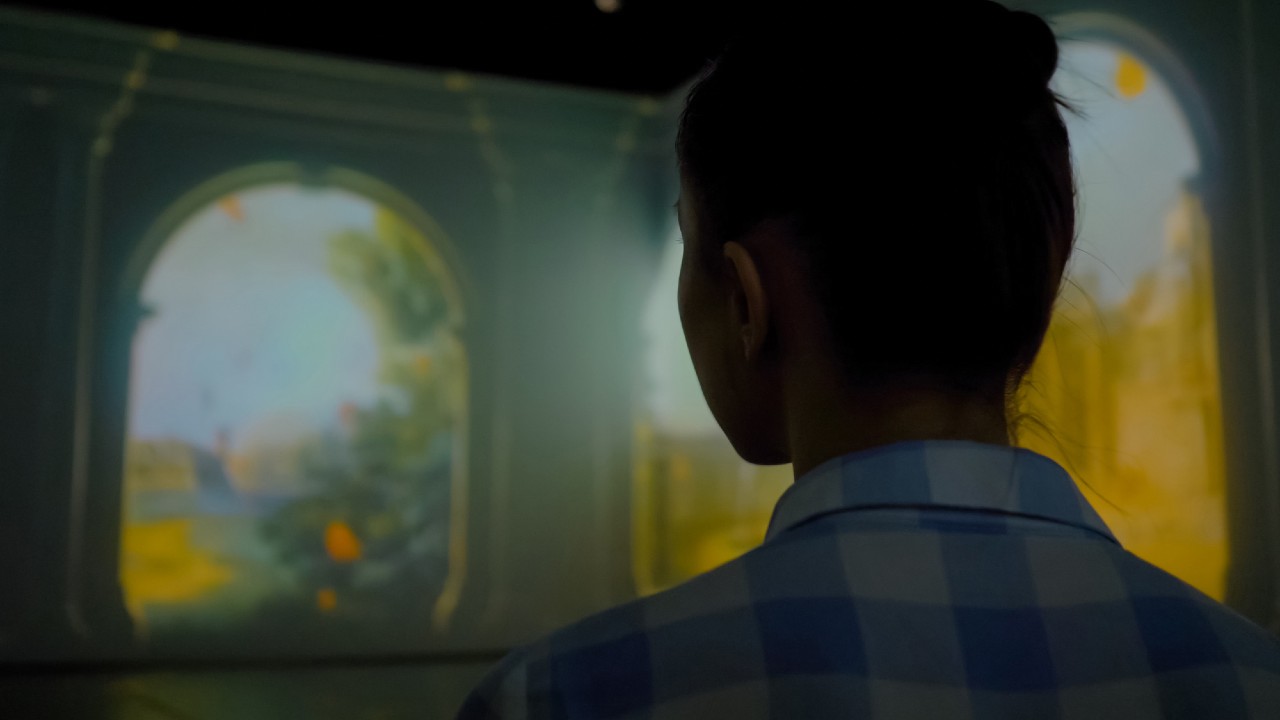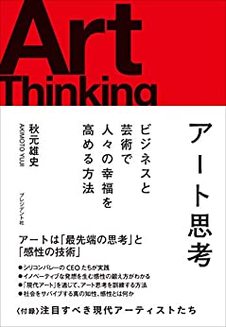精神(脳)に快楽を与える新しい芸術を提唱
デュシャンはそれまでの多くの美術作品を、「目から得られる刺激を楽しむ網膜的絵画」だとして批判します。デュシャンは、精神(脳)に快楽を与える新しい芸術を提唱すべく、《泉》を世に送り出したのです。それはただひとつだけのハンド・メイドにこそ価値があり、「美こそ善」であるといった、美術界の既成概念を打ち破るものでした。そのために彼は、あえて美から一番遠くにある便器を使って既存の価値観に意義を唱えたのです。
レディ・メイドをアートだと主張したデュシャンによって、長い歴史の中で、当たり前と思われていた芸術に対する概念が、覆されてしまったのです。
と同時に「芸術とはなにか?」という意味をゼロからつくり上げなければならない地点にまで芸術を引き戻してしまったのです。
しかし、こういうと何か終末的な気分になりますが、裏を返せば、まったくゼロから始められるものへと芸術を刷新してしまったともいえるわけですから、とんでもなく革命的なアーティストです。そして実際にデュシャン以後、様々な芸術運動が生まれました。
以後、作品は、コンセプトを重視したものになります。
他にも、通称「大ガラス」と呼ばれる《花嫁は、彼女の独身者達によって裸にされて、さえも》や遺作の《1.水の落下、2.照明用ガス、が与えられたとせよ》といった名作が残されていますが、どちらも問題文かなぞかけのようなタイトルを持つ作品です。
制作スタイルは、絵画、彫刻といったものから逸脱しており、一種の装置のようであり、現在のインスタレーション(空間設置に重点を置く作品)につながるスタイルです。
透明ガラスの上に機械を思い起こさせる金属製の形が張り付いており、それらの図像からいくつものストーリーを想像させる作品です。思わせぶりで難解なメモが存在していて、それらを参照しながら作品を読み込んでいけるようになっています。
また通常、「遺作」と呼ばれる作品は、デュシャン死後に初めて本人の遺言によって存在が明かされ、公開された作品で、観客は古い木製のドアに穿たれたふたつののぞき穴を覗き、ドア越しに見える風景を眺める装置のような作品です。