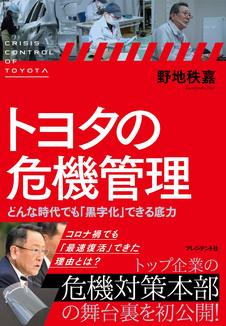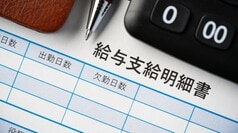「自主的に提案」経営者意識を持った社員の成長
発表に際して、「コロナ禍の有事だから」と社長の豊田章男が出席し、次のように語った。
「1番は、トヨタで働く人たちが強くなったことだと思います。
工場では、世の中が必要とするマスクやフェイスシールドの生産を自主的に行いました。非稼働日には、全員でカイゼンに取り組み、生産性が大きく向上いたしました。
販売現場では、オンライン販売など、お客様との関係づくりを続けました。
自動車は波及効果が非常に大きい産業です。雇用は550万人。納税額は約15兆円。経済波及効果は2.5倍になります。
私たちは、『幸せを量産する』という使命のもと、有事の時こそ、自分以外の誰かのために、世の中のために、未来のために、仕事をしてまいりたいと思います」
この「社員は強くなった」という意味は、物理的に頑張ったということだけではない。
豊田が例に挙げた生産現場での支援活動、カイゼン、そして、販売現場でのオンラインへの取り組みはいずれも、「やれ」と上から強制したものではなかった。
「こういうことをしたい」と現場が自主的に提案し、行われたものである。
「強くなった」とは、トヨタの社員は危機に際して、命令を待つのではなく、自分から手を挙げて動くことができる体質ができたという意味だ。
つまり、彼らは経営者意識を持ったのである。
36万人もいる従業員の大半が経営者意識を持ち、経営者の立場で考えることができるようになったのは大きなことだ。社員ひとりひとりがあたかも経営者のように会社の将来を考えて行動することができるとは究極の危機管理である。
豊田が言っているように「危機管理とは危機が来てからやることではなく、日ごろの仕事への取組みが表れる」ことだ。
なお、自動車はコロナ禍であっても決して売れていないわけではない。業界他社の見通しは次の通りである。
ホンダもまた従来予想よりも増え、営業利益は4200億円としている。
SUBARU(スバル)もアメリカを中心とする販売が想定を上回り、全世界販売91万1000台(前年予測比1万1000台増)、売上高2兆9500億円(同500億円増)、営業利益1100億円(同300億円増)と見通しを上方修正した。
日産、マツダ、三菱自動車は赤字予想である。
野地秩嘉
ノンフィクション作家