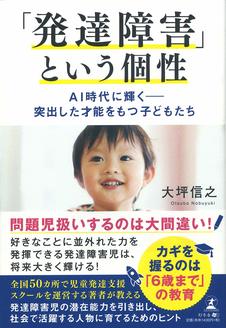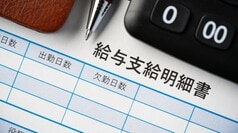なぜ、今「児童発達支援事業」が求められているのか…
>>>>>>>>記事を読む<<<<<<<<
「子どもの問題」と「親の問題」を分けて考える
昔は、子育てで出てくる問題はみんなお母さんの責任と思われていました。「あいさつができない、忘れものが多い、片付けができない……親がちゃんと育てていないから」といわれてきたことばかりです。
しかし、母親がいつも口を出していれば、子どもはやる気のある子に育つのでしょうか? そうではなく、やる気のない、依存心の強い子に育ってしまうでしょう。なかには、反抗的になる子もいるでしょう。
「やる気がない」「親の顔色を見る」「反抗的」と感じたら、親が子どもの問題に、口を出し過ぎていないか考えてみましょう。
そのような状況で、子どもの問題を親の問題と思っているお母さんは、子どもから目が離せず、とても忙しい思いをされていると思います。
子育てのゴールは、子どもの「自律であり自立」
もし、お母さんが病気になったら、子どもはどうなってしまうのでしょう?
今まで自分で問題を解決する経験がなかったお子さんは、自立するために苦労するでしょう。子育てのゴールは「自律であり自立」です。
そのゴールに向かうには、まずは子どもの問題と親の問題はわけて考える基本を、しっかりとおさえることが大切です。
「保護者が一切口出ししなくてもいい」ワケではない
子どもの問題は子どもの問題、親の問題は親の問題と分けて考えることを学びましたが、私たちは子どものすることに一切口を出さなくてもいいか、というとそうでもありません。
例えば、宿題。宿題は子どもの問題です。子どもが自分の問題で困っているときにおける、お母さんの二つの対応パターンをご紹介します。
子ども「お母さん、教えて」
お母さん「それは、あなたの宿題でしょ。学校で習ったことはわかるでしょ。早くやらないとテレビは見せないよ」
②子どもの問題を解決してしまうお母さんの場合
子ども「お母さん、教えて」
お母さん「まず、教科書を読みましょうね。そして、例題を解いてみようね。それから問題を解いたら、丸つけをしますからね」
上記の対応は、どちらも望ましくありません。
①の対応では、お母さんの助けを借りて、自分で問題を解決しようと努力する子どもを突き放してしまっています。
逆に②の対応では、お母さんが手取り足取りですべてを解決しようとしているため、子どもが自分で解決することができなくなってしまいます。
それでは、子どもが手助けを求めているときには、どのように対応すればよいのでしょうか。
注目のセミナー情報
【国内不動産】4月25日(木)開催
【税理士が徹底解説】
駅から遠い土地で悩むオーナー必見!
安定の賃貸経営&節税を実現
「ガレージハウス」で進める相続税対策
【資産運用】5月8日(水)開催
米国株式投資に新たな選択肢
知られざる有望企業の発掘機会が多数存在
「USマイクロキャップ株式ファンド」の魅力