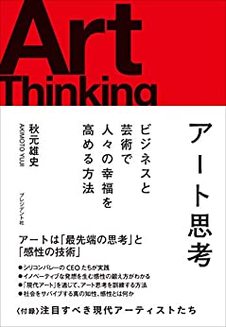今までにないアイデアを自ら発信しトレンドを作る
ものの持つ手触りや魅力の見直し
2017年、世界最大のアートフェアの開催地であるスイスのバーゼルに、突如、「バーゼル・トレゾア・コンテンポラリークラフト」という国際クラフトフェアが、登場しました。
アートフェアの世界的な開催地に、ついに工芸も登場したと、業界では話題になりました。現代アートが拡張のピークを迎え、停滞し、価格も小休止をしているタイミングだっただけに、現代アートの拡大は、とうとう工芸という別の震源地を生むのかと噂されました。
工芸と現代アートのハイブリッド化したアートに対して、ニューヨーク、ロンドン、日本など、世界各地で登場し始めたタイミングで、現代アートのコレクターの中で新しいトレンドを探している狩猟度の高い人たちが、この動きを注目し始めていました。皆が工芸の可能性を探っていただけに絶好のタイミングだったのです。
有機素材を使用する工芸と職人技術を再評価し、今のものづくりやアートに活かそうという発想は、アートへの新しい挑戦で、アートのフィールドを押し広げていく可能性を秘めていますが、これは同時にデュシャン以来のコンセプト重視の現代アートの考え方を根本から覆すものでもあるのです。つまり、テクノロジーが進化し、情報化が進んでいき、人と人のつながりが弱まり、人とものとの関係までもが希薄化してきた中で、改めてものの持つ手触りや魅力を見直そうという動きです。
工芸の国際的なプラットフォームづくりへの模索は、これだけにとどまりません。スコットランドのエジンバラで開催準備が進んでいるクラフト・ビエンナーレ・スコットランドやロンドンのクラフトウィーク、韓国のチョンジュ・インターナショナル・クラフト・ビエンナーレ、私が一、二回目のディレクターを務めた金沢・世界工芸トリエンナーレなど、新しい文化の創造とものづくりの可能性を探求する国際的な動きが、生まれています。
私自身も、金沢21世紀美術館時代に、現代アート化する工芸や新しいトレンドをつくり出している工芸を紹介する「工芸的ネットワーキング」「工芸未来派」などの展覧会を行い、これらの展覧会を台湾やニューヨークへも巡回させてきました。
こうやって今までにないアイデアや価値を自ら発信して、新たなトレンドをつくり出していくことで自分に流れを引き寄せるのです。これは、自分の思っているビジネスにピッタリとハマる場所がなければ自分でつくってしまえばいいという発想です。
秋元 雄史
東京藝術大学大学美術館長・教授
【関連記事】
税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】