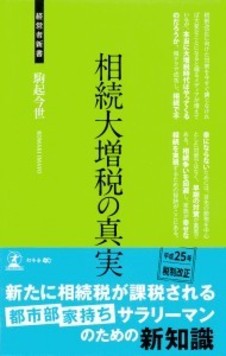長男の無関心が招いた悲劇。「あのときに…」
●一次相続時にしておけばよかった対策
田中さんの父親が亡くなったとき、すべての財産を母親が相続していました。長男の田中さんは相続に無関心だったこともあり、とくに疑問を抱かなかったのです。
しかし、田中さんは両親と離れて生活をしていましたが、介護のために母親が住むマンションに引っ越しをしています。であるならば、一次相続の際に財産の全額を母親に相続させるのではなく、たとえば母親の介護を行う名目のもと、田中さんがマンションの共有名義人になり、持分を2分の1ずつにするなどの方法がありました。
そうすれば姉の法定相続分の額が減り、田中さんが姉に現金で支払う負担が軽減できたはずです。一次相続だけにとらわれるのではなく、その先の二次相続も考えた対策を事前に講じておくべきだったという教訓といえるでしょう。
●二次相続までに考えられる対策
今回のケースでは遺言書がありませんでした。よって母親が元気なうちに、すべての財産を田中さんに相続させる旨の遺言書を書いておく方法があります。ただし、長女の遺留分の1500万円(特別受益がある場合、その分を差し引いた額)は長女の請求により支払う必要があります。
遺留分とは、相続財産のうち、相続人に法律上、必ず残しておかなければならない割合額をいいます。今回のケースでいえば、長女の遺留分は2分の1のため、法定相続分3000万円の2分の1の1500万円となります。
あるいは、母親が生前に田中さんの子ども1人と養子縁組をする方法もあります。そのうえで田中さんと、養子縁組をした子どもの2人に、すべての財産を相続させる旨の遺言書を書いておくのです。そうすれば法定相続人が1人増えるため、長女の遺留分は1000万円で済みます。
この事例は500万円程度の話なので、できる限り戸籍を汚したくないという気持ちもありますが、金額が大きくなれば養子縁組の効果は大きくなります。これらはあくまでテクニックにすぎません。それぞれの家族の置かれた状況に応じて、どうすれば相続問題に発展させず、穏便に解決する道筋を開けるのか、その視点に立って対策を検討してもらえたらと思います。
【関連記事】
税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】