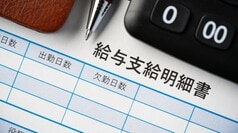脳の約9割は「6歳まで」に作られる
「幼児期の教育が重要だ」といわれるのには、理由があります。幼児期には、大人になってからとは比べ物にならないほどに、脳の配線が爆発的に成長するのです。
生まれたばかりの赤ちゃんの脳の重さは、平均して約320グラムですが、6歳になる頃には約1,300グラムにまで爆発的に大きくなります。
この爆発的な成長は、脳細胞が増えているわけではありません。脳細胞を結んでいる結合部分のシナプスや、その間の配線が伸びることによって、重さが増しているのです。
大人の脳の重さは、平均して約1,450グラムです。大人になってからは、脳の重さはほとんど変わりません。このことから、脳の約9割は6歳までに作られているということがわかります。
幼児期の脳は、たった1ヵ月で大人の10年分の発達を遂げるといわれているのです。
「養育環境」は、脳の配線状態に絶対的な影響を与える
それでは、脳の配線の状態の違いは、どのようにして生じてくるのでしょうか。これについては、現在2つの説が有力とされています。遺伝子の違いによるものであるという説と、育てられた環境の違いによるものであるという説です。
【WEBセミナー 開催】
数ヵ月待ちが当たり前?
社会問題化する「初診待機問題」を解決する
「発達支援教室」×「児童精神科クリニック」
こんな実験があります。ネズミの脳の発達を調べるために、同じ母親から生まれたネズミをAとBの2つのグループに分け、環境を変えて育てました。
実験の結果、遺伝的には同じであるはずなのに、育てる環境が異なるために、AグループとBグループのネズミたちの脳の配線は全く違った状態になったのです。
また、人間においても同じことがいえます。一卵性双生児であっても、育てられた環境が変わると脳の配線の状態も変わってくるという調査結果が出されています。
遺伝と脳の配線の状態とが全く無関係であるといい切ることはできません。しかし、少なくとも、育てられた環境は脳の配線の状態に絶対的に影響を与えるのです。

「読書家の遺伝子」や「楽才の遺伝子」は存在しない
読書を好む夫婦から生まれた子どもが、同様に読書を好むようになったとします。これは遺伝子の働きによるように見えますが、実際には読書好きの遺伝子というものは存在しません。
本をよく読む家庭環境に育った子どもは、本と触れ合う時間が長いために読書の面白さを覚えます。
両親が読書をする姿から受ける影響も大きいでしょう。このようにして育った環境によって読書を好むようになるのです。
一家全員が音楽の才能に恵まれている音楽一家というものがありますが、これも同じことです。生まれたときから音楽にあふれる環境にあるために、自然と音楽に親しむようになるのです。
能力も人格も「天才」も、6歳の時点で決まる
幼児期にしか身につかない能力があります。絶対音感は6歳までにしか身につかないといわれています。
6歳を過ぎると、脳の配線がほとんど成長を終えてしまい、残り10%ほどしか発達の余地がないからです。
幼児期にしか身に付かない能力は、絶対音感だけに限りません。すべての脳を使う資質が、6歳までに9割がた決定してしまうのです。
このことは、能力だけではありません。基本的な人格も9割がた決定してしまうのです。逆にいうと、6歳までであれば、どんな能力も開発することができます。赤ちゃんの頃はみんな天才なのですから、そのまま大人になることができればすべての人が天才になれるのです。
このように、幼児期の教育環境が人間の人格と能力を育む鍵なのですね。
【WEBセミナー 開催】
数ヵ月待ちが当たり前?
社会問題化する「初診待機問題」を解決する
「発達支援教室」×「児童精神科クリニック」